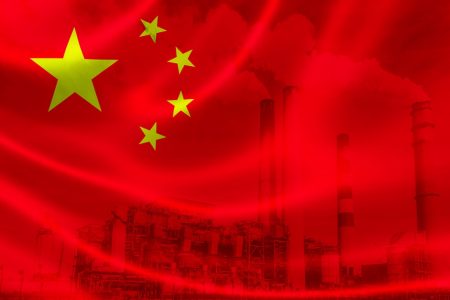地獄への道は善意のレンガで敷き詰められている
石炭バッシングで世界が失う未来
堀井 伸浩
九州大学大学院経済学研究院 准教授
やや旧聞に属するが、トランプ大統領が公約通り、パリ協定から離脱し、地球温暖化問題への取り組みを行わないと発表した。離脱発表前から、石炭に係る環境政策と鉱業権を見直し、利用を拡大することも表明していた。同大統領の主要な支持層、ラストベルト(錆びた工業地帯)にはアパラチアの炭鉱も含まれていることも公約の背景にあったとされ、早速米国の石炭業界は離脱歓迎のコメントを出した。
現実には米国の石炭産業の復活は容易ではないと見られる。米国の石炭消費低迷は環境規制の影響よりもシェールガス開発によるガス火力の競争力の向上に打ち負かされた、というのが実態だからだ。経済性に劣る石炭を政策で横車を押して利用促進するとしたらロクな結果にならないだろう。
しかし世界的に見れば米国の状況とは逆に、石炭はむしろ経済性という大きな利点があるのに「環境原理主義」によって不当に利用を制約されている。言わば、石炭は人気に恵まれず出場機会を奪われている実力選手であって、エコひいきしてもらう必要はない。とは言え、足を引っ張り続けるのは見過ごせない、最近の石炭バッシングは目に余るものがある。
例えば、2016年5月には英国・オックスフォード大学のスミススクールが、日本の電力各社の石炭火力増強計画に対し、今後環境規制が強化されることになればガス火力や再生可能エネルギーの競争力向上によって、石炭火力が「座礁資産」(Stranded Assets)、すなわち投資が回収できず不良債権化するというリポートを公表した。石炭火力の発電が上で挙げた要因で15年先に不能となった場合、座礁資産の額は616.2億ドルに及ぶ可能性があり、投資家は日本の電力会社が抱えるリスクを認識する必要があると警告している注1)。
他にも化石燃料からの投資撤退(Divestment)を年金基金など機関投資家が進め、化石燃料を利用するプロジェクトに資金が供給されない状況が広がりつつある。投資撤退を表明した機関や個人の運用総資産額は5兆ドルにも上るとされる注2)(柳 [2017])。機関投資家が化石燃料からの投資撤退を決める背景には、パリ協定によって気候変動対策の長期目標が一応定まり、それを投資戦略に反映させている、という面は確かにあるだろう。他方で、化石燃料からの投資撤退の動きの広がりは環境NPOなどが10年ほど前から投資撤退を陰に陽に働きかけてきた(率直な言い方をすれば圧力をかけてきた)結果でもある。パリ協定以前にも、特に欧米系の国際援助機関が最貧国を除く途上国の石炭火力発電所建設プロジェクトを融資対象から外す方針を掲げており、最近では石炭火力への支援を継続している日本の援助機関に対する圧力が増しつつある。環境NPOなどが投資撤退をツールとして用いて、いわば兵糧攻めを行うことで化石燃料を締め上げようとしているのだ。
化石燃料の中でも最も槍玉に上げられているのは石炭である。しかし果たして石炭という資源を活用することなく排除して、死蔵してしまうことは正しい判断なのだろうか?石炭はシェールガスの商業生産に成功したアメリカ国内を除くと、多くの国で化石燃料の中で最も安価である。問題は環境負荷が高いことであるが、従来型の大気汚染(SO2やNOxなど)については対策技術が普及しており、その導入コストを負担したとしてもコスト競争力は高い。確かに気候変動への対策技術は未だ開発途上であるが、石炭利用で生じるその他の環境問題については対策技術が存在し、環境負荷は制御可能である。
本稿は、石炭バッシングによって世界が被る損失は具体的にどのような形でもたらされるのかについて議論する。石炭バッシングによる損失は石炭よりも割高なエネルギーを使うことで、本来は別の目的に使えた資金が失われることによって生じる(経済学で言うところの「機会費用」)。それは百年先のリスクに対処するために、現在抱えている問題への対応を犠牲にする行為である。また競争ではなく、人為的な政治介入により石炭を排除することは石炭利用の環境負荷を大幅に削減する可能性のあるイノベーションを阻害する可能性も高い。それは同様に、気候変動対策に要するコストを結局高いものとし、他の重要な社会課題解決に向けた資源を食い潰すことになる。石炭を競争の結果ではなく(環境に及ぼすコストを反映した上での競争も炭素税などで環境コストを価格に反映することで可能である)、政治的に問答無用で排除しようとすることは結局将来の気候変動対策にも悪影響を及ぼすのではないか、という点について以下、考察する。
パリ協定の下でのエネルギー需要見通し
現状において世界全体の気候変動対策を包括するパリ協定の下で、石炭利用はどのような影響を受けると考えられるだろうか、まずこの点から見ていこう。IEA [2016]では、パリ協定において各国がコミットした温暖化ガス削減目標(NDC)を反映した「新政策シナリオ」を示している。この「新政策シナリオ」によれば、2040年のエネルギー消費量は2014年比で約30%増加する。OECD諸国では4%の減少であるのに対し、非OECD途上国は51%の増加となっているためだ。経済発展段階の違いを考えれば当然と言えよう。
個別のエネルギー毎に見ると、化石燃料は2014年に81%のシェアを占めていたが、2040年には74%へと低下する一方、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは大きく成長することが見込まれており、一次エネルギーに占めるシェアは2014年の13%から20%に上昇、発電に占めるシェアも22%から36%にまで上昇する。他にはガスが2014年比で49%と化石燃料の中で最大の増加を示す見通しである。
しかし実は石炭消費も5%増加する見通しで、発電に占めるシェアは2014年の41%から2040年には28%へと低下するものの依然として最大の電源であり続ける。世界最大の石炭消費国である中国、そして米国、EU、日本、韓国では石炭消費は縮小する見通しであるが、インドでは大幅に、他にASEAN諸国やアフリカでも石炭消費は増加する。これまでの主要な石炭消費国が消費量を減らす一方、新たな国々がそれを上回って消費を拡大するというこの点は重要である。そうした国々の石炭利用技術のレベルが低く、従来の石炭消費国からの技術移転が気候変動対策として重要な意味を持つ可能性があるためである。
「新政策シナリオ」が示すのは、パリ協定における各国のNDCが達成された場合でも2040年の世界のCO2排出量は2割弱ほど増加するという「不都合な将来」である。2100年時点での気温を産業革命前と比べて2度以下の上昇に抑えるという目標を達成するにはCO2排出量を更に半減させる必要がある。その点ではパリ協定は画期的な成果ではあるが、理想にはまだ程遠い、ということになるのだろう。CO2排出量半減に沿ったシナリオをIEAは「450シナリオ」として示しており、それによると例えば風力や太陽光などの再生可能エネルギーによる発電を「新政策シナリオ」よりも6割以上増やし、ガスは4割減、石炭に至っては8割近い削減をしなければならないことになる。
途上国では優先すべき緊急課題が山積
それでは、世界は気候変動対策を更に強化して「現時点で」この「450シナリオ」の実現に向けて動くべきだろうか?筆者はそうすべきではないと考えている。理由は以下の通りである。
まずパリ協定が合意に漕ぎ着けたのは、世界全体の目標を決めてトップダウンで排出削減を割り当てるのではなく、各国が自発的に自らの目標を設定し、その実現に向けた取り組みをコミットする方式を採用した点が大きい。「新政策シナリオ」と「450シナリオ」の間のCO2排出量のギャップは各国が経済成長や投資余力などの制約を勘案した上で受け入れ可能な現実的な解と理想との間のギャップと言える。「450シナリオ」のように再生可能エネルギーへの傾斜を極端に強め、ガスや石炭の利用を大きく制限することは市場メカニズムで進むはずもなく、気候変動対策のコストを高騰させる懸念が強い。
とりわけ逆風に晒されている石炭について言えば、「新政策シナリオ」の2040年時点での発電コスト予測では、規制の影響を受けて米国やEUでは石炭はガスよりも、更には風力や太陽光(メガソーラー)よりも割高となっているが、中国では石炭と他のエネルギーは概ね同水準、インドでは依然として最も安価な電源のままである。インドに代表される今後高度成長を実現しようとする途上国にとって、エネルギーコストは極力抑え、浮いた資本をインフラ整備や技術開発、社会保障に用いようとするのは当然であり、望ましいことである。
何よりも低コストで安定したエネルギーを必要としている地域がある、サブサハラアフリカである。同地域では2012年時点で6億2500万人の人々、すなわち人口のおよそ3分の2が電力供給を受けることが出来ない状態であり、2040年には世界全体の無電化人口のうちサブサハラアフリカが占める比率は75%へと上昇する見通しである(IEA [2014])。
皮肉なことに、サブサハラアフリカは世界の石油・ガスの確認埋蔵量の3割を有する資源豊かな地域であるにもかかわらず、採掘した石油・ガスを自ら利用できず、大半が輸出に回されている。国内では石油・ガスによる発電コストを負担する経済力がないためである。その結果、水力資源に恵まれた一部の国と経済的に豊かな南アフリカを除けば、工業化に、ひいては経済成長に必要な大規模発電所がほとんど存在しない状況となっている。安価な石炭注3)を活用することでこの制約から解き放たれる希望がある。
気候変動という地球規模の問題への対処が重要な点は否定しないが、他にも優先して解決すべき緊急課題が途上国においては山積している事実を忘れてはいけない。そしてその多くは途上国が経済成長するだけで解決に向かうと期待できる。年に一度の気候変動枠組条約締約国会議(COP)は華々しく先進国メディアが好んで報道するのに対し、途上国の開発問題は地味な話題ということか、注目を受けることは少ない。しかし取り組むべき課題の優先度とメディア、ひいては人々の関心は一致しているわけではないのである。
- 注1)
- このリポートに対しては、本サイトに掲載された有馬 [2016]において、議論の前提の非現実性と用いたデータの恣意性、信憑性について詳細な批判がなされている。有馬氏は後にオックスフォードリポートの筆者の一人と直接議論する機会を持ったが、先方からは同氏の批判に対する有効な反論は一切なかったようだ(有馬 [2017])。
- 注2)
- 総資産額を公表していない20%の機関が集計の対象外であり、そのうち投資撤退の宣言をした機関の総資産額である点には留意が必要である(Arabella Adviser [2016])。
- 注3)
- 現状において、アフリカの石炭生産量は2.6億トンと世界シェアは3%程度に過ぎず、しかもそのほとんどが南アフリカによるものである。南アフリカ以外のアフリカ諸国では現状では石炭の採掘コストが高く、競争力があまりないのが実態のようである。しかしアフリカにおける石炭資源探査は現状では低いレベルに止まっていること、将来的に大規模鉱床が開発されるようになれば規模の経済性が働き、採炭および輸送コストが低下することも期待できる。また石炭の利用技術および環境対策において効率向上、コスト低下の実現性も十分に考えられる。
理想へのアプローチはイノベーションで効率的に
気候変動による影響を抑制するために「450シナリオ」が示す理想を目指すことはいずれ必要であるが、その実現が求められるデッドラインまでにはまだ数十年の長期のリードタイムが与えられている点を活用するべきだ。なぜならその間、新たなイノベーションが生まれ、革新的な対策方法が生まれる可能性が存在するためである。大切なことは現在存在する選択肢を排除せず、幅広くイノベーションを促す制度を構築することである。理想と現実のギャップを埋めるためにはイノベーションを通じた、対策コストの低減による効率化が不可欠である。その意味で石炭を問答無用で排除しようとする風潮は改められるべきである。石炭の高いCO2排出強度を軽減するイノベーションが思ってもみない方向から生じることも期待できるのに、石炭利用を制限することはそうした技術開発の芽を摘む懸念がある。
もちろん対策を全て後回しにすれば良いと言っているわけではない。その点から、各国が背伸びをすれば達成可能と考えたパリ協定はイノベーション促進に有効であるため、実現に向けて米国もコミットするべきだろう。具体的な措置として、例えば炭素税のように環境負荷のコストを価格に内部化することは、環境面のコストも含めた石炭の真のメリットとデメリットを明確にし、イノベーション創出に向けた投資リターンを企業が判断する上で有用である注4)。イノベーションの担い手である企業にとっては、突然石炭利用が禁止され、「座礁資産」になる懸念が存在する状況では投資に踏み切れないが、削減すべき排出量が明確にされ、そのためのコストが税率という形で示されれば、企業はコストとリスクを勘案し、必要な投資判断を行える。
現状は石炭利用に付随するリスクを政治的要因で不当に高くすることで、イノベーションに向けた投資が大きく毀損されている。例えば、過去10年、再生可能エネルギーには8000億ドルの補助金が投じられたのに対し、CCS(炭素貯留・分離、Carbon Capture and Storage)への投資はわずか200億ドルに止まる。こうした歪みを正し、イノベーション支援はイコールフッティングにすべきである。
再生可能エネルギーの導入を進めるとしても、ドイツの経験などが明らかにしていることは電力供給の安定性を確保するためには間欠性のある再生可能エネルギーの導入には自ずと技術的な上限量があり、出力調整が可能な電源を相当量今後も運用し続けていくことになるという見通しである。そうだとすると、再生可能エネルギーの導入支援にばかり経済的資源を集中させ、化石燃料からの排出対策であるCCSへの支援を怠ってきたことは結局長期的な排出削減ポテンシャルを毀損してきた可能性もある。CCSが実用化すればより大きな量の削減をより安価に達成できるかもしれなかったということだ注5)。
「環境原理主義」のくびきから脱し、真に持続可能な対策を
確かに固定価格買取制度を中心とする導入支援によって再生可能エネルギーのコストは大幅に低下してきた。しかし割高なコストと消費者が支払う電力価格とのギャップを埋めるために投じられた補助金は莫大な金額であり、その資金を他の技術開発に回していればより効果的な排出削減が得られたかもしれない、という観点から買取制度の効果と是非を検証するべきなのである。そして繰り返しになるが、その資金の振り向け先は何も気候変動対策でなければいけないわけではない。従来型の大気汚染のようにいままさに直接人々の健康に悪影響を及ぼす問題ならともかく、気候変動より優先すべき課題が途上国はもちろん、先進国でも多数存在しているのである注6)。
それにもかかわらず、「環境原理主義」は環境が中心で全てに優先するという信念に基づき行動する。しかしながら、例えば国連の持続可能な開発目標(SDGs)には17の目標が掲げられており、低炭素な再生可能エネルギーの利用と気候変動対応はそのうちの2つ(目標7と目標13)に過ぎない注7)。目標1は貧困からの脱却、目標8は経済成長による雇用確保であり、国連はこれらの目標の均衡ある同時達成を求めている。「環境原理主義」はその均衡ある達成を実質的に否定するものといわざるを得ない。新政策シナリオと450シナリオとの間に埋められないギャップがある状況において、すなわち解決のための現実的な技術を有しない現状においては、化石燃料を最も効率的にかつ最低限必要な量を利用する権利はどの国にも等しくあると言うべきであろう注8)。
CCSの孤立無援に比して、再生可能エネルギーが偏重されてきたことが示すのは、社会に「環境=絶対善」というイメージが広がっているために、「環境原理主義」のそうした行動は制されることなく、許容されがちであるということである。「環境原理主義」は錦の御旗を振りかざし、化石燃料からの投資撤退を投資家に迫り、石炭火力を「座礁資産」であると脅すまでにエスカレートしている。本当に石炭火力が「座礁資産」になるとしたら、それは「環境原理主義」が政治的に立ち回ってそこに追い込むからだろう、まさにマッチポンプである。彼らは気候変動を解決することが世界をリスクから解き放つという善意に突き動かされて行動しているのかもしれないが、地獄への道は善意のレンガで敷き詰められているという言葉が頭に浮かぶ。
善意の暴走の結果、社会はより重要な問題に取り組むための経済的資源を侵食され、より効率的に気候変動に対処することを可能にするイノベーションの芽を摘み取られる。そして世界は本来実現したはずの未来よりも、多様なエネルギー・技術がより効率的な、経済性のある対策を目指して競争する場合よりも悪い状態となる。百年先にデッドラインが来る問題を優先したがゆえに、一刻も早く取り組むべき問題の解決が遅れてしまう。気候変動という長期的な問題に対処する際には、当面は多様な技術の選択肢の幅を狭めることなく、様々な選択肢の間でイノベーション競争を促進すべきである。石炭利用を問答無用で排除しようとする画策を放置してはならない、我々のより良い未来が犠牲にされるのである。
- 注4)
- 現時点の1トンのCO2排出が将来にわたって及ぼす環境被害額(炭素の社会的費用という)を割引率3%で現在価値にすると、約40ドルとする試算がある。気候変動とそのもたらす被害の予想には不確実性があるのでこの試算が唯一絶対のものではないが、炭素税率の一案となりうるだろう。ただし、最近の欧州の炭素価格(5ユーロ前後)や米国の一部州の炭素価格(北東部5ドル前後、カリフォルニア州13ドル前後)と比べて法外に高く、先進国でさえ、高額の炭素価格設定が容易ではないことを示している。また、米国のニューヨーク州とイリノイ州は既設の原子力発電所への補助制度を今年開始し、補助額の算定に約40ドルという炭素の社会的費用を用いているが、税ではなく、補助金であるがゆえに導入可能であったと思われる。
将来時点のCO2排出はより大きな被害を引き起こしうることから、仮に税率を40ドルに設定できたとしても、その数字で固定せず、徐々に引き上げていくべきとの議論もあるが、筆者は引き上げには慎重であるべきだと考える。その理由は本文でも主張している通り、対策を断行しなければならないデッドラインまでまだリードタイムがあり、当面は世界の経済をより成長させる用途に資金を回す方が社会の負担を小さくできるためである。
また石炭には安定供給の面で優れているという特性もあり、その利点を価格に反映することは容易ではないが、メリットとして勘案すべきとも思われる。
以上の点は、電力中央研究所社会経済研究所の上野貴弘主任研究員から示唆を受けた - 注5)
- 但し、残念ながら、CCSの実証プロジェクトは近年中止、撤退が相次いでいる。IEA [2010]では450シナリオにおける2035年に向けた必要削減量のうちCCSは26%の貢献が見込まれていたが、IEA [2016]での2040に向けた必要削減量に占めるCCSの割合はわずか8%にまで低下した。他方、再生可能エネルギーは18%から39%に上昇している。しかしこの結果は決して再生可能エネルギーがCCSよりも効率の良い削減技術であったことを全く意味しない。本文で指摘した通り、再生可能エネルギーを偏重し、導入を促進する政策がとられてきた結果に過ぎない。
- 注6)
- 先進国でも石炭火力という選択肢を排除すべきではない理由のひとつに、本文でも述べた通り、パリ協定の下でも今後途上国で石炭利用は拡大すること、しかも現在の主要な石炭消費国に代わって新たな国々が消費を拡大する見通しである点が指摘できる。新規の石炭利用国の技術レベルは低く、従来の石炭消費国、特に日本を始めとする先進国からの技術移転がそうした国々の排出量を抑制することが期待できる。すなわち、先進国でも石炭利用を継続することは石炭利用技術のイノベーションを生み、途上国への技術移転を通じて世界全体の排出削減にきわめて重要な役割を果たす可能性がある。
- 注7)
- しかも目標7は「すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する」という内容であり、「手ごろで」という表現で経済性の重要性についても配慮がされている。
- 注8)
- この論点については、本部和彦・東京大学公共政策大学院客員教授より示唆を頂いた。
<参考文献>
- ・
- 有馬純 [2016]「オックスフォード大の石炭火力座礁資産化論に異議有り」国際環境経済研究所オピニオン、
http://ieei.or.jp/2016/05/opinion160526/ - ・
- 有馬純 [2017]「オックスフォード大の石炭火力座礁資産論に異議あり ー後日談ー」国際環境経済研究所オピニオン、
http://ieei.or.jp/2017/02/opinion170227/ - ・
- 柳美樹 [2017]「化石燃料投融資撤退、『Divestment』の潮流-日本へのインプリケーション」(一財)日本エネルギー経済研究所 第63回研究報告・討論会「世界のエネルギーミックスと石炭の役割 ~逆風下にある石炭の位置づけを考える~」報告会資料
http://eneken.ieej.or.jp/data/7278.pdf - ・
- Arabella Adviser [2016] “The Global Fossil Fuel Divestment and Clean Energy Investment Movement,”
https://www.arabellaadvisors.com/wp-content/uploads/2016/12/Global_Divestment_Report_2016.pdf - ・
- International Energy Agency (IEA) [2010] World Energy Outlook 2010, OECD/IEA
- ・
- International Energy Agency (IEA) [2014] Africa Energy Outlook: A Focus on Energy Prospects in Sub-Saharan Africa, OECD/IEA
- ・
- International Energy Agency (IEA) [2016] World Energy Outlook 2016, OECD/IEA