パリCOP21を目前にして、気候変動問題についての取り組みを考える
書評:有馬 純 著「地球温暖化交渉の真実 - 国益をかけた経済戦争」
桝本 晃章
元東京電力副社長
主席研究員:有馬 純氏が国際環境経済研究所にWebsiteに連載をしていた「私的京都議定書始末記」が追記され、中央公論新社から新たに出版された。すでに、竹内純子主席研究員が本Websiteでも書評をしている。本のタイトルは、「地球温暖化交渉の真実…国益をかけた経済戦争」である。シニアの評者も、改めて読み直してみた感想などを綴ってみたい。
<大気に“国境”なく、地上に“国境”あり>
この本のサブタイトル:「国益をかけた経済戦争」は、気候変動対策を巡る国際枠組み作りについての国連での議論の本質である。気候変動対策という地球全体の大きな課題への取り組みが何故に“経済戦争”になるのだろうか。
その基本的背景は地球と人類のかかわりそのものに戻る。大気に国境はない。しかし、地上には、国境で区切られた“国”がある。国連の国際交渉の場では、国単位で議論が進められている。過去、産業革命以降化石エネルギーを大量に利用し、温暖化ガスをいやというほど排出して豊かになった先進国。さまざまな経緯をたどって現在に至った発展途上国。途上国といっても色々だ。ここ3、40年の間に、経済成長へのテークオフを果たし、急成長をしつつある中国とインド。それを追う中南米やアフリカ諸国。中東の産油・産ガス諸国も急追している。過去10年、20年で見ると、今では中印新興経済を筆頭に途上国は、大量の化石エネルギーを消費し、地球上の温暖化ガス排出増加分のほとんど全量をもたらしている。全地球における排出比率も、京都議定書が出来た頃に比べると先進国諸国にとって代わった。
一方、EU・ブラッセルは、加盟28カ国を強力に主導しつつ、日米などの先進諸国に対して排出削減と厳しい目標設定という強い要求をぶつけ、この問題で世界のリードをしようとしている。EUの背景には、開始して既に10年を経過した欧州域内排出量取引制度(EUETS:European Union Emission Trading Scheme)がある。トップダウンによる排出量の割り当て、そして、世界規模の排出量取引市場形成という野望である。始められた頃は、この取引市場規模は、将来、一兆ドル、あるいは、二兆ドルにも達すると期待されたのだ。排出削減のための国際枠組みつくりが経済戦争になる背景である。
<地球上には多くの課題、そして、限りある投入資源>
問題は、もうひとつある。
現実の地上には、多様な国があり、貧富の格差は大きい。最大の課題は、対策に要する投入資源:資金、人材、技術、さらに、時間に限りがあるということだ。何といっても、世界には課題が多く、投入資源は幾らあっても足りない。
2000年の国連ミレニアム宣言を中心に、地球上の緊急を要する人類の課題を見ると、次のとおり難題ばかりである。
・極度の貧困と飢餓撲滅、・普遍的初等教育達成、・ジェンダーの平等と推進と女性の地位向上、・幼児死亡率の低減、・妊産婦の健康改善、・エイズ/マラリアその他疾病蔓延防止。
著者は、こうした課題を第十章「温暖化交渉はなぜ難航するのか…地球規模課題へのリソース配分の難しさ」で短く取り上げている。
<気候変動問題検討の舞台:三つ、UNFCCC、IPCC、 G7>
実は、この気候変動対策国際問題を取り上げる場は、大きく分けて三つある。
第一は、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP:Conference of the Parties)である。気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change)には、世界195カ国+EUが加盟しており、事務局はドイツ・ボンに置かれている。この気候変動枠組条約締約国が参加する会議がCOPである。このCOPは、既に開催20回を数える。日本では1997年京都で開催された。今年の年末には、第21回目の会議がフランス・パリで開かれる。この本は、20回に及ぶ会議の過半に参加し、第一線で主張・論争をしてきた著者が体験に基づいて書きあげたものだ。余人をもってなし得ない貴重な著作である。
目を転じて現実を見ると、気候変動(以下、CC)議論の主舞台:COPの幕が上がる前に、二つの国際的前舞台があることに気付く。
<IPCC報告書作成から始まっている戦争>
第一の前舞台は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)報告作成の場であり、もうひとつは、先進主要国会議(G7:Group of SevenあるいはG8)である。
IPCCは、科学者が集まり温暖化ガス(GHG:Greenhouse Gas)と気候変動の関係に関する科学的分析検討を進める場だと聞かされてきたが、どうもそう単純なものではないようだ。IPCCの報告書主文は科学的立場を明確に踏まえて中立的に書かれていると聞く。しかし、最終段階でまとめられる「政策決定者向け要約(SPM : Summary for Policymakers)」となると、手順として各国政府のチェックがあるだけに、各国の思惑が入り込んで、歪められてしまうようだ。そして評者に言わせれば、それはもう政治的産物であり、COPでの戦いの前哨戦なのだ。・・・本書第十章「IPCCへの政治介入懸念」ならびに、杉山大志著「地球温暖化とのつきあいかた」(ウェッジ刊)
<G7も>
さらに、主要先進国首脳会議(G7, G8)も前哨戦の場である。このことは、著者も本書の中で何回か触れている。ご存知のとおり、サミットの最後には、宣言や共同声明が公表される。CCは、地球規模での問題である上に、G7メンバーには、EU主要加盟国である欧州四カ国が並んでいるわけだから、当然なこととしてアジェンダとして取り上げられ、宣言文にも書き込まれる。
<2009年ラクイラ・サミット宣言に書き込まれた2℃>
その代表事例を2009年COP15コペンハーゲン会議の直前のイタリア、ラクイラ・サミットに見る。このサミットは、前年の2008年に発生したリーマン・ショックによる世界経済大不況下で開かれたので、世界経済問題が第一の議題であった。しかし、年末に、デンマーク・コペンハーゲンでCOP15開催を控えていることもあって、CCは、第二の議題となった。宣言の一部を引用してみよう。
「本年12月のCOP15に向けて、すべての主要排出国が責任ある形で次期枠組みに参加することを確保することの重要性を再確認。工業化以前の水準からの世界全体の平均気温が2度を越えないようにすべきとする広範な科学的見地を認識。」となっている(外務省Website)。ここで見るべきは、太線部分の2℃があたかも科学的に正しい主張のように書き込まれていることと、2℃という言葉の後に続くなんとも慎重な表現である。そして、この2℃は、コペンハーゲンでのCOP15の合意にも書き込まれた。(我々は、世界全体の気温の上昇が摂氏2度より下にとどまるべきであるとの科学的見解を認識し、…」)さらに、その後、次第に、繰り返し強調され、今では、あたかも金科玉条のようにCC対応の大前提となっている。
<今年のサミット宣言では、“世界全体の目標”と記載>
ちなみに、今年6月にドイツのエルマウで開催されたG7サミットの首脳宣言に書かれた表現を見ると「全ての国が、世界の平均気温の上昇を摂氏2度未満に抑えるという世界全体の目標に沿って…」とある。いつの間にか、2℃は、世界全体の目標になっている。2℃は、年末のパリ・COP21でも当然の前提とされよう。“2℃”は、IPCC報告の中に詳細に書き込まれているとはいえ、シナリオの一つだと理解している評者のような者にとっては、あっという間の浸透具合である。
<COP21議長国フランスへの期待も>
本書の構成は、第一章から第九章「COP16と第二約束期間との決別」までで、著者の経験を中心に、具体的国際交渉場面が生き生きと紹介される。第十章「温暖化交渉はなぜ難航するのか」以降は、CC交渉の流れの中での幾つかの課題の紹介と著者の見解が述べられる。第十一章『「環境先進国」EUの苦悩』では、EUの強気の諸目標、EUETSの低迷など欧州が抱える問題、ポーランドを始めとするEU内南北問題などが語られる。ウクライナ紛争などの背景もあるので、生々しい。第十二章から第十四章までで、COP21パリ会議を前にして、課題整理と提案をする。紹介される“資金”、“技術”は、今後の最大課題である。著者は、COP21会議の議長国フランスのプラグマティズムに期待もする。
<エネルギー関係者必読書・COP参加11回の経験者でなくては書けない国際交渉の“真実”>
COPに11回参加した著者は、CCを巡る国際枠組み議論の最前線で健闘してきた。この本はその経験を踏まえて書かれている。それだけに、地球温暖化問題に関心のある人たち、国連という場での外交交渉に関心のある人たち、さらに地球温暖化問題がエネルギーというコインのもう一面でもあるわけで、エネルギー問題に関心のある人たちには、是非読んでもらいたい必読の一冊である。
まず、だいぶ前の出来事だが、CC問題の象徴的一面を良く現す事例に注目したい。
<ゴア副大統領が触れなかった“不都合な真実”>
著書名の中にある“真実”がまず連想させるのは、世界中で出版され評判になったアル・ゴア元米国副大統領の著書「不都合な真実」である。ゴア元副大統領は、この著書とともに、ドキュメンタリー映画を製作し、大ヒットさせている。その結果、一部の新聞に「世界初のカーボン億万長者」などと紹介されるほどに儲けたようだ。2007年には、パチャウリ率いるIPCCとともに、ノーベル平和賞の受賞もしている。
副大統領は、1997年京都で開催されていたCOP3の最終場面で来日。日本政府に、排出削減目標の設定について、巧みに圧力をかけたと伝えられている。日本は、そうした圧力もあって、温暖化ガス(GHG)排出量を1990年比6%削減するという目標値を決めたのだった。(EU:8%、米国:7%)。その場面を、著者は,こう書いている。「三極間(欧米日)の交渉は終盤までもつれ込んだ。最終局面で交渉に乗り込んできた米国のゴア副大統領は、日本に対して数字の上乗せを強く迫ったと言われている。」
実は、この時、副大統領は、自らに不利になる情報には触れていない。1997 年 7 月25日、アメリカ合衆国上院は知る人ぞ知る「バード=ヘーゲル決議」をしているのだ。それも、 95 対 0 の満場一致で。内容は、“途上国が実質的に地球温暖化ガス排出量削減計画に参加しない協定には反対する”というものだ。つまり、クリントン大統領は京都議定書に署名するものの、中国がGHG排出削減について同様の参加をしない限り、米国がこれを批准することなどありえなかったといえるのだ。そんなことなどどこ吹く風の顔をして、ゴア副大統領は、米国7%削減の目標値を飲み、日本にも米欧に次ぐ厳しい目標設定を要求したのだ。米国内での状況など知らん顔をして日本に、削減目標数値の上乗せを迫った。副大統領は“不都合な真実”を都合よく忘れていたのだろう。
<米国:ブッシュ政権の京都議定書離脱>
この状況は、結果的に、米国の京都議定書離脱という結果を招く。2001年、米国ブッシュ政権は、京都議定書から離脱した。
<ハイライト:メキシコ・カンクンでの著者発言「日本は議定書第二約束期間には署名しない」>
次に注目したいのは、2010年メキシコのカンクンで開催されたCOP16 での著者の発言場面だ。本書のハイライトである。
会議初日、有馬は挙手をして、周到に準備したメモにしたがって、発言を始める。京都議定書の第二約束期間については、日本は議定書に署名をしない。つまり、京都議定書のメンバーは辞めるということだ。当時、日本でもテレビで何回となく映し出された場面だから、ご記憶の方も少なくなかろう。この発言は、EUを初めとして、京都議定書加盟国関係者にショックを与えた。様々な働きかけもあったようで、その詳細が紹介される。しかし、それにもかかわらず、日本は大臣にいたるまで関係者一枚岩を通した。議定書の第二約束期間では日本はメンバーではない。議定書が誕生してから、13年目のことであった。
<京都議定書の欠陥>
京都議定書は、先進国グループだけにGHG排出削減を義務付け、途上国には義務付けがない。現実は、エネルギー起源CO2の排出で見ると世界の全排出量の60%強が非OECD諸国によるものとなっている。排出増分で見るとそのほぼ全量が非OECD諸国によってもたらされている。極めて難しいことだが、発展途上国の排出削減がない限り、現実には、地球全体でのGHG排出削減など出来るはずもないのだ。
<そして、2020年以降の国際枠組みについての日本の意見も十分主張>
カンクンでの著者による歴史的なスピーチは、第九章に詳しい。忘れていけないことがある。このスピーチでは、2020年に向けての日本提案(全ての主要排出国の参画、それを実現するための柔軟で現実的な国際枠組み)の考え方もしっかりと語られていることである。日本が主張するとおり、排出削減義務を先進国だけに課し、発展途上国には課さないというこれまでの二分法は、現実的でないばかりか実効性がない。どうしても、米中を始めとする主要排出国の全員参加が必要なのだ。そうでなければ、地球規模でのGHG排出削減はありえないといえる。そして、その実現のためには、国際枠組みは、現実的なものであって柔軟でなければいけないのだ。
<コペンハーゲンCOP15・大失敗ながら、示された将来の方向性>
実は、この方向性は、有馬がスピーチの中で触れているとおり、2009年コペンハーゲンCOP15において芽生えている(第六章、第七章)。このCOP15は、議長国デンマークの失敗によって、国連交渉の崩壊とまで言われ、その合意は、COPでの“採択”ではなく“留意”に終わった。しかし、最終場面で積極参加したオバマ大統領を始めとする首脳たちが自らドラフティングしたわけで、それだけの成果があったといえる。
この第九章までで、これまでのCOPを中心とする交渉の経緯についての語りは一応終わる。ここまでに書かれたことは、国際交渉の記録として、後々まで、評価されるだろう。
<後半に提言が>
第十章「温暖化交渉はなぜ難航するのか」以降は、著者が長い経験の中から得た貴重な解釈・見解、そしてCOP21に向けた日本への提案が書かれる。最終第十四章「温暖化交渉に日本はどう臨むべきか」である。提案は、極めて現実的で、建設的である。また、これも前に触れたが、著者は、COP21議長国フランスに、ブラッセルEUとは違ったプラグマティックな考えを見て、これに期待している。パリ会議は、もう真近い。会議の前までに、関心ある人たちに本書を読んでもらいたい。そして、年末にパリから送られてくるニュースに接してもらいたい。
<21世紀の南北問題>
結局、このCC国際交渉は、EUによる世界覇権の理念によってこれまで動かされてきた。先進国間の削減目標数値設定競争が法的拘束力のある枠組みの下で、“意欲的に、意欲的に”という言葉の鞭によって拍車をかけられてきた。
しかし、20年を超える長期の交渉の間に、発展途上国は成長し、GHG排出面では、かっての先進諸国にとって代わって中心的原因者となった。今では、これらの国々の努力なくして、地球規模でのGHG排出削減の実効は挙げられなくなっている。一方、400ppmに達した大気中CO2濃度は、世界各地で激しい気候変動を引き起こしているようだ。CCへの対応が急がれる。
CC対策としてのGHG排出削減や気候変動による影響緩和措置に必要な資金、技術、人材などの投入資源は、他にも使うべき大きな問題もあるわけで決して十分ではない。こうした状況にあって、投入資源の先進国から途上国への移転実行が急がれ、次第に具現化しつつある。地球環境ファシリティー(GEF: Global Environmental Facility)に加えてコペンハーゲン(COP15)を経てカンクン合意(COP16)により設立決定されたグリーン気候基金(GCF: Green Climate Fund)もできた。京都議定書の下では、クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)や共同実施(JI:Joint Implementation)なども対応する資金源だった。
30年程前に、西ドイツのヴィリー・ブラント首相は、“南北問題”の報告書をまとめた。現在のCC問題は、21世紀の南北問題の一つになってきている。最も重要なのは、ブラント報告にもある出し手と受け手のコミュニケーションであり、共同作業である。
<新たな経済戦争…新たなビジネスチャンス>
しかし、ここにも、経済戦争はある。より具体的で激しいものになると思われる。資金を如何に使うか。何に使うか。その実施主体は何処の誰なのか。選ばれて対象となる技術は、適格か? 国連の、あるいは、国際機関の非効率性は排除されなくてはならない。資金の提供は、一種の選別である。果たして公平な選別はあるのだろうか。出来るのだろうか。こうした点について、著者は、“資金メカニズム”と“技術メカニズム”とのリンクが重要だと書いている。そのとおりだ。こうした動きは、別の見方をすれば、新たなビジネスチャンスでもある。日本のエネルギー効率のよい技術の移転普及に期待したい。少なくとも、パリCOP21では、これまでのような削減目標値の数値争いは止めてほしい。実効あるより具体的な方策が動き出すことの出来る国際枠組みがまとめられることを期待したい。具体的には、著者が最終章:第十四章「温暖化交渉に日本はどう臨むべきか」に熱筆を振るっている。全面的に支持をするところである。
◎ 本稿は、(一社)日本動力協会の「ニュースレター」(隔月刊)に「本に学ぶ」として、書き下ろしたものである。
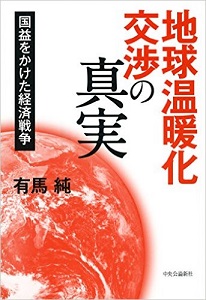
「地球温暖化交渉の真実 – 国益をかけた経済戦争」
著者:有馬 純(出版社: 中央公論新社)
ISBN-10: 4120047695
ISBN-13: 978-4120047695



















