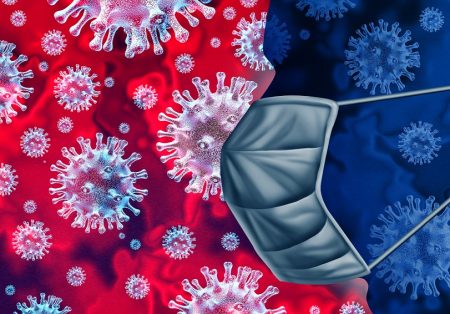“こどもと震災復興” 国際シンポジウム報告4
教育復興
越智 小枝
相馬中央病院 非常勤医師/東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 講師
※【“こどもと震災復興” 国際シンポジウム報告(1)、(2)、(3)】
災害に比べ、その復興をイメージすることは難しい。一時に大勢の人々に同様のインパクトを与える災害とは異なり、復興はその速度も方向性もまちまちだからである。災害復興とは単なるrecovery (回復・復旧)ではなく、development (発展)とsustainability (継続性)を含む、新たなプロセスの創成である。つまり被災地のある一断面、人々の一瞬の笑顔だけを切り取って「復興のイメージ」とすることはできない。復興がメディアで伝わりにくいのはそのためだろう。
今回のシンポジウムは、2日間をかけて、その動的プロセスとしての復興の在り方が語られる機会であった。本稿はその中の教育復興という視点から、以下の3つの講演を紹介する。
1.フォロアーチームの活動(安部雅昭氏、星槎グループ)
2.文化芸術による復興(菊川穣氏、エル・システマジャパン)
3.復興手段としての科学(早野龍五氏、東京大学)
1.フォロアーチームの活動:心的外傷後成長を目指して(阿部雅昭氏)
適応障害・発達障害の子どもの教育やスクールカウンセリングにおいて高い実績を持つ星槎グループは、震災直後より相馬市等と協力し、2011年5月にNPO法人相馬フォロアーチームを設立した注1)。主な業務はスクールカウンセラーの派遣である。フォロアーチームのミッションは大きく3つある。一つは継続的で一貫性を持つ活動。二つ目は個人ではなくチームとして活動すること。そして三つめは、支援に訪れている時だけでなく、24時間緊急時の対応も可能な学校支援体制の確立である。
フォロアーチームの特殊性は、その目標が短期目標としての心的外傷後ストレス障害(Post-traumatic stress disorder: PTSD)の予防にとどまらなかったことだ。中期的には心的外傷後成長(Post traumatic growth: PTG)により、むしろ子供の可能性を広げることも可能だ、と氏は述べる。震災によるストレスは大きいが、その体験があるからこそ成長できた。そう思えるサポートのためには、学校の枠組みの中に入らないスクールカウンセラーという専門家が、教員とは違う立場で、かつ緊急時にも対応することが重要であるという。
フォロアーチームの活動は現在も続いている。その目指すところは、子どもたちと同じ時間を共有することで災害後の紆余曲折を乗り越えることにより、「いろいろあったけれど今が幸せ」と感じられる社会を作ることにある。
2.音楽を通して生きる力を育む(菊川穣氏)
南米のベネズエラで始まったエル・システマ の理念は「社会変革を目指した音楽教育」である。元々年少者の犯罪の高い地域で始まった活動であるが、日本においては芸術活動での子どもの自己実現の場を拡充することを目的に活動を広げている。発展途上国の勤務経験の長い菊川氏は、コミュニティの再生のためにはこのように無償で参加でき、教え合い、学び合いを通じて育む連帯感が大切、と語る。エル・システマジャパン注2)が個々の音楽教室ではなく、オーケストラにこだわる理由もそこにある。
相馬こどもオーケストラは2012年より活動を開始した。それが実現可能であった理由の中に、民謡の里、相馬にはもともと音楽の豊かな伝統と人材がいたことが大きいという。震災という非常時だからこそ、既存の仕組みを最大限に利用しつつ大きな変化をもたらすチャンス。
そのようして始められた活動は、単に子どもたちに音楽の楽しみを伝えることに留まらない。既にドイツへの遠征だけでなく、アンゴラの子供たちを招待した交流コンサートを開くなど、相馬の子供たちは音楽で世界とつながりつつある。また地元の社会においても、こども、保護者、教育委員会のつながり、企業たちとのパートナーシップなどが確立することにより、社会の仕組みそのものも変える可能性を秘めている。
3.福島の放射線防護 ー若い世代に力をー(早野龍五氏)
東京大学で実験物理の教鞭をとる早野氏は、震災直後よりTwitterなどを通じて放射線量や放射能の知識に関する情報を発信し続けた。それだけでなく、現地の医師と協力し、2012年に3万人以上の住民の内部被ばく線量を測定した。(詳細はシンポジウム報告2を参照)
しかし、そのような数値だけでは現地の親御さんの納得は得られなかった。なぜなら親の心配は、確率論ではなく「自分の子供が大丈夫なのか」という具体的な心配だったからだ。その現状を打開するために、氏は放射能測定をコミュニケーションツールとして用いることを思い立った。
その試みの1つが、乳幼児の内部被ばく線量を測定する「Babyscan」である。現在のところBabyscanで測定感度以上のセシウムを検出した被験者はいないが、そのフィードバックを通じて心配する母親と対話するための有効なコミュニケーションツールとなっている。
もう1つは、D-シャトルという、1時間ごとの外部被ばく線量を測定できる機器を用いたコミュニケーションだ。この方法により、個人が行動と線量を関連づけて納得できるという。2014年に立てられたD-シャトル計画は、福島と国内外のそれ以外の地域で暮らす高校生の個人線量を比較したもので、200人以上の学生・教師が参加した。この結果、福島県の居住区域の個人の外部被ばく線量は、その他の地域とほぼ変わりないことが明らかに示された。その結果は高校生自身によって科学論文として発表され、これまでに6万回以上ダウンロードされたメジャー論文となっている注3)。
福島の放射線で必要なことは、知ることだけでなく知ろうとすることが重要、と早野氏は強調する。実際に子供がDシャトル計画にかかわるようになってから、親御さんが県内産の野菜を食べるようになった、という家庭もあるという。
福島の若い人が自分で線量などを測定し結果を伝える取り組みは、単なる目的ではなく、教育・コミュニケーション・復興の手段としての科学の有用性も示唆している。
さいごに
これら一見異なる3つの活動は、実は多くの共通点を持っている。たとえばいずれの活動も、地の利、人の利、時の利を最大限に生かしている点がある。また、知る、得る、というある意味静的な学びではなく、知ろうとする、得ようとする、という動的な学びを得る機会が提供されている。可能性には自由度を持たせつつ、活動自体は専門家による、根底に筋の通ったものである、という点も共通点だろう。
「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」という格言がある。しかしこれらの活動はそれ以上に、「その海に魚がいること」を人々に示す活動であった。災害という攪拌作用により、よそ者と地元の人々が混ざり合って作られた「潮目」が、子どもたちが自主的に育つ豊かな漁場となりつつある。教育復興という活動を通じ、地域全体が、「心的外傷後成長」を遂げようとしているのかもしれない。