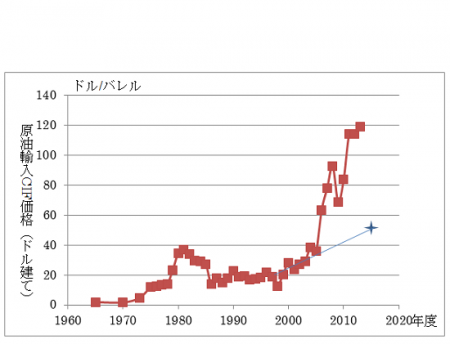温暖化よりも怖いのはエネルギー資源の枯渇だ
久保田 宏
東京工業大学名誉教授
環境史のなかに含まれていない人為起源の温暖化
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第4次評価報告書統合報告書の主著者で、第5次評価報告書第3部会総括執筆責任者でもある杉山大志は、その著「環境史から学ぶ地球温暖化(2012年)」(文献1)のなかで、地球の環境史に学べば、「われわれは、地球温暖化とつきあいながら生きていける」としている。
環境史とは、地球の気候変動の歴史である。杉山(文献1)は、内外の環境史のなかに見られる気候変動、およびそれに伴う環境の変化は、「森林での樹種の自然の変遷、農業での品種の改良、沿岸域での高潮対策など、現在行われている自然災害への適応技術対策への積み増し」で、十分対応できてきたとして、IPCCに反旗を翻しているように見える。ただし、ここで、その影響が心配されている環境史のなかの地球気候の変動は、温暖化、すなわち、地球の気温上昇ではなく、いわゆる寒冷化が主体のようで、さらには、温暖化とは直接関係のない乾燥(旱魃)や人為的な農耕、牧畜に関連した森林破壊、都市化などの影響も含まれている。すなわち、人間の適応能力で解決できないような地球気温の上昇は、日本および世界の環境史のなかに見出されなかったということではなかろうか。
昨年(2013年)秋に発表された第5次報告書(文献2)でIPCCは、人為起源の温暖化効果ガス(CO2が主体で、以下、CO2 と略記)による温暖化(地上気温の上昇)を、気候シミュレーションモデルを用いた予測計算結果の最大値4.8 ℃としている。すなわち、CO2 起源の温暖化は、環境史を学んで杉山が結論した「われわれは付きあいながら生きていける」とした限界値3 ℃(2008年5月に発表された環境省の報告書「地球温暖化「日本への影響」-最新の科学的知見-」による)を大幅に超えている。言い換えると、環境史のなかでの地球規模の気候変化には、いまIPCCが問題にしている産業革命以降の化石燃料の大量消費に伴うCO2起源の温暖化(地球気温の上昇)は含まれていないことになり、環境史に学んでも、温暖化が怖いとは言えないことになる。これが、いまIPCCが、委員の一人である杉山の意見を無視して、CO2起源の温暖化で地球が大変なことになると訴える根拠になっているとみることもできる。
科学的根拠が失われた人為起源のCO2に起因する温暖化
IPCCの第5次報告書(文献2)は、化石燃料の大量消費に伴うCO2排出量が急増した20 世紀後半の環境史から見るとほんの短期間の地球気温上昇の観測結果とCO2排出量の関係が、気候シミュレーションモデルを用いた予測計算結果とほぼ一致したとし、地球温暖化が人為起源のCO2の排出増加によりもたらされたとする仮説に科学的な根拠があるとしている。
一方、いわゆる懐疑論者の一人の赤祖父(文献3)は、環境史のデータに基づいて、このIPCCの仮説を否定している。すなわち、地球上の気温は数万年もの大きな周期で氷河期と間氷河期を繰り返して変動している。1000年ほど前の地球は今より高温であったと推定される。IPCCがCO2起源の温暖化としている最近の20世紀後末の気温上昇は、14 ~ 18世紀の小氷河期と呼ばれる寒冷期間が終わって1800年頃から始まった気温の回復期間に含まれる。人為的なCO2排出に起因する20世紀後半の温度の急上昇も1800 年からの自然の温度上昇の一部と見るべきとしている。
杉山(文献1)は、同じ環境史を論じる立場から、この赤祖父の主張に対して、「意見を異にする部分もあるものの本書を著わす上で多くのヒントをいただいた」としながらも、結局は「懐疑論騒動」の一つとして退けてしまっている。IPCCの主要なメンバーの一人として、CO2起源の温暖化を否定する主張を支持するわけにはいかなかったからであろう。
しかし、この赤祖父の懐疑論を裏付ける科学的な研究成果が、最近、国内であいついで発表されたので、以下、簡単に紹介しておく。
東大海洋研の阿部ら(文献4)は、大気温度の指標となる氷河中の酸素同位体の元素分析値に見られる約10万年の周期で繰り返される古気象学における大きな気候変動が、地球の自転軸の傾き、公転軌道の離心率などの変化に伴うによる日射強度の変動により起こる(ミランコビッチ理論)ことを前提とした上で、大気・氷床・地殻間の熱・物資移動のフィードバック効果(変動要因に対しシステムの応答が加速されたり遅延したりする効果)を考慮した独自の氷床-気候モデル(に基づく微分方程式)を過去40万年間積分することで、再現できることを明らかにした。同時に、古気象学のデータで、大気中のCO2濃度の上昇が気温上昇に先行するように見えて、長周期気候変動が日射強度の影響だとするミランコビッチ理論が否定されるようにみえる現象についても、彼らの氷床気候モデルを用いた解析結果から、大気中のCO2濃度の変動が気温変動に伴って起こるので、CO2濃度の増加が地球温度の上昇を引き起こす主体ではないことが示唆されたとしている。
また、IPCCの報告書に記載されている数十年規模の短周期の地球気温の変化(文献5 参照)について、海洋開発研究機構の中村(文献6)は、これは、メキシコ湾流による熱供給と北極圏の氷床の溶解によって起こっているグリーンランド海を起源とする地球規模の海洋水の大循環が、数十年規模で消長を繰り返す大西洋数十年規模変動(Atlantic Multi-decade Oscillation AMO)によるものであるとして、1980年から35 年間継続する地球地上気温の上昇は2015年で終了し、以降、寒冷期に入ると主張している。このグリーンランド海の海面水温と塩類濃度の変化に起因する海洋循環流の変動に伴う北半球の気温の変化も、海水と大気の熱移動を考慮したポジテイブフィードバック効果をとりいれた気候シミュレーションモデルを用いることによって初めて正確に予測することが可能になったとしている。
この最近の両研究の成果は、人為的起源によるCO2の排出が地球温暖化の原因であるとする仮説を科学的な根拠に基づいて否定するものであるが、IPCCの第5次評価報告書(文献2)の中では一切、触れられていない。