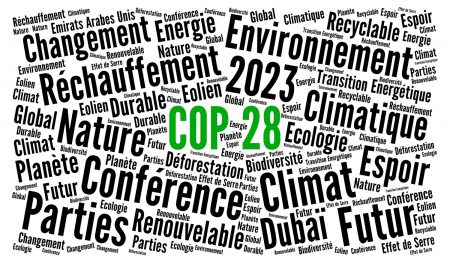世界のエネルギー転換論はイデオロギーからプラグマティズムへ
有馬 純
国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授
ここ数年、エネルギー転換に関する国際的な議論は一時の環境至上主義的なものから、より現実的なものにシフトしてきた。これは明らかにウクライナ戦争、ハマス・イスラエル戦争によって国際エネルギー市場の不安定性が高まり、先進国、途上国を問わず、エネルギー安全保障及びエネルギー価格の手頃さ(affordability)が一丁目一番地になったことと密接に関係している。
我が国の第7次エネルギー基本計画も「エネルギー安定供給を第一として経済効率性と環境の適合を図る」との考えのもとに、第4次エネルギー基本計画以降、日本のエネルギー政策を呪縛してきた「原子力依存度を可能な限り低減」という文言を削除し、「再エネか原⼦⼒かといった⼆項対⽴的な議論ではなく、脱炭素電源として両者を最⼤限活⽤する」とのプラグマティックな方向性を打ち出した。
2021年以来、2050年カーボンニュートラルからバックキャストしたNZEシナリオを通じて世界のエネルギー転換をめぐる議論に多大な影響(あえて悪影響と言いたい)をもたらしてきた国際エネルギー機関(IEA)の2025年の世界エネルギー展望(1は不安定な地政学情勢の中で、従来の燃料供給のリスク(石油・ガス)だけでなく、重要鉱物のサプライチェーンや電力系統・サイバーリスクにも焦点を当てるものとなった。クリーンエネルギー転換のみならず、サプライチェーンの強靭性、安定性の重要性がハイライトされた。また数年前に廃止された現行政策シナリオ(CPS: Current Policies Scenario)が復活し、化石燃料(石油・天然ガス)の需要が中期まで成長し続け、石炭も2030年前後まではかなり使われる可能性が示唆されている。その背景にはデジタル/データセンター等により電力需要の増大が見込まれる中で、再エネだけでは対応困難であることもある。カーボンニュートラル推進機関と化していたIEAが本来の設立目的であるエネルギー安全保障に軸足を移したことはエネルギー転換に関する国際的な議論をより現実的なものにするだろう。
筆者はCOPに来る10日ほど前、アブダビ国際石油展示会議(ADIPEC)に参加した。ADIPECでオープニングリマークスをしたのはCOP28の議長であったアル・ジャーベルADNOC(アブダビ国営石油会社)総裁であり、基調講演をしたのは米国のダグ・バーガム内務長官兼国家エネルギードミナンス協議会議長である。
ジャーベル総裁によるオープニングリマークス(2の主要なポイントは以下のとおりである。
- •
- 再生可能エネルギーなどの新たなエネルギー源と並行して、既存のエネルギー源を置き換えるのではなく強化するバランスの取れた現実的なアプローチを提唱。
- •
- 将来の需要を満たすためには、送電網、データセンター、あらゆるエネルギー供給源に対し、年間4兆ドルを超える巨額の資本投資が不可欠であることを指摘。
- •
- エネルギー源の最適化、効率向上、そしてエネルギー部門を「世界で最もAIを活用したエネルギー企業」へと変革する上で、AIとデジタル技術の役割を強調。
- •
- 既存インフラは不十分であり、2040年までに少なくとも600万キロの新規送電線を含む大幅なアップグレードが必要。
- •
- 投資を加速・保護し、資本を適切な分野へ導くためには現実的な政策と規制が必要。
- •
- 人材・技術・AIへの投資が不可欠。
注目されるのは化石燃料フェーズアウトが大きな争点になったCOP28の議長であったジャーベル総裁の口から、1.5℃、2050年カーボンニュートラル、化石燃料からの移行(transition away from fossil fuel)はおろか、パリ協定にも言及がなかったことである。
ダグ・バーガム長官のスピーチ(3は
- •
- 知識=力だった時代を経て、今では“1キロワットの電力が直接インテリジェンスに変換できる”時代になった。
- •
- 従来の“データセンター”という呼び方をやめる。これらは“知能を製造する工場”だ。AI・データセンターの爆発的成長が、エネルギー政策・資本投資・地政学において新たな軸になる。
- •
- 「エネルギー転換(energy transition)ではなく、「エネルギー追加(energy addition)」が重要だ。石油・ガス・電力・再生可能を“どれかに取って代わる”ではなく、“すべてを動員して増やす”戦略が必要。
- •
- 世界が必要としているのはより多くのエネルギーであり、選挙を経ていないイデオロギーに凝り固まった官僚ではない(The world needs more energy, not unelected, ideological bureaucrats)
S&Pグローバルのダニエル・ヤーギン副会長もAIによる電力需要急増を背景に「エネルギー転換」から「エネルギー追加」へのマインドセットの転換、イデオロギーからプラグマティズムへの転換の重要性を強調した。その趣旨は以下のとおりである。
- •
- 技術、経済的優位性が過去のエネルギー転換を牽引してきた。現在は公共政策が牽引。これまでのエネルギー転換は100年以上の時間をかけて展開され、既存技術を完全に置き換えるものではなかったが、今日の転換は四半世紀余りで既存技術を完全に置き換えることを企図している。
- •
- 想定される規模は大きく、政策立案にあたり、マクロ経済分析に十分注意すべきである。転換を急すぎると、1970年代に類似した供給ショックをもたらすとの分析もある。
- •
- エネルギー転換には4つの大きな課題がある。
- ▶
- ウクライナ戦争により、ほとんどの国にとってエネルギー安全保障が再び最優先課題になっている。
- ▶
- 100兆ドル規模の世界経済は、80%以上を炭化水素に依存している。現代文明に不可欠なセメント、鉄鋼、プラスチック、アンモニア(肥料)は既存のエネルギーシステムに大きく依存している。
- ▶
- グローバルノースでは、気候変動が最重要課題だが、グローバルサウスでは、気候変動よりも、経済成長の促進、貧困の削減、健康増進など、他の重要な優先課題がある。途上国の多くにとって「エネルギー転換」とは、薪や廃棄物からLNGへの移行。欧州議会の化石燃料インフラ非難に対し、「新植民地主義」との反発がある。
- ▶
- エネルギー転換に伴い、銅、リチウム、コバルト等の重要鉱物の需要が急増している。新規鉱山開発には16~25年かかり、許認可要件は複雑化。政府が採掘を敵視する資源国もある。
- •
- エネルギー転換の方向性は明確だが、それが内包する課題を認識しなければならない。移行目標を達成するためには対処すべき複雑な問題をより深く、より現実的に理解することが不可欠である。
これらはいずれも各国のエネルギー政策を席捲してきた脱炭素への狂熱が落ち着きを取り戻しつつあることを示している。筆者は現在、COP30(ベレン)に来ているが、こちらでは英国、ドイツなど80か国以上が化石燃料フェーズアウトに向けたグローバルロードマップ策定を求めるなど、COP28に続いて再び化石燃料フェーズアウトが政治的争点になりそうだ。COPの中の世界と外の世界の乖離はなかなか解消されそうにない。
脚注