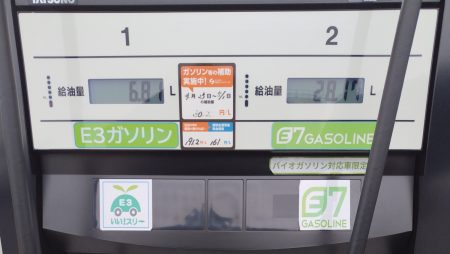気候変動の報道で羊のごとく、おとなしい不気味な言論空間が出現!
小島 正美
科学ジャーナリスト/メディアチェック集団「食品安全情報ネットワーク」共同代表
気候変動をめぐる言論空間をごく簡単に描写すると、次のような言葉に集約される。
「一個の怪物がヨーロッパを徘徊している。すなわち、「気候危機」という怪物である。古いヨーロッパのあらゆる権力は、この怪物を退治するために、神聖同盟を結んでいる。・・」
若かりし頃、学生運動に身を投じたオールド左翼の人間なら、この文章を読んで、すぐにマルクスとエンゲルスが著した共産党宣言(1848年)の冒頭だと分かるだろう。ここでは「共産主義」を「気候危機」に置き換えているが、ヨーロッパという言葉を「全世界」にと言い換えても、意味は通じるだろう。神聖同盟は、パリ協定や国連気候変動枠組条約(最近のCOP26など)に相当する。
この怪物はいまや全世界、つまり政府、企業、環境保護団体、ハリウッドのセレブ、自治体、学校、科学者集団、そしてメディアと、あらゆるところを侵食し、「気候正義」という革命的呪文を唱えながら俳諧している。
羊のごとく唯々諾々の朝日新聞
朝日新聞は今年9月19日付新聞で気候問題の専門家である江守正多・東京大学教授を登場させた。読んでみるとまるまる江守氏の言い分が載っている。江守氏は、こと気候変動問題では政府側に立つ学者だ。
朝日新聞といえば、原子力や残留農薬、ゲノム編集問題などの問題では、どちらかと言えば、政府の政策に批判的な意見を述べる学者が登場する。つまり、政府側に立つ学者の意見をそのまま載せるケースは少ない。
ところが、気候変動問題になると、江守氏のような学者や企業人、環境保護団体の登場が目立つ。しかもその記事内容はほとんど批判的ではない。この記事でもインタビューする側の記者は「温暖化は本当に人間のせいなのでしょうか」と問うが、江守氏は「結論から言うと、人間活動による温暖化には疑う余地はありません」ときっぱりと答える。他のテーマなら、おそらく記者は「こういう見方もあるが、どうか」と反論する形でインタビューを進めるはずだが、そういう鋭い問いかけを放棄している。
別の質問で江守氏は「人間の活動で最も影響が大きいのが二酸化炭素(CO2)です」と答えているが、これもそれでおしまいである。
悪く言えば、朝日新聞は政府側に立つ学者の意見を唯々諾々と載せている印象を受ける。これが原子力の新設や再稼働の問題なら、おそらく記者は鋭い質問を浴びるだろう。なぜ、気候変動や温暖化問題だと、その鋭い批判精神が鈍ってしまうのだろうか。
朝日新聞は、政府に批判的な学者の意見を載せるのが真骨頂だと思っていたが、こと気候変動問題では人為的な二酸化炭素説に懐疑的な学者、つまり政府に批判的な学者を大きく取り上げたインタビュー記事(今回の江守氏のような例)を見たことがない。
安倍元首相へは批判精神旺盛な朝日新聞
一方、朝日新聞は、安倍元総理が凶弾に倒れたあとの7月15日、朝日川柳に「還らない命 幸せ無限大」という読者の投稿を載せた。一国の元首相が殺されて、幸せ一杯という人がいてもおかしくないが、通常の殺人事件でも、他人が殺されて喜ぶ人の声を記事に載せることはまずないだろう。
だとすれば、この川柳を載せることは世間からの批判を覚悟しての掲載だと考えられる。ある意味で勇気のあるあっぱれな行為である。そして、9月23日には、犯人の山上徹也容疑者をモデルにした映画「REVOLUTION+1」を記事で紹介した。監督は元赤軍派メンバーの足立正生氏(83)だ。政治家の細野豪志氏はツイッターで「この時期に元テロリストが製作した映画を告知するマスメディアの見識を疑う」と書いているが、逆から見ると、この記事掲載は大変勇気のいる記者魂あふれる報道行為である。
こうした川柳や記事の掲載自体は言論の自由として肯定できる。不思議なのは、これだけの勇気と批判精神がありながら、なぜ、気候変動問題だと批判の刃が鈍ってしまうかという点である。このことは毎日新聞や東京新聞にもあてはまる。
どの社説も似たり寄ったりの内容
社説を読めば、それは明白である。最近の主要新聞社のどの社説を読んでも、気候変動問題の内容は似たり寄ったりだ。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書を「世界の科学的知見が結集された報告書」(朝日新聞2021年8月12日社説)とみなし、脱炭素の方向については「すでに多くの先進国で、政府も企業も温暖化対策を前提に、政策やビジネスを組み立てており、遅れれば国際競争力にも影響を及ぼす。日本はさらに高い目標を目指すことで世界をリードしたい」(同社説)と述べ、政府と企業が足並みをそろえて、世界をリードすべきだと論じる。
読売新聞も「地球規模の温暖化問題に国境はない。世界が一致団結して取り組める安定した環境が望まれる。日本では地方自治体や企業とも協力し、温暖化に強い社会を目指すことが重要だ」(2022年3月2日社説)と熱く述べる。骨子は朝日新聞と大差はない。
もちろん、原子力発電を認めるかどうかでは、読売と産経、朝日と毎日と東京新聞では従来通り、差は大きい。あとで述べるように産経新聞だけはややスタンスが異なるものの、CO2を主原因とする人為的温暖化説に与する点で大きな差はない。
どのメディアも脱炭素に向けて、政府と企業、地方自治体が協力しようと呼びかけ、さらに政府の脱炭素を応援する論調である。メディアが「政府と企業が協力しよう」と呼びかける姿をあまり見かけないだけに、異例の論調にみえる。
その一方、福島原発事故によってたまり続けるタンクの処理水の放出問題の論調はどうか。本来なら、この処理水の放出こそ、風評が生じないよう「政府も企業も自治体も協力して対処しよう」と呼び掛ける必要があるはずなのに、まるで他人事のように風評を煽るような識者(少数派か異端派)や市民の声を載せる。協力を呼び掛ける相手を間違えているのではないかと思うほどだ。
孤軍奮闘する産経新聞の長辻記者
こうした異常な言論空間であえて異議を唱えているのは、私の見るところ、産経新聞でコラム「ソロモンの頭巾」を執筆する論説委員の長辻象平氏くらいである。長辻氏は「(人為的温暖化論に)反論する研究者には異端のレッテルが貼られ、研究費も枯渇してしまう。論文も受理されにくく、若手の場合は、ポストも遠ざかる。結果として科学界はCO2温暖化論一色になる。『ルイセンコ効果』そのものだろう」(2021年3月31日付)と書く。
「ルイセンコ」といえば、かつて旧ソ連では生物学者のルイセンコ氏以外の説が全く認められない時代があった。それを今の状況に重ねて表現したものだが、まさにそれに近いと言えよう。産経新聞の「正論」には懐疑派を代表する杉山大志氏(エネルギー環境問題の専門家でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹)が登場するため、産経新聞だけはやや異質とみてもよいだろう。
4人の署名者は取材する価値あり
では、気候変動問題で取り上げるべき価値のある懐疑派の学者がいないのかというと、そんなことは全くない。
科学者の世界では、ノーベル賞受賞者をはじめとする1100人以上の科学者らが「気候危機は存在しない」とする「世界気候宣言(WCD)」に署名する活動が始まっている。米国や英国など42カ国の科学者らが参加し、「気候モデルには多くの欠点がある。CO2など温暖化効果ガスの影響を誇張しており、CO2の有益な点は無視されている」などと主張している。
『ノーベル物理学賞の受賞者を筆頭に1100人以上の科学者らが「気候危機は存在しない」とする宣言に署名 無茶な「脱炭素」政策は転換すべき』
日本からは、中村元隆氏(NASAなどの研究所にいた大気・海洋・気候科学の専門家)、室中善博氏(エネルギーや環境のコンサルタント)、兵頭政幸氏(古地磁気などの専門家で神戸大学内海域環境教育研究センター教授)、田中博氏(大気科学を専門とする筑波大学計算科学研究センター教授)の4人の名がみえる。
この4人は、れっきとした学者でありながら、気候科学の世界では既成科学を批判するいわば少数派(もしくは異端派)である。原子力やゲノム編集、ワクチンの世界に置き換えてみれば、朝日、毎日、東京新聞が好みそうな学者のはずである。普通の記者なら、「なぜ、4人は署名したのか、気候科学のどこが問題だと考えているのか」など、興味をもって取材するはずだし、その取材価値に匹敵する学者ばかりである。それが読者のニーズに応える報道機関の使命でもある。しかし、この4人に関して、江守氏のようなインタビュー記事を見たことはない。
メディアが政府や企業、環境団体と横一線に並ぶ異常現象
結論に入ろう。こと気候変動問題になると既成の科学界に批判の矢を向ける学者が無視されているのだ。前回の記事で「ねじれ現象」と呼んだのは、これまでに見たことのないこの異様な光景のことである。
気候変動問題に関する言論空間の構図は、政府、企業(大手銀行や大手流通事業者、原子力関連企業も含む)、自治体、学者、政治家、全国の生協、環境保護団体、そしてメディアが横一線に並び、手をつなぐ光景である。その反対側にいるのは、メディアから軽視された一部の科学者集団と産経新聞の一部記者だけである。この構図では少数派がメディアの力を借りて、政府に対抗する拮抗関係は出現しない。勢力の数からいうと、象とアリである。
象を倒そうとするのが記者魂だと思っていたが、どうやら、ほとんどの記者はいまだ不確かな気候科学を素直に受け入れている。まるでファシズムの世界だ。不気味としか言いようがない。
この構図でさらに気になるのは、従来、政府を批判してきた環境保護団体が政府の側にいて、論調をともにしていることだ。次回で、そのおそるべき帰結を、有機農業を推進する農水省の「みどり食料システム戦略」を中心に論じてみたい。