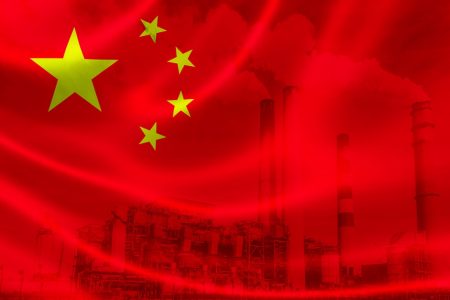日本の「グリーン成長」を可能にする条件は?(後編)
-アジアの市場を足掛かりに火力の脱炭素実現でゲームチェンジを-
堀井 伸浩
九州大学大学院経済学研究院 准教授
前編から始まる3編は、我が国のグリーン成長を現実的な実行可能性という点から考察し、その上で我が国のカーボンニュートラルに向けた戦略を批判的に検討しようとするものである。とりわけ2030年目標に関しては再エネ一本鎗となっている我が国のカーボンニュートラル戦略について、再エネの導入拡大でグリーン成長が可能かどうか、前編と中編ではそれぞれ風力と太陽光について検討を行った。
筆者が中国のエネルギー産業の分析を専門としていることより、いずれも中国との比較の視座で考察を進めた。しかしそれには積極的な理由もある。日本の国内需要のみで十分なグリーン成長を達成できるわけもなく、当然海外、特にアジアに向けた展開が必要となるが、そこに立ちはだかるライバルは中国企業となるはずであり、その中国企業と比べて競争力があるのかないのかを検証したわけである。
再エネ一本鎗でグリーン成長実現は困難
前編では政府のグリーン成長戦略の筆頭に挙げられていた洋上風力について考察した。日本政府の目標は2030年に10GW、2040年に30-45GWの洋上風力を導入し、2030-35年にkWh 当たり8-9円までコストダウンするというものであるが、中国では2021年9月時点で13.2GW、すなわち日本政府の2030年目標を大幅に超える洋上風力が既に送電網に接続済となっている。
そして驚くべきことに、2021年は17GW(!)の新規発電設備を導入し、送電網未接続の設備も含めると累計導入量は26GWに達したとされる。1年間で17GWという莫大な導入量は2021年の世界全体の導入量の8割以上を占めたと考えられる。この驚異的な急拡大の背景には洋上風力の買取優遇価格の見直しが予定されていたために駆け込み需要があったとされ、今後多少減速すると考えられる。しかし日本の2040年目標の下限30GWに早ければ2022年にも到達する可能性があり、上限にも2030年までに到達する可能性が高いということだ。
また前編執筆時点では中国の風力発電業界として、2025年に同6.3円までのコストダウンを目指していることを指摘したが、この導入急拡大を見るとコストダウンの目標は更に深掘りされている可能性も高い。こうした点を考えると、日本の2030-35年のコストダウン目標では中国企業に対抗して日本の洋上風力のアジア展開など一縷の望みもないと言わざるを得ない注1)。
中編ではかつて世界生産ランキングで多くの日本企業が上位を独占していた太陽電池について、2010年代以降は中国企業が台頭し、現在では中国企業が世界の太陽電池生産の7割を占めるに至った経緯について分析を行った。中国企業が日本企業を凌駕するようになったのは、一旦トップシェアを握った有力企業でさえも、数年先には経営危機に追い込まれるような激しい企業間の競争で国際競争力を鍛え上げたところにある。この点を踏まえると、注1に書いた洋上風力の入札評価基準見直しを画策して蠢動する業界の様子などを見ると、我が国の再エネ業界のぬるま湯体質を改革することの必要性を痛感せざるを得ない。
中国の太陽電池が世界で多く選ばれた理由はそのコスト競争力にある。2000年代はドイツなどEU諸国の固定価格買取制度(FIT)の潮流に乗り、中国企業はEU向けの大量輸出で産業基盤を作り上げた。しかし中国製太陽電池がアンチダンピング・補助金の対象とされEU向け輸出が2012年以降激減したため、中国政府はFITを用いて国内市場への導入に切り替えた。重要なのはその際、中国はFIT価格を世界のLCOE(均等化発電原価)よりも65%低い水準に設定した点である。その結果、2010年代は中国企業のコスト面での国際競争力が急速に向上し、世界の上位10社に占める中国企業のシェアで見ると2011年は58.7%であったが、2019年には90.4%にまで上昇した。ちなみに同時期にFITを導入した日本のFIT価格は中国の6.7倍の水準であった。
そして中国の太陽電池の競争優位はコスト面だけに止まらないことも注目すべき点である。中国は太陽電池の製造設備についても国産化を進め、国内で原料となるシリコン加工から製造設備、そして太陽電池(セル)、太陽光パネル(モジュール)まで一気通貫で完結したバリューチェーンを構築することに成功している。目下、商用段階で最も高い変換効率のPERC電池の商業化を進めたのも中国企業であり、中国は技術開発の面でも先導するようになっている。2017年と2019年を比較すると、世界の上位10社の市場集中度が38.6%から52.4%へとわずか2年で13.8ポイントも急伸している。このことが示すのは、太陽電池では上位企業(先に述べた通り、ほとんどが中国企業)による寡占化が進みつつあり、今更日本企業が割って入ることができる余地などない、という厳しい現実である。
以上の洋上風力や太陽光の現状を踏まえると、我が国が風力や太陽光などの再エネ導入を大幅に拡大しても導入される設備は海外製であるため、設置や運転などで多少の雇用と付加価値は生むものの海外で展開できず、経済効果は限定的なものに止まるだろう。日本を含むアジアの再エネ拡大でグリーン成長するのは中国企業になりそうだ。最悪のシナリオは、グリーン成長にこだわるあまり、割高な国産設備の導入を(市場では選ばれないので)政策によって義務付けるケースである。中国の経験が示しているように、競争のない保護によって競争力のある企業が育つことはない。日本国内でしか導入されず、規模の経済性を欠いた国産化設備の導入はエネルギーコストを増大させ、我が国経済の足を引っ張ることとなる。杞憂とも言えない。現実に、洋上風力の導入設備に関してその部品の国内調達率を2040年までに60%以上とするという目標が掲げられている。部品メーカーが国際競争力のある水準までコストを低下させることができなければ割高な設備が日本国内に導入されていくことになる。
日本の強みは火力発電技術にこそ
気候変動対策にはコストがかかる。コスト負担を軽減するために、中国が太陽光をほぼ独占することで世界の再エネ導入で成長の果実を得るように、我が国も気候変動対策が進むことで経済的にメリットのある仕組みを作り出さなければならない。
再エネは上で述べた通り、もはや日本企業が割って入る余地がほとんどない。しかし火力発電の脱炭素(当面は低炭素)に向けた技術に関しては依然として、世界に比して我が国に優位性が残っている。とりわけ石炭火力関連のCO2削減技術、具体的にはIGCC(石炭ガス化複合発電)やCCS(炭素回収・貯留)は日本の技術が世界トップレベルにあり、例えば世界で導入されているCCS設備の7割は三菱重工製とされる。他にも石炭火力でのバイオマス、あるいはアンモニアや水素の混焼・専焼なども技術的には課題をほぼ克服しており、残る問題はコストをどう下げるかという点のみという。
「世界の脱炭素に向けた潮流の中で今更火力、しかも石炭火力?」と考える向きが多いだろうが、現実の世界は脱炭素へと一直線に進んでいくように思えない。2020年時点において世界で使われるエネルギーの83%は化石燃料の燃焼により供給され、なかでも電力の64%は化石燃料で発電されている。その中で石炭火力も世界全体の発電量の35%を支え、途上国に限れば発電量の46%が石炭火力によって供給されている事実がある。
とりわけ注目に値するのがアジアにおける石炭火力の重要性である。全世界の石炭火力発電量のうちアジア太平洋地域のシェアは78%を占め、巨大な石炭消費国である中国を除いたとしても55%と高い水準である。同地域では電力需要の57%が石炭火力によって担われており、石炭火力はアジアの旺盛な経済成長に伴う電力需要を支えることに貢献しているのだ。
このように石炭火力の集積地であり、石炭火力が電力供給に重要な役割を果たしているアジア地域の中に我が国は存在していることを改めて認識するべきである。アジアの国々が今後も経済発展を目指していく上で、引き続き増加していくエネルギー需要を再エネ一本鎗で賄うことは現実的に考えて難しいだろう。経済発展には安価で安定供給される電力が必要であるが、再エネはいずれの条件も満たさない注2)。途上国にとっての石炭火力の魅力は失われておらず、アジアの国々にきちんと環境に配慮した高効率な我が国の石炭火力技術を供与していくことは本来望まれるべきものである。しかし日本政府は日本の石炭火力の海外輸出を今後停止する旨、2021年6月のG7サミットにおいてコミットしている。
石炭を槍玉にあげて排斥する動きは欧州の価値観に過ぎない、アジアにはアジアの事情がある、と堂々と主張すべきところである。COP26の終盤、石炭を「段階的に撤廃」しようとする会議全体の流れにインドが異議を唱え、中国などの賛同と支援もあり、「段階的に低減」という語句に修正させた件を想起されたい。国連のSDGs(持続可能な開発目標)においても目標7として、「すべての人々に安価かつ信頼できる持続可能な現代エネルギーへのアクセスを確保する」目標が設定されている。そしてその具体的手段として、「先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術」をクリーンエネルギーと認め、「国際協力を通じて途上国がその技術へのアクセスと投資を受ける支援を行う」ことが先進国に求めているのだ。SOx、NOx、PMなどの従来型汚染物質をほとんど排出しない我が国の石炭火力をアジアに展開していくことはむしろSDGsの理念に合致した取り組みなのだ。
それでもCO2を増やすのはけしからんというのは、世界のCO2排出量の44.5%が中国と米国の2カ国によって排出されている事実をどう考えるのだろうか?アジアの途上国が経済発展に必要なエネルギーを石炭火力で賄うことで増えるCO2の量は米中両国による排出量と比べれば微々たるものに過ぎない。石炭火力によって安価で安定的な電力を供給することで、産業化を進めて経済成長を実現することこそアジアの人々の幸福につながるだろう。その幸福を犠牲にせよという前に、まず米中に求めるべきことがあるだろう。
そして我が国にとっても、欧米や中国に圧倒的に差をつけられた再エネで巻き返そうとするよりも、石炭火力の脱炭素化技術を磨く方がずっと勝算の高いグリーン成長につながる戦略である。実際、日本政府のグリーン成長戦略にも火力発電における水素・アンモニア混焼・専焼は重点分野として掲げられている。これまでのところ、再エネ、なかでも洋上風力にばかり脚光が当たってきたが、今後は化石燃料の燃焼技術の脱炭素化にも注力すべきと考える。その意味で、今年1月にインドネシアの石炭火力発電所においてアンモニア混焼導入の官民連携プロジェクトを進める覚書を交わしたことは、今後の進展に期待が高まる。
中国における石炭火力の脱炭素化をバネにゲームチェンジを
そして真に世界の気候変動対策に貢献しようとするなら、やはり中国の石炭火力の脱炭素化への協力が効果的だろう。何と言っても中国のCO2排出量は世界の31%を占め、そのうち半分強が(熱供給プラントを含む)石炭火力から排出されている。すなわち中国の石炭火力の脱炭素化は世界のCO2排出量の15%程度を対象とし、それは日本の排出量の5倍の規模となるものだからだ。
一応付言しておくと、現在の中国の石炭火力の技術レベルは我が国で導入されている最新鋭の発電所と比較して遜色のない高い水準である。近年導入されているシステムはほとんどがUSC(超超臨界発電)であり、発電効率は高い。従来型大気汚染への対応はPMを始め、基本的に完備している。技術的には遜色がないにもかかわらず、価格は日本の設備と比べて3割から4割安い。日中がアジア展開で競った場合、再エネ同様、我が国の石炭火力設備は太刀打ちできないだろう。
しかし石炭火力の脱炭素に向けた先端技術となると、我が国は依然として技術優位を維持している。IGCCもCCSも中国ではパイロットプロジェクト段階にはあるが、筆者の現地調査での見聞では、商業化への次のステップへの投資は全くなされていない。再エネの圧倒的な国際競争力と習近平政権が石炭を冷遇する姿勢を取ってきたことが影響していると見る。
もっとも2020年9月に習近平国家主席が2060年カーボンニュートラル実現の目標を表明したとは言え、中国は2030年までは経済発展優先で石炭火力を維持する方針である。その先については2020年の時点では、太陽光と風力、そして原子力を大幅に拡大し、急激な脱石炭を推進していくシナリオが示されていた。しかし現在も果たしてそうしたシナリオが想定されているかどうかは留保が必要である。と言うのも、昨年秋の全国的な停電を受けて中国政府はエネルギーの安定供給の重要性を再認識して軌道修正している節があるからだ。特に、習近平国家主席が今年1月の政治局会議における講話で、「CO2削減は同時に、エネルギーや食料の安定供給、産業チェーンの安全保障も確保して、人々の日常生活を確保しなければならない」と述べ、短期的な、政治主導の急進的な気候変動対策を戒めたことは注目すべきである。昨年秋の停電の一因に風力の急激な出力低下があり、安定供給に果たす石炭火力の役割が再評価されているように見える。
日本政府は最先端の石炭火力の脱炭素技術に関しては、中国との協力に消極姿勢で及び腰であると聞く。虎の子の技術を吸収された挙句、アジア展開で対峙する強力なライバルになる懸念によるものと思われる。実際、石炭火力について言えば中国のUSC発電技術の成熟化に我が国企業が貢献し、その後インドネシアなどアジア展開で煮え湯を飲まされた事実があり、石炭火力以外にもそうした事例は枚挙にいとまがない。警戒するのには確かに理由がある。
しかし石炭火力の成長見通しが芳しくない我が国の国内市場だけでは技術開発の投資回収に十分なリターンを期待できそうもない。また中国が石炭火力の脱炭素に舵を切れば、ほんの数年で我が国の技術にキャッチアップしてくる可能性が高いとこれまでの事例から当然予想される。インドネシアにおける石炭火力のアンモニア混焼導入のプロジェクトは我が国の石炭火力輸出の停止という壁を打ち破る重要な契機であるが、やはり中国の追い上げが始まった際に、優位性を保ち、更に広げていくために短期間に巨額の投資を確保するには心許ない。中国市場では薄利であってもスピード勝負で短期間に市場浸透を目指すことが必要なタフな市場環境であるが、市場が巨大なのでその分のリターンがある。
米中対立に加え、ロシアのウクライナ侵攻でも中露派生した国際的な中国への警戒感の高まりの中で、日本が中国と石炭に関する協力を推し進めることは相当に難しい状況であることは理解している。しかし我が国がグリーン成長を実現可能なのはやはり優位性を維持している火力分野をおいて他にないだろうし、そのためには圧倒的な市場規模を持つ中国で投資回収の好循環を構築することが最適の道だ。たとえ中国企業に技術を吸収されキャッチアップされたとしてもそれまでに十分なリターンを得るための仕組みづくりに知恵を絞ることを選ぶべきではないか。中国市場、そしてアジア市場を足掛かりに安価で安定供給可能な石炭火力の脱炭素化に成功すれば、再エネ一本鎗とは違う別の選択肢を世界に提示するゲームチェンジャーになれる。
- 注1)
- もっとも日本国内にも明るい兆しはある。2021年末に行われた秋田県と千葉県の3海域における洋上風力プロジェクトの入札で三菱商事を中心とするコンソーシアムが他の参加者の平均価格の半分程度という圧倒的な低価格で応札した一件である。これを契機に我が国の洋上風力がコスト競争力を磨くべく切磋琢磨するようになることが期待される。しかし最近の動向を見ると、入札価格よりも事業実施可能性の評価割合を大きくせよなどと入札評価制度の変更を画策する動き、あるいは経産大臣が事業開始時期を前倒しすることを入札評価に組み込むことを表明するなど(数年早く導入するよりコストを下げることの方が国民の福利向上に資することは明白なはずだが?)、不明瞭な評価基準が導入されることで競争が歪められ、日本企業は結局中国企業に太刀打ちできない結果に陥る懸念が払しょくされたとは言えない。
- 注2)
- 再エネはいまや石炭火力よりも低コストの電源となったという主張もなされているが、それは再エネの発電コストに限った話である(しかも我が国ではその発電コストでさえも依然として石炭火力よりも割高である)。自然条件の変化によって出力が変化する再エネの間欠性を補って電力の安定供給のために需給調整する電源の費用(系統統合費用)を加味すれば、電力需要が伸び続けている途上国では再エネの全体コストは非常に高いものにつくはずだ。