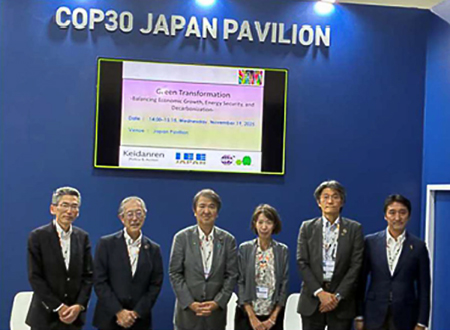COP30参戦記
~産業界の視点から~
手塚 宏之
国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)
1.はじめに
ブラジルのアマゾン河口の街ベレンで開催された国連気候変動枠組条約締約国会議COP30に、経団連のミッションとして11月16日から19日までの4日間参加してきた。筆者にとってはバリ島で開催されたCOP13から数えてこれで17回目のCOP参加になる(コロナ禍で参加を見合わせたCOP28が欠番)。政府関係者に加えて国連機関、環境NGO、研究機関、産業界関係者など、毎年のべ4~5万人が参加するとされているCOPであるが、来年の国内選挙を控えて自らの地元であるアマゾン河口という「地球の肺」ともいわれる熱帯雨林地域でCOPを開催するという伯ルーラ大統領のこだわりから、宿泊キャパシティが1万床余りしかないといわれるベレンで開催が「強硬」された。その結果ホテル代は高騰し、期間中に住民を市外移動させるなどして仮設したとされる民泊や、にわか作りの簡易宿泊施設、ラブホテルなどを総動員。ひいては大型クルーズ船(定員4000人超の船2隻)を、河口近くの浅瀬を大規模浚渫・桟橋仮設工事までして招致して、何とか実施されたものである。それでも宿泊費は通常の10倍ともいわれるほど異常に高騰し、キャンセル不可とか最低宿泊日数が設定されるなど、「普通の人が普通に参加できる」COPとはかけ離れたものとなってしまった。この宿泊先問題は途上国交渉団や非営利団体はもとより、企業からの参加者にとっても大きな障害となったはずである。筆者も例年は1週間ほど滞在するのを常としていたのだが、今回は宿泊日数を減らして予算を節約し、何とかクルーズ船に部屋を確保して4泊8日での参加となった(地球の反対側のブラジル出張は行き帰りだけで機内3泊を要する)。
そうした背景事情もあり、会場を訪れた印象は「例年より参加者が少ないな・・」ということであった。実際に例年会場でお目にかかってきた国内外の産業関係者や環境NGO、労働界・研究機関等の知己とも、会場内で顔を合わせることが少なかった。一方で11月17日の朝に筆者が参加登録に向かったCOP会場の入り口前には、交通を遮断して装甲車が配備され、マシンガンを構えて武装した兵士が数十人で警護をしていて物々しい雰囲気が漂っていた。報道によれば前週にアマゾン流域の原住民たちが大規模なデモを挙行し、自分たちの神聖なアマゾンの自然環境を「森林クレジット」のような金銭取引の対象にするCOPそのものが許せないと抗議して(環境保護を装った欺瞞であるとして)セキュリティを突破して大挙して会場内になだれ込み、警備員などに負傷者が出たことへの対策だったようである。さらに会期末の迫る11月20日には会場で火災が発生し、サイドイベント会場の屋根(テント)が焼け落ちて会場全体が半日余りにわたり立ち入り禁止となった。その結果、各国政府パビリオンで行われていた様々なイベント・プログラムがそれ以降中止となるなど、せっかくアマゾンの河口で行われたCOPであるが、ロジスティクス的には褒められたものではなく、世界最大の「環境保護の祭典」であるCOPとしては“ least inclusive COP(最も包摂性の低いCOP)”と揶揄される結果となった。
2.現地での活動
そんなCOPであるが、筆者は現地参加した実質3日間の間に3つのサイドイベントに登壇。また少なかったとはいえ、現地に参加していた欧州、米国、インドなどの産業界代表と意見交換をしてきた。11月19日の午後には今回の参加の目的の一つ、ジャパン・パビリオンで開催された経団連主催のイベント “Green Transformation: 成長・エネルギー安全保障・脱炭素化の両立“ に講演者兼ファシリテーターとして登壇した。
冒頭で前日到着されたばかりの石原環境大臣から開会のご挨拶を頂いた後(写真2参照)、経産省、日本エネルギー経済研究所から日本のGX(グリーントランスフォーメーション)政策の概要と取り組みを紹介する講演があり、さらに日本自動車工業会(トヨタ)、大成建設、JFEスチール(手塚)からそれぞれ自動車、建設、鉄鋼の各産業セクターのGXの取り組みと課題についてプレゼンテーションが行われた。その後GXを進めていく上での課題について、登壇者間でパネルディスカッションが実施された。
これまで日本を含む世界の気候変動対策では、政策的な重点課題として革新的なGX技術の開発・実用化や投資支援に焦点が当てられてきたが、そうして開発されたGX技術が実装段階に入っていく今後のトランジション期には、コスト上昇が避けられないグリーン製品が、投資回収が可能となるプレミアム価格で販売される“需要の創出”に焦点を当てた政策が必要になってくること、その先行事例として公共調達におけるグリーン製品の優先調達方針やエコカー補助金の上乗せなどの日本の実例が、官民パネリスト双方から指摘・紹介され、今後はそうした需要面での政策が拡大、強化されていくことが必要という認識で一致した。またそうした日本のGX戦略の取り組みを、今後の成長投資の中心となっていくアジア地域に普及させていくことを狙ったAZEC(アジアゼロエミッション共同体)の取り組みの重要性も強調された。
筆者はこのほかに韓国パビリオンで開催された韓国鉄鋼協会のサイドイベント(17日)、標準化パビリオンで開催された世界鉄鋼協会のサイドイベント(18日)にもパネリストとして登壇し、日本の鉄鋼産業のGX戦略の実施状況、GXグリーンスチールの国際標準化の取り組み等に加え、従来よりもコストが高くなるグリーン鋼材に適正な環境プレミアムがついて売られる「グリーン製品市場」をいかにして創出・拡大していくかが、世界の鉄鋼産業のカーボンニュートラル投資を進める鍵を握っていることを繰り返し強調させてもらった。
この、市場におけるグリーンプレミアムの負担受容という課題は、COPでもようやく昨年あたりから指摘されはじめたカーボンニュートラルに向けた政策テーマである。昨年のCOP29では、ボストンコンサルティング(BCG)が「グリーン製品市場創出」をテーマにイベントを開催して、鉄鋼やセメントなどの排出削減が困難とされる製品の排出削減には大幅なコストアップが不可避となるとしたうえで、BCGの司会者が会場に向けて「ここにいる皆さんが消費者としてカーボンコストを負担する気がなければこうした産業のカーボンニュートラル投資は進まないのですよ。」と訴えていたことが印象的だった。それが今年に入って世界の様々な研究機関、シンクタンク等がこのグリーン市場創出、グリーンプレミアムのコスト負担問題(要するにカーボンプライスの社会での負担の在り方)について課題提起を始めており、今後の世界のカーボンニュートラル政策の鬼門となっていくことを感じさせる状況が生まれつつある。その点、今回のジャパン・パビリオンでのイベントも日本GX戦略における課題意識と市場創出に向けた具体的な取り組みを紹介する良い機会となった。
3.COP30交渉結果について
そのCOP30の交渉概要と結果(グローバル・ムティラオ決定)については、交渉の専門家から他稿で様々な紹介や解説がなされているので(1)本稿では筆者が今回気になった点、特に印象に残った点についていくつか紹介していきたい。先ず今回は過去30回のCOPの歴史の中で初めて、米国政府の公式な交渉団(交渉官)の姿が見られなかったCOPであった。いうまでもなくトランプ政権が今年1月にパリ協定離脱を宣言しただけでなく、米国国務省の気候変動対策関連部署も廃止してしまったからであるが、前回の第一次トランプ政権(2017~21年)では、政権開始半年後の2017年6月1日に大統領自らがパリ協定からの離脱を宣言したものの、パリ協定の規約上、協定発効から3年間は正式離脱通告ができなかった上に、正式な脱退はその通告の1年後とされているため、実際に米国が離脱できたのは2020年11月4日であった。その日はくしくも、次の大統領選挙でパリ協定への復帰を掲げたバイデン候補が当選した前日であった。つまり前回米国が公式にパリ協定から離脱していたのは2020年11月から翌年1月のバイデン大統領就任までのわずか3か月に満たなかったのである。加えて第一次トランプ政権では離脱宣言後も米国政府交渉団はCOPに派遣されており、交渉そのものには参加していた(2)。それが今回は、米国の正式な協定離脱の発効が来年の1月になるにもかかわらず、11月の今回のCOP30にすら一人の交渉官も派遣してこなかった。この米国政府のCOP不在は、政権の方針が変わらない限り、少なくとも3年後のCOP33までの4年間続くことになり、前回の離脱と比べるとその影響が拡大していくものと思われる。
実際には今回のCOP30でも、民主党系の州知事(カリフォルニア州のニューサム知事等)や米議会議員など、米国政治の関係者もCOPに参加して気候変動対策へのコミットの継続を訴えており、また筆者自身も会場内でトッド・スターン元大統領特別補佐官、トリッグ・タリー国務省気候変動交渉官といったバイデン政権時代の米政府交渉団幹部数人に遭遇して驚いたのだが(多くは政権交代で退職してシンクタンクや大学に籍を移しているという)、彼らは将来の復帰を期して人脈や影響力の維持のために個人の立場で参加して交流に努めていたものと思われる。
一方で今回、会場内で懇談した米国の産業団体である米国国際ビジネス評議会(USCIB)の代表は、「トランプ政権がパリ協定やCOPのプロセスに反対の立場をとるのは政治的にやむを得ないとしても、全く交渉に参加しないことは米国産業界にとって望ましいことではない」と懸念を示していた。グローバルにビジネスを展開している米国企業は、自国がパリ協定から離脱したとしても、事業活動がCOPや国連関係交渉で決まった様々な国際ルールや規制の影響を受けることになるので、米国企業が不利になったり、経営が制限されるような国際ルールが決められないように、米政府も交渉の中でしっかりと調整してほしいというわけである。さらに言うと今後4年間COPの場で、米国政府抜きで様々な国際的な取り決めに関するCOP決議がなされていくと、米国が絶対に認められないようなルールやコミットが決まっていく懸念があるという(例えば途上国への巨大な資金支援拡大の義務化や中国との差別的な権利・義務の固定化など)。将来トランプ政権から政権交代が起きた際に(民主党政権になるにせよ共和党新大統領になるにせよ)「パリ協定への再加入」ができなくなってしまうような事態も懸念される。さすがにパリ協定そのものが米国の容認できない形で改定されるような事態は考えにくいが、毎年のCOP決議で追加されていくその運用ルールや新たな義務などで、大統領権限だけで米国が実行を担保できない案件(新たな予算措置を要するものや国家安全保障の機微に触れるものなど)が、この米国不在の4年間に合意・決議されると、米議会上院の承認なしにすんなりと再復帰しにくくなり、あるいは米国不在時のCOP決議を受諾しないといった条件付きで再参加するというように、COPを複雑化する事態も起きうるかもしれない。その点、今回のCOP30の決議 では、途上国の求めた適応資金の3倍増という支援拡大が義務化されることなく、「努力を求める」程度の表現に収まったことは、結果的に米国のレッドラインも超えずにすんだということになる。
一方、従来COP交渉の場で先進国グループの一翼を担ってきた米国が抜けた今回のCOPでは、1.5℃目標の達成に向けた排出削減の強化を中国、インドを含む途上国に執拗に求めてきた欧州勢(EU+英国)が、対途上国交渉で矢面に立たされて苦戦していたという感が強かった。ネットゼロ強硬派として有名な英労働党のミリバンド環境エネルギー大臣(一時は首相候補にもなっていた)が率いる英国は、議長国ブラジル、EU、島嶼国、最貧国らと共に連合を組み(80か国余りが賛同)、削減対策の強化を狙って「化石燃料からの移行(フェーズアウト)のロードマップ策定」を決議すべく交渉に臨んだというが、結局サウジアラビア、イラン、ロシアなどの産油国の強硬な反対にあい、COP30決議からこの「化石燃料フェーズアウト」は消えてしまい、結果として決議文には「化石燃料」という言葉すら一切触れられていない。交渉が対立した最終局面でEUの交渉団は、本国のフォン・デア・ライエンEU委員長に交渉決裂も辞さない覚悟で化石燃料フェーズアウト・ロードマップを求める交渉を続けることの是非を打診したと報道されていたが、米国が脱退してパリ協定の土台にひびが入る中で、交渉決裂によってこれ以上パリ協定の協調的な枠組みに傷をつけることはパリ協定の弱体化を招き、得策ではないと判断して引き下がったのかもしれない。
一方EUがさらに単独で矢面に立たされていたのが「制限的貿易措置」に関する決議である。来年1月からEUが本格導入・運用を開始する炭素国境調整措置(CBAM)について、これを気候変動枠組み条約ならびにパリ協定が原則禁止している「気候変動対策として偽装された一方的な国際貿易制限措置」であるとして、インドを筆頭とした途上国が束になってEUを責め立て、COPの場でその是非を協議すべき(=交渉議題にいれるべき)と主張した。この点については、最終的な合意文書の中で今後2028年までの3年間、締約国、WTO、UNCTAD,ITC他のステークホルダーを含めた対話の場を設け、28年のハイレベル会合で見解の交換を行ってCOPの場に正式に報告することが決まっている。今回会場で意見交換した欧州経団連(Business Europe)のメンバーは、「CBAMの国際貿易制度上の問題は高度に専門的な通商法上の問題であり、そもそもそれは各国財務省の所管なので、環境閣僚や環境省交渉官の集まるCOPは議論の場として不適切だ。WTOで議論すべき問題である。」と言っていたのだが、結果的にはCBAM問題は、WTOも議論には加わるとはいえCOPに正式に報告・議論をすることが決議され、EUの意に反してCOPの俎上にのぼる道が開けてしまったことになる。
以上のように今回のCOPでは今まで気候変動の世界で議論をリードしてきたEU(英国含む)が精彩を欠き、取るものは取れず(COP28から強くこだわり、再三蒸し返して俎上にのせてきた化石燃料フェーズアウトの決議に失敗)、一方で途上国に押し込まれてCBAMの是非をCOPの場で議論する道が開かれてしまい、さらに努力義務とはいえ途上国の適応対策への先進国による資金協力規模を3倍にすることまで決議されている。EUは取るものをとれず途上国の要求に押し込まれて終わったというのが実情だろう。近年EU域内では英独仏の主要国の国内で、気候変動対策に後ろ向きな右派政党が躍進してきており、もともと気候変動対策に消極的だった東欧諸国の発言力が強まってきている中、EUとして一丸となってCOPに臨み、世界の気候変動対策をリードしてきた従来の立ち位置が次第に崩れ始めているということを感じさせられるCOPであった。
現地で会食を共にした欧米の経済界代表たちとの会話の中で、あるEUの産業関係の政策シンクタンクの代表が以下のようなコメントをつぶやいたのが大変印象的であった。
曰く「EUはあまりにも野心的な高い目標を掲げて気候変動対策を進めてきたが、その結果エネルギーコストが跳ね上がり、産業の域外脱出と空洞化によって域内生産・雇用の衰退が進んでいる。これはあきらかに経済的な自殺行為だ。このままいけば10年後のヨーロッパは、世界遺産と美術館・観光だけで食べていくことになっているかもしれない・・・。」
インバウンド観光客に沸くなかでGX戦略を進めている日本にとっても、これは「他山の石」として深くかみしめるべき教訓ではないだろうか。
脚注
- (1)
- 例えば以下を参照:https://agora-web.jp/archives/251130104115.html
- (2)
- 第一次トランプ政権でもパリ協定からの離脱は宣言したものの、その親条約である気候変動枠組み条約そのものからは離脱をしておらず、その条約締約国会議に米国交渉団が参加することは自然であった。この状況は今回の第二次トランプ政権でも変わっておらず、引き続き交渉団を派遣することは形の上では可能なはずだが、それは実行されていない。