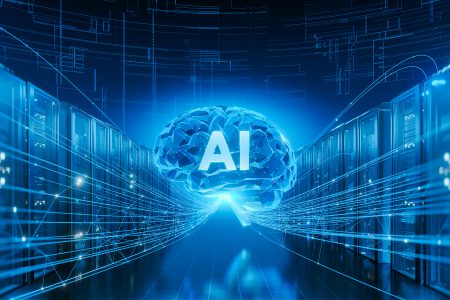AI活用の必要条件は電力供給
最新エネルギー市場
山本 隆三
国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授
(環境市場新聞2025年(令和7年)秋季 第82号【季刊】より転載)
学校、職場などにも利用が広がる生成AI(人工知能)を支えるには、情報を処理するデータセンター(DC)が必要です。世界には1万以上のDCが有り、その半分を持つアメリカが生成AIでも世界をリードしています。それを追い上げているのが、格安の費用で開発されたディープシークに代表される中国の生成AIです。
中国のDCの数は世界4位でアメリカの10分の1以下。ですが多くのシンクタンクはやがて中国の生成AIがアメリカに並ぶと予測しています。
中国の生成AIとDCを支えるのは年間10兆キロワット時の世界一の電力供給量です。世界の発電量の3分の1に相当し、2位アメリカの2.5倍、日本の10倍です。DCの増加で電力需要の大きな伸びが見込まれる中、発電関係のインフラ整備に制約の少ない中国がアメリカより有利と考えられます。
では、日本のDC整備と電力供給に不安はないでしょうか。日本の全電気事業者が会員の電力広域的運営推進機関により今年6月発表された電力需給の予想は最大で2040年に4600万キロワット、2050年に8900万キロワットの発電設備が不足する可能性があるとしています。電力供給がなければDCは新設できず、AI活用も広がりません。
日本政府は、地方でDCの新設を想定しています。以前の連載で触れたように、地方では電気や機械の技術者不足が心配されています。そこに電力供給の不安も出てきました。今まで発電設備の不足が心配されなかった大きな理由は、電力需要が波を打ちながら減少していたからです。
1985年の発電量6500億キロワット時は、1996年に1兆キロワット時を超えましたが、その後失われた30年間で需要は頭打ちになり、発電量も2008年をピークに波を打ちながら減少しました。その背景には省エネもありますが、鉄鋼、セメントなどのエネルギー多消費型産業の成長が鈍化したことも大きな原因でした。しかし、EV(電気自動車)を中心とする電化の進展とDCの新設が電力需要を押し上げると、たちまち設備不足の心配が浮上します。
なぜ電力事業者は設備を新設しないのでしょうか。理由は2016年の電力市場の完全自由化で電力価格の見通しが不透明になったことがあります。将来の価格と収益の見通しが立たない中では発電設備の大きな投資に踏み切れません。電力供給の見通しがなければDCの日本での建設は進みません。まず発電設備の建設が進む制度が必要です。太陽光、風力発電には固定価格買取制度が用意されていますが、再生可能エネルギーに加え安定的な電源がDCには必要です。早急な制度の整備が望まれます。