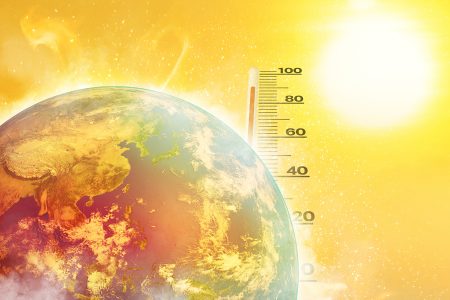1000年に1度の洪水と呼ぶのは不適切だ
印刷用ページ監訳 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 杉山大志 訳 木村史子
本稿はロジャー・ピールキー・ジュニア
What is a 1000-year flood?-It is time to retire the concept を許可を得て邦訳したものである。

Washington Post in 2017
誰しもがこの用語を耳にしたことがあるだろう。洪水や熱波といった異常事態が発生すると、その直後に「1,000年現象」(1,000である必要はなく、どんな数字でもよい)と表現されることがある(訳注:日本では1,000年に1度の現象と訳されることの方が多い)。今週私は、世界で最も注目されている気候科学者の一人であるマイケル・E・マンが全国放送のテレビに出演し、その中で、この概念が実際に何を意味するのか全く分かっていないのを見た。
まず、一般的な誤解(気候科学者ならばよく知っているはずの内容)をしている気候科学者を正すことから始めよう。1,000年洪水とは、1,000年ごとに起こる洪水レベルのことを指すのではない。
米国地質調査所の説明によると:
1,000年洪水という言葉は、統計的に言えば、その規模(またはそれ以上)の洪水がある年に発生する確率が1,000分の1であることを意味する。つまり確率で言えば、1,000年洪水はどの年においても0.1%の確率で発生する。
同じく、2年洪水はどの年でも50%の確率で起こり、100年洪水はどの年でも1%の確率で起こる。もし、6面体のサイコロ2個を使うのであれば、ゾロ目(つまり両方とも1が出る)を振ることを「36振り現象」と呼んでもよいが、私が遊ぶサイコロゲームでは、誰もそんなことは言わない。みんなが混乱するのも無理はない。
さいころで「1・1」のゾロ目を2回続けて出すことはできるのか?もちろん可能ではある。1人で「1,296振り事象」を起こすことは大変だが、それでも起こりうることではある。では、全米50州の30人が同時に2つのサイコロを振ったとすると、1,500回のうち、どれだけの確率で「1・1」のゾロ目が出るであろうか。あるいは、その30人が1年間毎日一緒にサイコロを振るとしたらどうか。30人ではなく、それが500人だとしたらどうなるか。
「100年洪水」という概念は、少なくとも1930年代の米国の洪水政策に遡ることができ、米国の洪水政策の父であるギルバート・ホワイト(嬉しいことに、彼は私のコロラド大学の元同僚であった)が導入した概念である。ホワイトの才気と影響力にもかかわらず、この概念には根本的な問題がある。1999年、私は「洪水に関する9つの誤り」という論文で、N年洪水を取り上げたが、これには理由がある(余談だが、その論文を注意深く読むと、その部分にいくつかの誤植があることに気づくはずである!)。
ここで、N年事象という概念の問題点を挙げてみよう:
- ●
- N年事象は固定値ではなく、気候の変動と変化により時間とともに変化する。例えば、カリフォルニアで大量の雨が降る確率は、毎年同じではない。その年の気候の状態や、ENSO(エルニーニョ・南方振動)、PDO(太平洋十年規模振動)の位相など、さまざまな要因に左右される。
- ●
- N年事象は通常、非常に短い気候記録(時には10年や30年など)に基づいて推定される。例えば、テキサス州のエネルギー規制当局は、2021年の大停電の前に生じる凍結災害のリスクを判断する際に、わずか14年間のデータしか考慮しなかった。
- ●
- N年事象は、時間的にも空間的にも独立した出来事ではない。気候パターンによってN年事象が密接に関連することがあるのだ。このため、サイコロの例えは通用しないのだ!
- ●
- 実際のところ、N年事象というのは、現実的な意味を持つ用語としては存在しえないのかもしれない。もちろん概念として持ち出すことは出来る。けれども、例えばN年洪水が何度も連続するとしたら、それはN年洪水なるものに対する我々の理解が的外れである可能性が高い。なにしろ、とても想像しきれなかったようなことが現実世界では次々に起こるからだ(世界金融危機のリスクモデルとの比較もあるが、それはまた別の機会に)。
アメリカ地質調査所による以下の解説を読んでみてほしい:
100年に一度の洪水が2年連続で起こることもある:
頻度分析と呼ばれる統計的手法により、ある降水事象の発生確率を推定することができる。再現期間とは、与えられた事象が任意の年に等しいか超える確率に基づいている。例えば、ある地域で、ある年の24時間に6.60インチの雨が降る確率が50分の1であるとする。この場合連続する24時間の間に合計6.60インチの雨が降ることは、50年の再現期間を持つことになる。同様に、頻度分析(Interagency Advisory Committee on Water Data, 1982)を用いると、ある流水測定地点で15,000立方フィート/秒(ft^3/s)の流水が1年間に発生する確率は100分の1であることがわかる。したがって、この場所で15,000 ft^3/sのピークフローが発生した場合、100年の再現期間を持つということになる。 降雨の再現期間は、降雨事象の大きさと継続時間の両方に基づいているのだが、流水の再現期間は、年間ピークフローの規模にだけ基づいている。
頻度解析で再現期間を求めるには、10年以上のデータが必要だ。もちろん、過去データの年数が多ければ多いほど良く、水文学者は、10年の記録に基づく分析よりも、30年の記録を持つ河川の分析に信頼を置くであろう。
ある地点における年間ピーク流量の再現期間は、その地点の流況に大きな変化がある場合、おそらく流量の貯留または分流によって引き起こされるのであろうが、そのような場合において変わる。開発(森林や農業用地から商業、住宅、または工業用地への転換)がピーク流量に及ぼす影響は、一般に、25~50 年または100 年洪水のような高い再現期間の洪水よりも、低い再現期間の洪水の場合のほうがはるかに大きい。大規模な洪水時には、土壌の水分は飽和状態にあり、追加の降雨を吸収する能力がない。そのような条件下では、舗装された表面や飽和した土壌に降った雨は、基本的にすべて流出し、河川流となる。
以上はごく単純なことだ。この説明では気候の変動や変化には触れないが、どちらもN年洪水が固定的・定常的でないことを理解する上で重要である。
ここで、極端な事象を議論する際にN年事象を用いることについて、私の見解を述べようと思う。
ただ、ノー、だ。N年事象という用語を使うべきではない。
この概念は広く誤解されている。そして、気候システムに関する現実を反映していない一連の仮定に基づくものだ。そして現在、いわゆる事象の帰属研究やプレスリリースで広く使われているが、これは混乱を助長するだけである。
この概念は米国の洪水政策の中に組み込まれており、保険業界で使用されているのも事実である。
しかし、お飾りの気候科学者がその概念すら理解していないのであれば、おそらく公の場ではもっと役に立たないだろう。異常気象について話すときには、N年事象という言葉は持ち出さない方がよい。