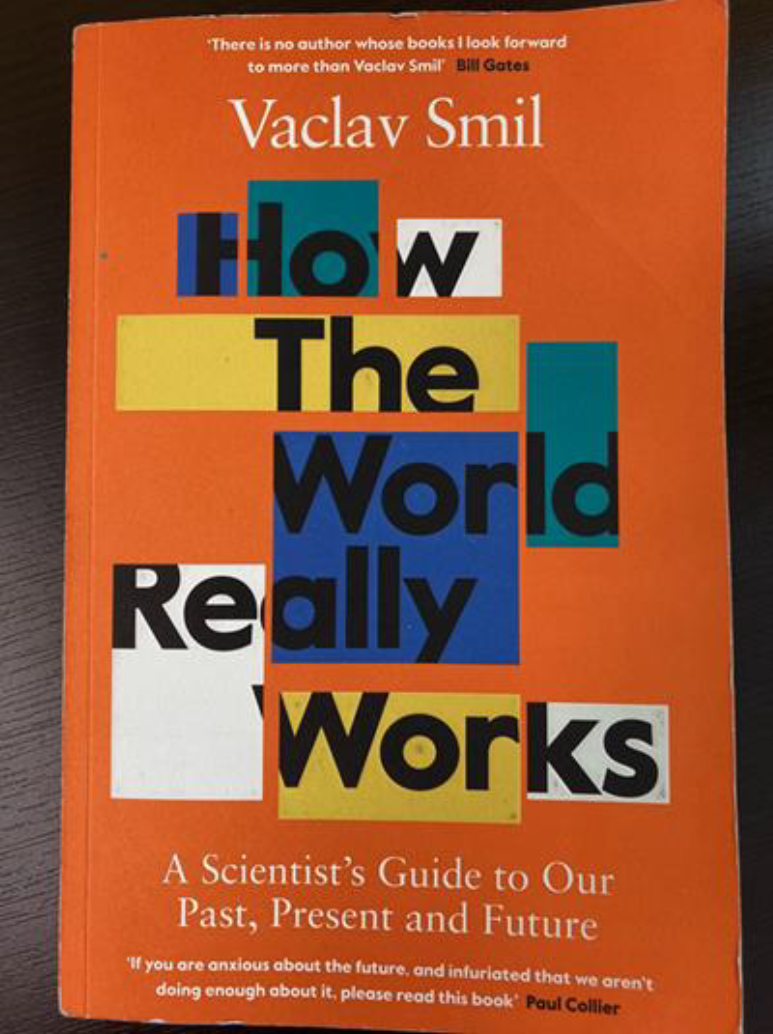それでも化石エネルギー文明は続く(その1)
世界はいかにして営まれているか
手塚 宏之
国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)
1.われわれは化石エネルギーを食べて生きている
毎日の家庭の食卓にのぼる食事の食材が、どのようにして作られているのか、我々が毎日の食事を通して、どれだけの化石エネルギーを「食べて」いるのか?こうした問いについて、その実情を理解している人は、筆者を含めてほとんどいないだろう。ところが、その「不都合な真実」を定量的に明らかにしてくれる書籍を最近読んで目から鱗の経験をし、今後の気候変動対策について深い示唆を与えてくれるので、本稿ではその書籍の概要について筆者の私見を交えながら紹介することにしたい(欧米のデータに基づいたものなので日本とは少し事情が違うが、同書の主張は普遍的な科学的知見に基づいており、得られる教訓は共通である)。
さて、米国で家庭の食卓に1㎏のパンが上るまでに必要とされるエネルギーはどれほどになるか?正解は、大農場での機械化された小麦の生産から脱穀、製粉、輸送、製パンプロセスを合わせて、ディーゼル燃料換算で200~250mlに相当するという。同様に、1kgの加工された鶏肉が、米国家庭の食卓に上るまでに必要なエネルギーは、養鶏用飼料(コーンや大豆)の生産と養鶏所までの輸送(多くの場合遠隔地の農場から大量輸送される)、大規模な養鶏舎における飼育プロセス(暖房燃料を含む)、食肉加工過程(可食部分の歩留まりは60%に留まる)、肉の冷蔵・冷凍、梱包と、消費地のスーパーへの冷蔵配送等にかかわるエネルギーをすべて足し合わせた、ディーゼル燃料換算での総必要量は約300~350mlに上るとされている。
トマトの場合は話がもう少し複雑になる。グレタ・トゥーンベリ女史が住むスェーデンの食卓に上るトマトの例を見てみよう。欧州で最大のトマト生産地、スペインのアルメリア地方では、4万ヘクタール(20㎞×20㎞!)の広大なビニールハウス群で、多毛作により年産3百万トンのトマトが栽培され、その80%がEU域内各国に輸出されている。その栽培には莫大な窒素、リン肥料が使われ、温室の加熱を合わせて、トマト1㎏あたり150~500mlの燃料が必要である(ちなみに1㎏の窒素肥料生産には1.5リットル相当の化石燃料が必要である)。またハウス栽培に使われるビニールは石油由来の素材であり、さらに生産されたトマトは大型トラックに積載されてスペインから3745㎞離れたストックホルムに1120mlのディーゼル燃料を使って運ばれ、さらに現地で加工、パッケージ、保管され、1㎏あたり140mlのエネルギーを使って市内のスーパーの棚に陳列される。スェーデンの食卓で1kgのトマトを食べるのに消費されているディーゼル燃料は、総計650ml。つまりワインボトル1本に近い化石燃料をトマトと共に「食べている」ことになるという。前述のパン1kg、鶏肉1kgと合わせると、毎日の食卓で1.15~1.65リットルもの化石燃料が消費されることになり、これが世界中の家庭で大なり小なり毎日繰り返されていることになる(筆者註:日本の軽油のCO2排出係数は2.65tCO2/klなので、これら3㎏の食材だけで3~4kgのCO2を排出して食卓に届けられていることになる)。
2.世界はいかにして営まれているか
この数字は、マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツをして、「この人の新著が出版されるのを心待ちにしている」と言わしめ、同氏の科学アドバイザーを務めてきた、カナダのマニトバ大学のヴァークラフ・シュミル特別名誉教授の新著「How the World Really Works(世界はいかにして営まれているのか)」(Penguin Books 2022:未翻訳)に示されているものである。
ゲイツ氏は毎年、夏休みに読むべき推薦本を発表しているのだが、今年の6月に発表された推薦図書5冊の中に、同書が含まれていて、表紙にはゲイツ氏自身の推薦文が書かれている。ちなみにシュミル教授は、日本政府が2014年から毎年開催しているICEF (Innovation for Cool Earth Forum)の運営委員を、創設以来務められており、実は筆者も製鉄所の見学を案内するなど、個人的なお付き合いをさせていただいていて、著書もいくつか拝読させていただいている。
さて、ゲイツ氏も大推薦する同書であるが、まずシュミル教授は冒頭前書きの「なぜ我々には本書が必要か?」の中で、基本的な問題意識として、そもそも先進国社会に住む大半の人々が、モノや食物の「生産現場」から切り離されて生活しており、「現場」に関する知識も肌感覚も持ち合わせていないことが問題だと切り出している。
実際、3億人にのぼる米国人は、日々自分たちが食べているパンや肉などの食物が、人口のわずか1%、300万人の人たちによって生産されてということを知らないし、ほとんどの人々は、身の周りで使う便利な機械やデバイス、加工食品といった必需品が、いったい何からどのようにして作られて、手元に届けられているかという「現実」から切り離された世界で生活しているという。都会生活を送る多くの人は、日常使うものや食べている食品が、どんな原材料をどうやって確保し、加工して生産され、それがどこからどうやって自宅に届けられるか、そしてその過程でどれだけのエネルギーを消費しているかについて、まったく無知だという。
シュミル教授は冒頭でこれを指摘した上で、そうした物資の生産と供給には、物質とエネルギーに関する物理法則に由来する制約が存在しており、普段の生活で日々スマホやパソコンを通して接している、ヴァーチャルな情報やエレクトロニクスの世界とは、全く異なる世界であることが認識されていないというのである。その上でシュミル教授は、現在の人類文明は、本質的に「化石燃料文明(Fossil-fueled civilization)」であるとし、人類がそうしたモノの生産と供給を前提とした生活水準を維持し、便利な世界で繁栄を続けていくためには、当分の間、莫大な量の化石燃料の消費が必須であり、その制約を克服し、脱炭素化するのは不可能ではなく、またそうするべきだとしながらも、それには何十年もの歳月を要するのだ、としている。2050年までの急速な脱炭素化は可能であり、あるいはそれを実現するべきといった主張の背景にある虫の良すぎる話(wishful thinking)と、現実(reality)の間には、埋めがたい巨大なギャップが横たわっているというのである。
3.繰り返される終末論
今世界に広まっているカーボンニュートラルに向けた挑戦の背景にあるのは、気候危機、つまり人類が化石燃料を大量消費した結果、地球温暖化が進み、このままでは地球は人類が住めない星になってしまうという、一種の終末論である。シュミル教授によれば、この手の終末論は過去にも繰り返されてきた。中でも60年代から70年代に繰り広げられた「成長の限界」説は、筆者の記憶にも残っているが、そこでの基本的な主張は、第二次大戦後に急増する世界の人口が、このまま増え続け、巨大な消費を続ければ、石油などの天然資源がたちまち枯渇し、また食料の供給が足りなくなって、いずれ人類は成長の限界に突き当たり、文明の破局を迎えるというものであった。シュミル教授も本書の中で、例えば米国の名門科学雑誌「サイエンス」が1960年に掲載した論文のシミュレーションでは「このまま人類の人口増加が続けば2026年11月13日に人口増加率は無限大に達する」と警告していた、と皮肉を込めて紹介している。しかしその後の経緯を知っている我々は、こうした将来予測に基づく過去の終末論も、聖書やノストラダムスの予言同様、ことごとく外れてきたことを知っている。
その現実に起きたことは、石油危機により石油の需要増は抑制されたものの、石炭、天然ガスなどの化石燃料需要は70年代からも継続して大幅に拡大した。一方でその間、探索・掘削技術の進展や、シェール革命といった技術イノベーションにより、需要に見合う供給拡大が続き、世界的に人口が急増した現在の人類も、依然としてエネルギーの8割以上を、潤沢に供給される化石燃料によって賄って生活を送っている。
4.終末論の克服
シュミル教授によれば、「成長の限界」説が唱えた、食糧危機という一昔前の「終末論」は(現在の終末論は言うまでもなく気候変動問題である)、化学工学におけるハーバーボッシュ法という技術革新によって過去のものになったという。20世紀後半から大量生産が始まったハーバーボッシュ法による合成アンモニアを使った窒素肥料の大量導入によって、農業生産は飛躍的に拡大した。60年代から世界の人口が3倍に膨らみ、今や80億人が地球上に暮らしている一方で、低所得国における栄養不足者の人口比率は、60年代の40%から2019年には11%にまで低下している。それを可能としたのが、従来の動植物由来の堆肥に頼った有機農業から、化学合成されたアンモニア由来の窒素肥料の大量投入による大規模近代農法への転換による、穀物生産の大幅拡大であった。1975年以来、世界の窒素肥料使用量は2.5倍に膨らみ、その結果同じ農地での農業の生産性が上がり、穀物の収穫も2.2倍と、60年代には想像できなかった大量生産、大量供給が可能となったというのである。
現在、世界では年間1.5億トンのアンモニアが、主に天然ガスを主原料として生産されており、その8割が肥料生産に向けられている。天然ガスは化石燃料として使われているだけではなく、80億人の食を支える肥料の主原料としても使われているのである。シュミル教授によれば、もし窒素肥料がなければ、食糧生産は激減し、たちまち人類の半分にあたる40億人が、飢餓によって死滅することになるという(筆者註:全ての作物を有機栽培に転換すると突如決めたスリランカの農業生産が壊滅し、政権転覆という混乱の引き金を引いたのはつい先ごろである)。
昨年まで世界最大の天然ガス輸出国であったロシアは、実は同時に世界最大の化学肥料輸出国でもあった。そうして見ると同書は、ロシアのウクライナ侵攻による世界的な天然ガス供給危機と価格高騰が、眼前に繰り広げられているエネルギーインフレという経済危機に加えて、今後、深刻な肥料供給不足と肥料価格高騰による世界的な食料供給不足と食品インフレという二次的な災害をもたらす深刻な懸念があることを示唆しているとも読むことができる(筆者註:ちなみに同書は今年1月に発刊されているので、ウクライナ紛争ぼっ発前に書かれたため、こうした問題についての記述はない)。
次回:「それでも化石エネルギー文明は続く(その2)」へ続く