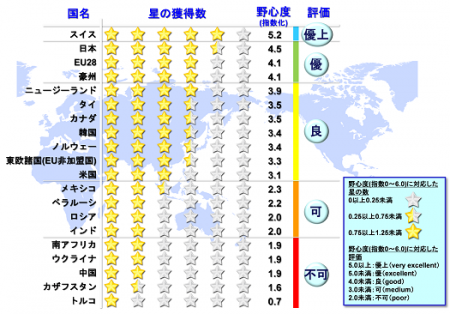第6次エネルギー基本計画 -「科学的評価」の難しさ
秋元 圭吾
公益財団法人 地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー(IPCC WG3 第5次、第6次評価報告書代表執筆者)
第6次エネルギー基本計画の策定が間近になっている。筆者は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会等の委員を務め、この議論に参加してきた。本稿では、エネルギー基本計画の中身については議論せず、その議論のプロセスにおいてしばしば明に暗に登場した「科学的評価」について、考えたところを述べたい。
基本政策分科会において、消費者団体の委員から、エネルギー政策の議論に若者の参加を取り入れるべきと何度も発言がなされた。将来世代の社会に大きく影響するため、その当事者となる若者を議論に加えるべきという点で、筆者も原則論としてはそうあるべきだと思う。一方それは、エネルギーという、まさにS+3Eの総合的な知識、理解を高い水準で有していることが前提であるように思う。エネルギー政策を決めるための議論は、それぞれの分野の深い理解と、総合科学としての全体感の理解が不可欠である。審議会は時間も限られており、深く総合的に議論することは不可能であるため、参加者にはベースとなる多面的な知識が備わっていることが求められる。そのため、ただエネルギー問題の発信を積極的に行っているというだけで参加対象となってしまう場合のことを想像すると、消費者団体の委員のこの意見に積極的に賛成しにくかった。
明示的カーボンプライス導入を求める意見もあった。カーボンプライスは、CO2排出による気候変動影響の内部化としては重要であることは論を俟たない。一義的な科学としては正しい。しかし、カーボンプライスの議論はそれほど単純な話ではない。2030年▲46%や2050年カーボンニュートラルのためにいくらの炭素価格水準を求めているのかなどを含めた議論が必要である。消費者団体代表が、カーボンプライスの導入を求めることが多くあったが、その予想されるあまりに高い価格水準と、それに伴う消費者負担の大きさのイメージ感があるのか図りかねた。これも▲46%の科学的な議論がないため、カーボンプライスの具体的なメリット、デメリットの議論ができない。ここでも表面的な科学と、科学の総合化という点で単純な議論にギャップがあり、簡単には賛同できないのである。
RITEは、モデル分析結果として、2050年カーボンニュートラルシナリオを基本政策分科会に提示した。ある研究機関は、需要側の対策が重要で、RITE分析では考慮が足りないと主張した。一方で、電力限界費用の推計を批判的に論評し、平均費用にすれば安価になり、生産者余剰を小さくできるとも主張がなされた。しかし、提示した電力限界費用は、可変費と固定費を含めた長期限界費用に基づく限界価格であって、社会厚生を最大化する需給均衡解として求まるものである。需要側の対策を適切に引き出すためには、理論的には限界費用で価格が決まることが重要である。もちろん、実際の社会はモデルが想定するような単純さがなかったり、衡平性の問題などから、電気料金をどう設定するかは、複合的に決められるべきであるが、そういう主張ではなかったと理解している。
RITE以外の2050年カーボンニュートラルシナリオ分析についても提示がなされた。しかし、再エネ100%のシナリオは除外するとしても、再エネ70%台のシナリオを2機関が提示したが、この再エネ比率は、他のエネルギーの比率等を外生シナリオとして制約していることから、モデルの計算上の尤度はなくなっており、経済計算で内生的に決まるのではなく、モデル計算の前にほぼ決まってしまっている数字である。基本政策分科会でシナリオの議論は行ったものの、このような点も、短い議論の中では社会には正確に伝わらない。モデル分析者以外には、何を科学的な分析として導き出しているのか等を理解するのは必ずしも容易ではないと想像される。
また、内閣府の再エネタスクフォース(TF)は、7月30日の基本政策分科会で、エネルギー基本計画素案に対して意見表明を行った。しかし、その意見表明に対して、基本政策分科会委員の多数から強い批判が相次いだ。再エネが安価でポテンシャルも豊富だと主張するなら、再エネ政策は不要ということになるはずだが、主張が一貫的ではない。再エネ業界団体は再エネに期待しつつも、実際の事業においてその難しさも実感していることから、ある程度慎重さが垣間見えたが、再エネTFの主張は外野からの無責任なものに見える。容量市場の凍結の主張も同様である。2021年1月のスポット市場高騰の批判を強くしておきながら、容量市場は凍結すべきと主張する。科学的な整合性はほとんどない。また、欧州は日本よりも導入目標が高いなど、欧州との比較が何度も繰り返されたが、産業構造、自然条件や土地の条件やそれによって変化する再エネポテンシャルとコストなど、具体的にそれらの差異を踏まえた上での分析に基づいた議論はなかった。
国際的に気候変動対策への要請が強まっている中、2050年カーボンニュートラル、2030年▲46%(さらに▲50%の高みを追求)という高い排出削減目標を掲げなければならない状況となったことは理解する。特に2050年カーボンニュートラルはイノベーションへの取り組みによる目指すべき方向性という位置づけで理解はできる。しかし、2030年▲46%は、2050年ゼロまでの直線に乗っている数字くらいの意味合いでしかない。本来、科学に基づき、コスト、経済影響等を踏まえた上で決めるべき目標である。先に▲46%は科学的な議論を経ずに決まってしまったため、エネルギー基本計画における2030年のエネルギーミックスは「帳尻合わせ」にしかなり得なかった。すべての対策をストレッチするしかなく、それに加えて、稼働までの期間が短い太陽光発電を更に大幅にストレッチして「帳尻合わせ」するしか手段がなかったのである。気候変動対策の議論において、「科学に基づき」意思決定されるべきとよく主張されるが、それは気候変動影響の議論でなされることが多いが、同様に気候変動緩和の議論での「科学」は、少なくとも2030年目標ではなおざりにされた。
第5次エネルギー基本計画においては「科学的レビューメカニズム」を構築するとされていた。また、第6次計画に関する基本政策分科会の議論でも、複数の委員から「科学的レビュー」の重要性の指摘もなされた。筆者も原則論としては当然強く支持するところである。エネルギー・気候変動対策においては、様々な不確実性があり、それぞれの不確実性の幅が大きく、「科学」は一意に決まらないことが多いが、それでもその中で、学際的かつ総合的、そして、深淵な真理の探究に基づいた科学が必要である。しかしながら、何がより蓋然性の高い科学なのか、何がより真実に近い科学なのか、を見極めることも社会の多くの場面において容易ではない。「科学的評価」の御旗の下で、単純で表面的な科学が横行し、エネルギー・気候変動政策が歪められてしまう危険性もある。「科学的評価」の必要性が指摘されるたびに、これまで記載してきたような点が思い起こされつつ、もやもや感が蓄積していった。そして、エネルギー基本計画議論の終段となった7月30日の基本政策分科会では、言葉は悪かったかもしれないが、筆者は、横行する「薄っぺらいサイエンス」に引きずられないようにしなければならないと願望を述べた。なお、第6次エネルギー基本計画の素案からは、第5次計画記載の「科学的レビューメカニズム」のような強い記述は消えている。