エネルギー生産性改善の要因はどう認識されるか?
-『日本の経済成長とエネルギー』(慶應義塾大学出版会)書籍紹介-
野村 浩二
慶應義塾大学産業研究所 所長・教授
優れた経済学者は経済統計量の変化や、統計量相互の関係性において数量的な感覚を持っている。本年初め、経済測定分野の第一人者であるアーヴィン・ディーワート教授(ブリティッシュコロンビア大学)から、中国の政府消費価格と自己所有住宅の家賃評価に関する問題提起を頂いた。中国GDPが水増しされているという巷にある批判ではなく、むしろその水準が歴史的に小さく推計され、長期の経済成長率や生産性が過大に評価されている可能性である。この数か月間、ともにそのパズルの解明へと取り組んだが、データに基づき分析し、見いだされた問題によってデータ自体が見直され、そして再び分析していく、こうした漸近的な改善によって真理へと近づこうとする経験科学のアプローチは、経済現象にも適用される。むしろ経済現象では、統御された実験が困難なだけに、データが発生するメカニズムの解明と観察とは一体ともなる。
微力ながらも、これまで経済測定の諸問題へ取り組んできた著者の経験では、その変化における数量的な感覚をもっとも持ちづらい統計量のひとつが、マクロや産業など集計度の高いレベルで測定される「エネルギー生産性」であった。それはエネルギー消費量というインプットと、生産量(実質GDPや生産トン数など)やエネルギーサービス量(輸送トンキロ、冷暖房面積など)などのアウトプットとの比によって定義される。しかしエネルギーコストは数%のシェアしか持たず、価格の変動も激しいために、経済統計に基づくその測定値は大きく荒れ、変化の解釈も難しい。エネルギー統計に基づけば、整合する適切なアウトプット指標を持たないために、抽象度の高いマクロか代表性を欠く部分的な評価に留まってしまう。
個別機器、建設物やプラントなど細分化されたレベルでは、エネルギーサービス量などのアウトプットを定義しやすく、多くの工学的な分析が蓄積されている。それは概念的にはエネルギー生産性とも類似するが、集計度の低いレベルで測定される「エネルギー効率性」は技術的な要因によって規定される。しかしエネルギー生産性はアウトプットとインプットの双方が集計量として、それぞれの内部の構成変化(アウトプットでは生産される製品構成や産業構造の変化、インプットでは電力化などエネルギー種構成の変化など)の影響を含んでいる。集計度の高いレベルで測定されるエネルギー生産性は、経済的(非技術的)要因に大きく依存する。
両者の間には大きな溝が存在するが、その解明なきままに、政策評価としての誤謬を生じさせてきた。誤謬を生む第一の要因は、経済的要因の無考慮である。2010年代、マクロ的に観察されるエネルギー生産性の改善は、経済的な変化要因が問われることもないままに、あたかも技術的な改善であるかのように解されてきた。それは省エネに向けた規制強化や省エネ機器導入のための補助金政策など、現行政策の自信を深めさせている。しかし、そうした「改善」の多くは見かけ上のものにすぎず、集計量の内に潜む経済的要因による影響を大きく反映したものであることは忘れられている。
政策評価の誤謬を生じさせるもうひとつの要因は、エネルギー生産性改善が独立した事象のように評価されてきたことである。本来「生産性」としての理解は、エネルギーが投入要素のひとつに過ぎないという認識と結びついている。アウトプットを産出するには、エネルギーとともに、資本や労働といったインプットが必要である。生産への貢献度はむしろ後者が大きく、エネルギーは資本を稼働するための付随的な需要にすぎない。エネルギー生産性は労働生産性や資本生産性と並列に定義され、エネルギー投入の一面のみに基づく評価は、木を見て森を見ずとする批判を免れないだろう。労働者が生産性を高めるためのカギは、(個々が人的スキルを改善させるよりも)より多くの物的資本を利用することにある。エネルギー生産性改善のみが目的関数ではない。
「省エネの余地はまだ多く残る」という主張は日本でも多い。しかし、その実現には省エネ設備投資が必要であり、モニタリングや管理のための(そして社会的には政府が省エネ政策を推進するための)人件費も必要である。現実のエネルギー生産性の水準は、エネルギーコスト減少とそのために必要なコスト増加との比較考量のもとに定まっている。そのもとでは、「技術的に可能な限りの高い省エネ水準」が実現していないことは当然であり、また合理的である。長期にわたり世界でもっとも高い二次エネルギー価格に直面してきた日本経済には、省エネへのインセンティブがもともと組み込まれている。またオイルショック後に、省エネが政府の仕事として組み込まれてからすでに半世紀近くが経過した。市場メカニズムの導く水準を不十分であるとして、全体を見ずに部分のみを見て強化されるエネルギー政策は、資本蓄積に歪みを与え、労働生産性の改善を抑制し、全体的な経済効率を低下させてしまう懸念は大きい。
昨年10月、政府は見通しなきままに脱炭素宣言を示した。エネルギー供給側における脱炭素の難しさは、(反論の声がほとんどない)エネルギー需要側における消費抑制へと押し付けられ、省エネ政策をさらに強化させようとしている。一見(無駄は無くすことが望ましいという普通の感覚に基づけば)、公益にも繋がるとも見える政策強化は、政府に恰好の仕事を与えている。しかしその抑制は必ずしも技術的な効率改善ではなく、究極的には国内生産量の縮小(経済停滞)によって実現されるように、政策は虚構性を多分に含んでいる。
本書は日本の経済成長とエネルギー消費に関する観察事実を構築し、そのメカニズムを解明しようとする試みである。その分析的な特徴は、経済統計とエネルギー統計の融合にある。生産に必要となる資本・労働とエネルギーといったすべてのインプットを考慮し、背後にあるそれぞれの相対価格における変化に基づき、現象は解明されていく。日本の経済成長において実現してきたエネルギー生産性改善はどう理解されるのか、将来に向けて何を注視すべきなのか、賢明なる読者が経済と環境の両立する姿について再考し、そして日本のエネルギー環境政策が地に足を付けて再構築されるための一助となれば幸いである。
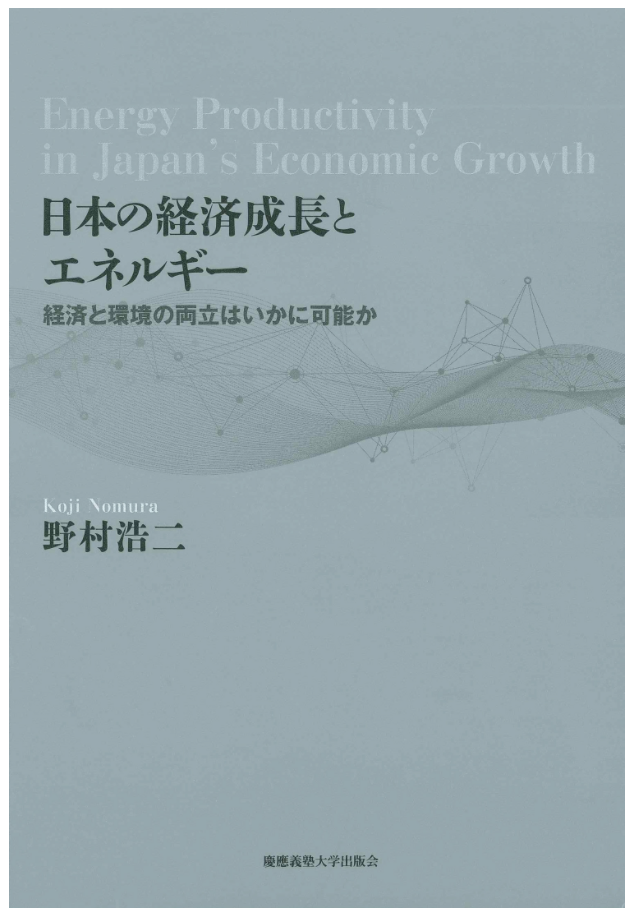 『日本の経済成長とエネルギー』
『日本の経済成長とエネルギー』
本書(慶應義塾大学産業研究所選書)の情報は慶應義塾大学出版会のホームページを参照されたい。
なお本書に含まれる主要図表は、読者による参照の利便性のため同ホームページ内で提供される予定となっている。




















