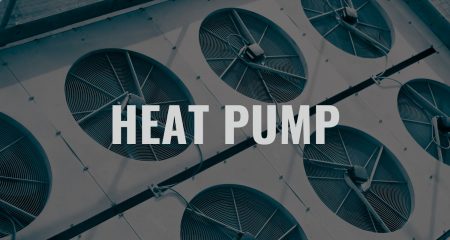「化石燃料へのロックイン」は本当に起きるのか?
杉山 大志
キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹
低炭素社会に移行するためには、CO2を排出するエネルギーインフラに「ロックイン」しないことが必要で、例えば石炭火力発電への投資を直ちに止めて、太陽電池等の再生可能エネルギーへの投資に切り替えるべきである、という考え方がある。さて、この「ロックイン理論」は本当だろうか。
1.ロックイン理論とは何か
ロックインという考え方は、元々は、技術史の文脈で生まれてきた。最も有名な例が、パソコンのキーボードの配列は何故QWERTY(クワーティ、と発音する)という順序になっているか、というものである。QWERTYという配列は、決して打ちやすいものではないと言われ、別の配列も提案されてきた。しかし、いったんQWERTYが普及して標準的なものとなると、違う配列に変えることは難しくなった。
このように、技術は最適な状態からはほど遠いところで、ロックイン(固定化)されてしまうことがある。
以上のことを、複雑系理論の用語を駆使して理屈っぽくいうと、技術はネットワーク外部性があり(つまり多くの人がその技術を使うようになると、今度はその人々が当該技術の継続を促す力を及ぼす)、従って歴史的経路依存性があり(つまりどのような経緯を辿ったかによってどのような技術が採用されるか決まる)、いったん準安定状態になると、他の準安定状態に抜け出すことがなくなる(ブライアン・アーサー2003 収益逓増と経路依存―複雑系の経済学)。
2.温暖化対策における「ロックイン理論」
この「ロックイン理論」を温暖化対策の文脈で用いて、「化石燃料インフラ、なかんずく石炭火力発電への投資をすべきではない」という主張がなされる。このような主張には、2つのパターンがある。
- ①
- 一度石炭火力発電所を建てると、設備寿命である40年以上にわたって発電を続け、その間CO2を出し続ける(例えば、環境省長期低炭素ビジョン 2017 p91)
- ②
- 大規模集中型の電力システムに投資をすると、ネットワーク外部性・経路依存性のためにロックインしてしまうので、再生可能エネルギー等の小規模分散型の電力システムに投資すべきである。そうすると、大規模集中型ではなく、小規模分散型の電力システムで技術進歩やコスト低減等の習熟効果が働き、後者にロックインするので望ましい、というものである(例えば、IPCC2007 p149 Fig 2.1)。
両方とも、理論としては、そのような状況はありうる。だがそれは理論的な可能性の1つに過ぎなくて、本当にそれが現実に当てはまるかについては、個別具体的に考えねばならない。以下では日本の文脈で考えてみよう。
3.石炭火力発電には「柔軟性」がある
上記の①についていえば、設備が一度立てばそれが必ず40年フル稼働を続ける、という想定が間違っている。発電所がどのぐらい稼働するか、その設備利用率は、電力需給全体に依存する。
石油火力発電は1973年の石油ショック時には電力の大半を供給し、フル稼働していた。だが発電システムがそこで「石油にロックイン」したわけでない。石油火力発電は、その後、年間のうち数%の時間しか稼働しなくなり、石油が電力供給に占める割合も数%になった。1973年以降の石油価格の高騰によって、石油火力発電は電力需要のピーク対応に回ったためだ。
石炭火力発電も、どの程度稼働するかは、将来になってみないとわからない。
もしも原子力発電の再稼働が低調で、中東で有事が起きるなどして石油価格・天然ガス価格が高騰して、太陽電池等の再生可能エネルギーも相変わらず頼りにならなければ、石炭火力はフル稼働するだろう。そして電力を安定的かつ安価に供給し、経済活動を支えることができる。CO2は勿論出るがやむを得ない。CO2だけが政策目標ではない。
あるいは逆に、原子力発電が順調に稼働し、石油・天然ガス価格が極めて低く推移し、また太陽電池等の再生可能エネルギーが安価になったとする。エネルギー安全保障上の懸念もなくなり、石炭火力発電に頼らずとも良くなり、CO2削減が優先課題となるならば、石炭火力発電所が、緊急時のバックアップ以外の役割を果たさず、近年の石油火力発電所のように、稼働率が大幅に下がるという状況になるかもしれない。
このどちらの将来も、現時点ではありうる。だから国全体としては、いずれの場合になっても良いように、一定の割合で石炭火力発電設備を持っておくことが適切である。
こうしてみると、「ロックイン理論」に基づいて①のような議論をすることは、不適切なことがわかる。かかる失敗に陥った理由もはっきりしている。それは、設備が一度建つとそこに物理的は存在し続けるという素人目にも分かりやすい「固定化」だけに注目し、稼働率を変えることで異なる政策目標に対応できるという「柔軟性」に対して無知だった為だ。
4.インフラは再定義され、再利用される。
では②の「大規模電力システムへのロックインを避け、再エネに投資すべき」という意見についてはどうか。
歴史的には、実はこれは全く逆である。近年になって太陽光発電が爆発的に増大してきたが、これは、実は大規模な発電・送電のネットワークが存在していたからこそ可能になったのである。太陽光発電は、太陽が出たときにしか発電をしない、出力が不安定なものである。このため、現状としては、大規模な発電・送電のネットワークに接続することで、太陽光発電の電気が余ったら水力発電や火力発電等の他の電源の出力を下げ、逆に電気が足りなければそれらの出力を上げて、停電が起きないように調整してきた。このように、太陽光発電は、既存の電力インフラがあったからこそ大規模に導入することが可能になったのであり、そのおかげでコストも低減してきたのである。
今後についても、太陽光発電等の再エネの導入拡大を支えるためには、その出力の変動を吸収するために、大規模な送電・配電のネットワークも、化石燃料発電も必要なことに変わりは無い。それに代わる有力な技術的回答は今のところ存在しない。
ただし、化石燃料発電の稼働率は変わりうる。そのため単に発電量(KWh)を売るだけでは採算がとれなくなる恐れがある。だが日本の発電システム全体として、設備容量(KW)を一定程度維持することが必要であり、このために容量市場の導入が決定され、政府によって検討されているところである。
1920年代初頭には、米国には馬車があふれていたが、わずか10年間で自動車に殆ど置き換わったという。道路は馬車のためのものだったが、自動車のためのものに再定義され、自動車普及のために大いに再利用された。同じことで、大規模な電力システムは、再エネを取り入れた電力システムとして再定義され、再利用されてきた。決して、大規模な電力システムがあったから太陽電池が導入できなかったというのではなく、その逆であった。もし仮に既存の大規模な電力システムが無かったとすれば、太陽光発電のために送電線を引き、バッテリーを設置しなければならなかった。これでは採算が合うことは難しく、太陽光発電の導入は遅々として進まなかったであろう。
5.おわりに
以上で、日本の電力部門については、ロックイン理論は当て嵌まらないことを見た。だがこれはもちろん、エネルギー分野におけるロックイン理論の適用を全面的に否定するものではない。例えば米国では広大な土地と豊かな資源を背景として自動車社会が出来上がり、電車は使われなくなった。この結果、自動車からのCO2排出は大きくなっており、今後の削減は容易ではない。これはロックインが起きた例である。
一般的に言って、理論は重要であるが、政策的示唆を得るためには、個別具体的な状況における考察が必須である。本稿はその一例であった。














 カーボンニュートラル
カーボンニュートラル
 プラスチックリサイクル
プラスチックリサイクル
 エネルギー基礎講座
エネルギー基礎講座