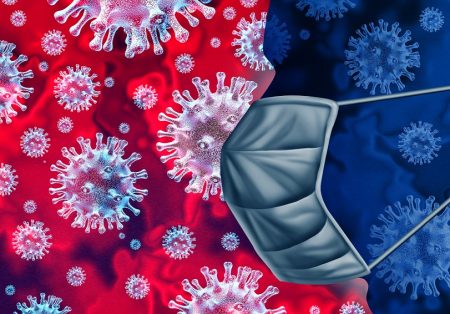“こどもと震災復興” 国際シンポジウム報告2
放射能に関する話題
越智 小枝
相馬中央病院 非常勤医師/東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 講師
(前回は、「“こどもと震災復興” 国際シンポジウム報告1」をご覧ください)
本シンポジウムでは、原発事故を含むトリプル災害の影響を広く議論することを目的としていたが、県外から参加された方の中には放射能と甲状腺の話題だけに興味を持たれていた方も多かったようだ。これに関しては地域と県外の温度差を感じ、地元としては多少残念な感は否めなかった。
放射能に関しての話題は、住民の被ばく線量と甲状腺スクリーニング結果の2点が議論された。前者に関しては坪倉正治医師が相馬市・南相馬の被ばく線量データについての報告を行い、IAEAのピーター・ジョンストン氏が放射線防護の基本的考え方について述べた。後者に関しては、志村浩己医師が甲状腺スクリーニングシステムの設立と実情、インペリアルカレッジ・ロンドンのジェリートマス氏がスクリーニングデータの解釈を述べた。
1.相馬市・南相馬市における被ばく量の経過と教育としての放射線(坪倉正治氏)
震災後、内部・外部被ばく検査は各自治体で継続的に行われている。相馬市・南相馬市ではホールボディーカウンターによる内部被ばく量測定、ガラスバッジによる外部被ばく線量測定が継続的に行われている。
氏は、災害初期から内部被ばく線量を検出する人々が少なかったこと、検出しても、外部被ばくの年間1mSv相当に値するほどの内部被ばくをしている者は殆どいないことを示した。さらに内部被ばく線量の高い人々は、線量の高いとわかっている野生の動植物を定期的に摂取している方であることも述べ、普通に生活を送る際には外部被ばく線量を気を付けるべきであると述べた。その外部被ばく線量に関しても、震災1年後ですら、追加被ばく線量が年間1mSv以上となる住民の方が少なかった。
2016年現在では外部被ばく検査に関して南相馬市で98%以上、相馬市では100%の子供が、年間追加被ばく線量1mSv以下を達成している。さらに内部被ばくも、2016年現在ホールボディーカウンター検査により、放射能汚染は検出される住民はほとんどおらず、特に子どもに対しては汚染食品のコントロールが十分になされ、かつ5年後もそれが維持されていることを報告した。
しかし一方で、坪倉医師が懸念するのは地域住民においても福島県産の食材の忌避傾向や偏見が強く残ることだ。坪倉氏は、5年が経過し、住民の危機意識や興味関心が薄れることで子どもが放射線についての知識を習得する機会が減っていることを懸念する。
「将来子供たちが、この災害についてどのように教えられて育つのでしょうか。」
「子どもが前向きに生活出来るための知識をしっかり持ってもらうための仕組み、特に継続的な放射線教育の充実が重要。」
この5年間の測定結果を未来への遺産としてどのように残すのか、住民が考えなくてはいけないときに来ている、と語った。
2.放射線防護の原則と福島の現状(ジョンストン・ピーター氏)
一方、国際機関であるIAEAは放射線防護の原則から、どのように福島の現状をとらえているのだろうか。
ジョンストン氏は、放射線防護のためには、地域社会を俯瞰して地域のコミュニティ全体を崩さないような対策が取られるべきである、という認識が必須だ、と述べ、特にこどもたちの放射線防護のために子供を地域社会から隔離するような方法を考得るべきではない、と主張した。その上で
- ・
- 常に改善を目指すこと
- ・
- 地域社会にとっての最良の方法を考えること
- ・
- 地域社会自体の開発と並行して行うこと
という適正化の原則を挙げた。
氏は、「子供が大人よりも数倍も放射線の影響を受けやすいのは事実」
としたうえで、世界の一般的な住民の放射線年間被ばく量は1-10mSvであり、福島では子供の最大のリスクは現在の日常生活における外部被ばくではなく、原発事故初期のヨウ素被ばくによる甲状腺がんのリスクであった、と述べる(放射性ヨウ素については後述)。
今後IAEAとしても除染、除染廃棄物処理、汚染マップの作成を援助するが、
「放射線によらない健康被害も含めて地域に有益となるのは、健康調査の継続、推進、および健康相談サポートの推進である」
と述べた。
3.甲状腺スクリーニングの現状と課題(志村浩己氏)
では、ジョンストン氏のいうところの子供の「最大のリスク」についてはどのような結果であったのだろうか。
福島県で2011年10月から2014年3月まで行われた甲状腺がんスクリーニング検査では、震災時0-18歳であった子供のうち367,685名(約80%)が受診した。そのうちBまたはC判定となった2,294名の受診者が二次検査の対象者となった。対象者のうち2,056名が二次検査を完了しているが、約1/3にあたる700名は悪性の可能性は低い、と再判定された。 約2/3にあたる1,356名がB判定相当となり,保険診療に移行したが、そのうち穿刺吸引細胞診が実施されたのは537名。悪性ないし悪性疑いと診断されたものは113例であり、検査時平均年齢17.2歳(8-21歳)、平均腫瘍径14.2 mm (5.1 – 45.0 mm) であったと報告した。そのうち99例が乳頭がん、3例が低分化腺がんであったという。
一方2015年12月までに行われた本格調査の結果で見つかった悪性ないし悪性疑い例は45例、発見時平均年齢は17.2 歳 (10 – 23)、平均腫瘍径は9.9 mm (5.3 – 30.1 mm) 、16例が乳頭がんであった。
このデータを踏まえたうえで、志村医師は「本格調査の甲状腺がんは放射線被ばくの影響か?」という問いに、「現在のところは、No」と答え、
- 1.
- 福島県におけるこどもの被ばく量は50mSvを超えないと推定されている。
- 2.
- 居住地の間で甲状腺がんの発見率に差を認めない。
- 3.
- 震災時にもっとも放射線感受性が高い0-5歳だった小児の間では、これまで甲状腺癌は認めていない。
- 4.
- 基本調査で推定外部被曝線量が5mSv以上だった小児においては甲状腺癌を認めない。
- 5.
- 福島の甲状腺の遺伝子変化はチェルノブイリ原子力発電所事故後の甲状腺癌と異なる。
という理由を挙げた。
そのうえで志村医師は調査の継続の重要性を述べ、
「震災後比較的早期に開始された先行検査や1回目の本格検査の結果は,今後の検査において放射能被曝のリスクを評価する上で,基準となるデータとなる。」
と訴えた。
以前、「原発事故の後に生まれた子供からはがんが見つかっていない」という議論がされたことがある。しかし、現在福島で発見されている子供の甲状腺がんは、最低年齢でも8歳であることを考えれば、「原発事故の後に生まれた子供」と現在のスクリーニング結果を比較できるのは少なくともあと3年が必要ということになるのかもしれない。
4.甲状腺スクリーニングの結果とその解釈(トマス・ジェリー氏)
ではこのスクリーニング結果を、チェルノブイリ原発事故にかかわった疫学者はどのように見ているのだろうか。
トマス氏は、甲状腺がんのスクリーニング方法につき、触診法、エコー検査、死後の解剖による調査の3種類に分け、各々の方法による小児の甲状腺結節の発見率はそれぞれ2-6%、19-35%、8-65%であり、全世界の人口の約6%は甲状腺がんを持っていると推定されている、と述べた。さらに、日本で現在発見されている甲状腺がんの年齢分布はスクリーニング効果によって発見されうる甲状腺がんの年齢分布(他国データ)と類似しており、チェルノブイリで発見された小児甲状腺がんの年齢分布とは全く異なるため、福島で放射能による甲状腺がんが増えている可能性は非常に低い、と主張した。
しかし一方で、トマス氏と志村医師の論説では一点大きく異なる点がある。それは福島の甲状腺がんで見られた遺伝子型に関する解釈だ。先述のとおり、志村医師は、福島で甲状腺がんが増えていないとする一因として、「チェルノブイリ原発の後の甲状腺がんと遺伝子型が異なる」ことを挙げた。ジェリー氏は、甲状腺がんの組織型はもともとのヨウ素摂取量によっても、小児がんと成人がんの間でも異なることを示し、日本とロシアではそもそも甲状腺がんの遺伝子型が異なる可能性がある、と指摘する。
つまりこれは、チェルノブイリと日本でがんの遺伝子型が異なってもそれだけで放射能のせいとはできないかもしれない、ということを意味している。
また、小児の甲状腺がんの予後が非常に良いこと(進行がんでの再発率30%、死亡率1%)を考えれば、
「注意深く経過を見守ることが、即座に手術に進むよりも予後が悪いと言う証拠は存在しない。」
と、手術の選択はこどもの精神的なストレスなども考え慎重に行うべき、という立場を示した。
まとめ
福島第一原発事故後の放射線量の議論は、現在新たな段階に来ていると考えられる。
1つには、地域社会全体への影響を最小限に食い止めつつ線量を可能な限り下げるにはどうすればよいか、という「適正化」を改めて考えること。もう1つは、福島の経験を後世にどのように伝えるべきであるか、真剣に考えることである。
「原発があったから福島は怖いね」でもなく、「原発はあったけど福島は大丈夫だったね」でもなく、原発事故の後、見えない線量と闘ってきた地域の人々が蓄積した知恵を残していくことが重要である。