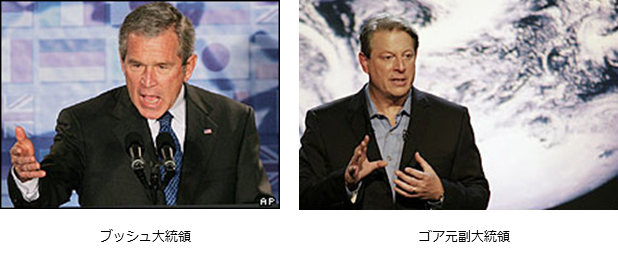私的京都議定書始末記(その5)
-米国の京都議定書離脱と日本の苦悩-
有馬 純
国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授
2001年1月、私は資源エネルギー庁の応接セットで、谷みどり地球環境対策室長の後任に着任したばかりの関総一郎室長と向かい合っていた。関室長は私が資源エネルギー庁国際資源課補佐の頃、企画調査課補佐として机を並べ、気の置けない関係であった。二人の話題は米国のブッシュ新政権の動きである。「米国はそのうち、京都議定書離脱と言いだすのではないか。米国が逃げてしまえば、ゴア副大統領の働きかけに応じて目標数値を水増しした日本は取り残され、馬鹿を見るだけじゃないか」と私が言えば、「それが正に悪夢のシナリオだ」と関室長が答える。二人で「そうならなければ良いが・・・」と思いつつ、ため息をついた。「来るべきものが来る」という予感はあったからだ。
ゴア前副大統領と大接戦の末、2011年1月に大統領に就任したブッシュ大統領は3月、「途上国が不参加であり、米国経済への悪影響が懸念される京都議定書はfatally flawed である」として京都議定書不支持を表明した。予想されたように、この表明は世界の環境関係者から強い批判を浴びた。しかし米国の京都議定書離脱は決して唐突に決定されたものではない。1997年7月、京都議定書交渉に先立って米国上院では「途上国の参加がなく、米国経済に悪影響がある議定書に米国は参加すべきではない」というバード・ヘーゲル決議が95対0で採択されていた。米国が条約を批准するためには上院の3分の2の支持がいる。このため、上院が京都議定書を批准する可能性は皆無であった。その意味でブッシュ政権の対応は、横面を張るような言い方はともかく、ある意味、正直なものであったとも言える。COP6で英国が米国と欧州の調停に奔走した大きな理由は、ブッシュ政権が誕生する前に、米国を取りこんだ合意を作ろうということであったという。しかし、仮にCOP6で京都議定書の細目ルールに合意が成立していたとしても、ブッシュ政権の米国が京都議定書から離脱するシナリオは変わらなかったであろう。事実、8年後に誕生する民主党のオバマ政権も、「温暖化問題に真剣に取り組む」としつつも、京都議定書を拒絶するとの点ではブッシュ政権と何ら変わることはない。ブッシュ政権が特異であると言うよりも、京都議定書交渉におけるゴア代表団こそが異例だったというべきであろう。
ゴア元副大統領は「不都合な真実」を初め、温暖化問題の緊急性を世界に広めたとの点でノーベル平和賞も受け、この世界で重きをなしている人である。しかし彼は京都交渉の際、米国上院が決して批准するはずのない京都議定書成立に大きな役割を果たし、それに署名した。京都議定書誕生の時から米国の離脱は運命づけられていたとも言える。にもかかわらず、京都議定書は、その後10年近くに渡って温暖化防止の国際レジームの「モデル」となり、米国を含む全ての主要国が参加する国際枠組みの議論を様々な意味で制約することとなった。その意味で「ゴア元副大統領の残した負の遺産も大きかった」というのが、温暖化交渉で苦労した私の率直な思いである。
予想されたこととはいえ、当時、世界最大の排出国であった米国のいない国際枠組みは実効性を著しく欠き、しかも日本にとって著しく不公平なものになる。日本政府部内では米国離脱への対応をめぐって早急に対応を検討する必要に迫られた。まず、川口環境大臣を初めとして米国に対して「地球温暖化問題解決には米国の関与が不可欠」との働きかけを行った。また、「米国の参加を得るためには京都議定書の一部見直しも排除すべきではない」との方針も申し合わせた。京都議定書の一部見直しとは、例えばEUに一方的に有利な90年基準、数値目標の設定方法(絶対目標か原単位目標か)、タイムスケジュール、主要途上国の扱い等である。