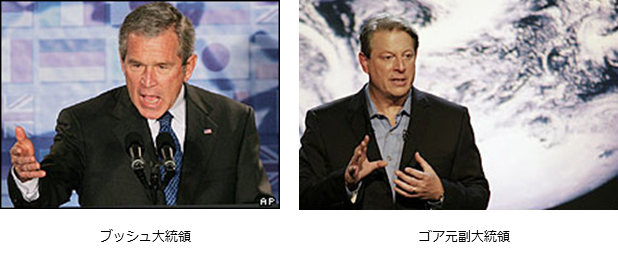私的京都議定書始末記(その5)
-米国の京都議定書離脱と日本の苦悩-
有馬 純
国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授
2001年1月、私は資源エネルギー庁の応接セットで、谷みどり地球環境対策室長の後任に着任したばかりの関総一郎室長と向かい合っていた。関室長は私が資源エネルギー庁国際資源課補佐の頃、企画調査課補佐として机を並べ、気の置けない関係であった。二人の話題は米国のブッシュ新政権の動きである。「米国はそのうち、京都議定書離脱と言いだすのではないか。米国が逃げてしまえば、ゴア副大統領の働きかけに応じて目標数値を水増しした日本は取り残され、馬鹿を見るだけじゃないか」と私が言えば、「それが正に悪夢のシナリオだ」と関室長が答える。二人で「そうならなければ良いが・・・」と思いつつ、ため息をついた。「来るべきものが来る」という予感はあったからだ。
ゴア前副大統領と大接戦の末、2011年1月に大統領に就任したブッシュ大統領は3月、「途上国が不参加であり、米国経済への悪影響が懸念される京都議定書はfatally flawed である」として京都議定書不支持を表明した。予想されたように、この表明は世界の環境関係者から強い批判を浴びた。しかし米国の京都議定書離脱は決して唐突に決定されたものではない。1997年7月、京都議定書交渉に先立って米国上院では「途上国の参加がなく、米国経済に悪影響がある議定書に米国は参加すべきではない」というバード・ヘーゲル決議が95対0で採択されていた。米国が条約を批准するためには上院の3分の2の支持がいる。このため、上院が京都議定書を批准する可能性は皆無であった。その意味でブッシュ政権の対応は、横面を張るような言い方はともかく、ある意味、正直なものであったとも言える。COP6で英国が米国と欧州の調停に奔走した大きな理由は、ブッシュ政権が誕生する前に、米国を取りこんだ合意を作ろうということであったという。しかし、仮にCOP6で京都議定書の細目ルールに合意が成立していたとしても、ブッシュ政権の米国が京都議定書から離脱するシナリオは変わらなかったであろう。事実、8年後に誕生する民主党のオバマ政権も、「温暖化問題に真剣に取り組む」としつつも、京都議定書を拒絶するとの点ではブッシュ政権と何ら変わることはない。ブッシュ政権が特異であると言うよりも、京都議定書交渉におけるゴア代表団こそが異例だったというべきであろう。
ゴア元副大統領は「不都合な真実」を初め、温暖化問題の緊急性を世界に広めたとの点でノーベル平和賞も受け、この世界で重きをなしている人である。しかし彼は京都交渉の際、米国上院が決して批准するはずのない京都議定書成立に大きな役割を果たし、それに署名した。京都議定書誕生の時から米国の離脱は運命づけられていたとも言える。にもかかわらず、京都議定書は、その後10年近くに渡って温暖化防止の国際レジームの「モデル」となり、米国を含む全ての主要国が参加する国際枠組みの議論を様々な意味で制約することとなった。その意味で「ゴア元副大統領の残した負の遺産も大きかった」というのが、温暖化交渉で苦労した私の率直な思いである。
予想されたこととはいえ、当時、世界最大の排出国であった米国のいない国際枠組みは実効性を著しく欠き、しかも日本にとって著しく不公平なものになる。日本政府部内では米国離脱への対応をめぐって早急に対応を検討する必要に迫られた。まず、川口環境大臣を初めとして米国に対して「地球温暖化問題解決には米国の関与が不可欠」との働きかけを行った。また、「米国の参加を得るためには京都議定書の一部見直しも排除すべきではない」との方針も申し合わせた。京都議定書の一部見直しとは、例えばEUに一方的に有利な90年基準、数値目標の設定方法(絶対目標か原単位目標か)、タイムスケジュール、主要途上国の扱い等である。
しかし、「京都で生まれた京都議定書」からの米国の離脱に対し、国内では環境NGOが中心になって「米抜きでも率先批准すべきである」とのキャンペーンを張った。4月半ばには参院で「京都議定書の率先批准」を、衆院で「京都議定書の早期批准」が決議された。私は「米抜き批准」を主張する人々の頭の中を覗いてみたいとの思いにかられた。「日本で生まれた議定書を守れ」という俗耳に入りやすい議論を別にすれば、世界最大の排出国である米国が抜けた枠組みに一体何の実効性があるというのだろうか。後に残されるのは寝転がっても目標を達成できるEUと吸収源とメカニズムに最大限頼らなければ(しかも後者については有料である!)目標を達成できない日本のみである。1年弱の交渉経験ではあるが、温暖化交渉は国益をかけた「武器なき戦い」であるという意識を強めていた時期でもあった。同時に残念ながら戦っていると「後ろから弾が飛んでくる」ことも多かった。
2001年4月には7月に予定されるCOP6再開会合に向けてのブレーンストーミングと、米国離脱の対応策協議を目的として、ニューヨークのウオルドルフ・アストリアホテルで非公式閣僚会合が開催された。また国連本部では川口大臣とプレスコット英副首相等、主要関係者とのバイ会談も行われた。会議では実質的な進展はなかった。米国は京都議定書を拒否する姿勢を繰り返し、多くの国が「京都議定書だけが街で行われているゲームである(Kyoto Protocol is the only game in the town)」という主張を行った。プレスコット副首相との会談では、「京都という家は維持しつつ、皆が住めるようにするために、家具の配置を変えることは有り得るのではないか」との議論があった。この観点でプロンク議長が「京都議定書のコアエレメントは法的拘束力のある取り決めであること、削減目標があること、タイムフレームがあること、途上国について第1約束期間には優遇措置があること、シンク、京都メカニズムには環境十全性が求められることである」と発言したことが注目された。この要素が満たされるのであれば、京都議定書の見直しを完全に排除するものではないと解釈されたからである。ところで、会場となったウオルドルフ・アストリアホテルも国連本部も私にとっては初めて足を踏み入れる場所であった。ウオルドルフ・アストリアホテルの豪華な内装に圧倒され、「北北西に進路をとれ」を初め、数々の映画でとりあげられてきた国連本部の中に入ったことも貴重な経験だった。川口大臣とプレスコット英副首相のバイ会談は国連本部のカフェテリアの一角で行われ、私はメモ取りを担当したのだが、カフェテリアの天井が高く、人の声がわんわん反響して二人の声がよく聞こえず、四苦八苦したことを覚えている。
この頃から日本に対するEUの攻勢が非常に強まってきた。京都議定書は附属書Ⅰ国の排出量の55%を占める国々が批准をしない限り発効しない。最大の排出国である米国が離脱を表明する中で、日本とロシアが批准することが京都議定書の発効にとって不可欠となったからである。まず、「京都議定書が生まれた国」である日本を陥落させようというのがEUの戦略であった。6月半ば、プロンク議長はCOP6再開会合に向けた「統合交渉テキスト」を提示したが、その中で日本向けの特例措置として吸収源3%を認めるという「餌」を投げてきたのもその一環であった。
日本は「米国の参加が不可欠である」との方針の下、「米国と欧州の懸け橋」になろうとの必死の努力を続けていた。プロンク議長の京都議定書の「コアエレメント」発言はあったものの、米国から「京都議定書のこの部分を直すのであれば」という具体的な対案はなく、7月のCOP6再開会合が刻々と迫りつつあった。6月末にハーグで開催された非公式閣僚会合でもプロンク議長の統合交渉テキストをめぐる原則論の応酬が続いていた。夜には川口大臣と朝海地球環境大使、今野経産審議官、浜中地球環境審議官がクアハウスの小部屋で、「米国の復帰が望めない中で、COP6再開会合で合意が成立した場合はどうするのか」というぎりぎりのシナリオを議論していた。今野経産審議官は、私が通産省に入省した時の採用担当者であり、バイ、マルチ何でもござれの国際派であったが、気候変動交渉は初めてであり、「国連交渉はひどいね。ブリンクマンシップが横行しているね」と漏らしていたことを今でも覚えている。

余談であるが、会場となったハーグのクアハウスはスケベニンヘンにあり、小中学生の頃、「スケベニンゲン=助平人間」と覚えていた場所にあり、豪華なリゾートホテルであったが、とても楽しむ気分にはなれなかった。COP13ではバリ島、COP16ではカンクンと、リゾート地で会合が開催されるケースがあるが、一般の観光客がくつろいでいるのを尻目に交渉に奔走するのは精神衛生上よろしいものではない。
米国の態度が変わらない中で、「米抜き率先批准」を主張する声が国内でも高まってきた。特に7月末の参院選を控え、京都議定書率先批准を政治アジェンダとする動きも強まってきた。党首討論で鳩山民主党代表が小泉首相に対して「政府は京都議定書を批准するんですか、しないんですか」と声高に迫る姿をテレビで見て、「国益をかけた国際交渉を政争の具にしてほしくない」と思ったものだ。戦前、ロンドン軍縮条約を進める与党民政党を攻撃するため、野党政友会が統帥権干犯を持ちだし、結局、国を滅ぼす一因を作った。コンテクストは違いながらも、条約交渉の政治利用という文脈で、そんな故事をぼんやり思い出していた。米国と欧州の間に挟まれ、日本が厳しい選択を迫られるCOP6再開会合はもうすぐそこであった。