執筆者:杉山 大志
-
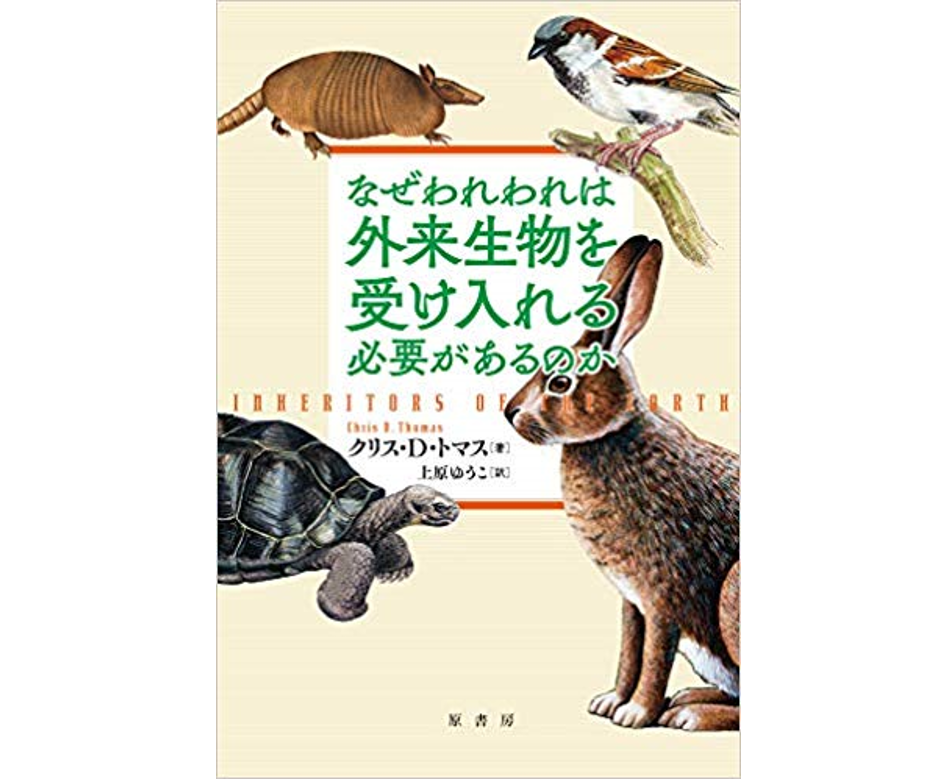 2019/05/29
2019/05/29地球温暖化は生物多様性を増す
書評:クリス・D・トマス 著、上原 ゆうこ 訳『なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか』 -
 2019/05/23
2019/05/23温暖化対策長期戦略とSociety5.0の思想
現代的環境主義宣言――技術こそが地球環境問題を解決する -
 2019/05/20
2019/05/20「脱石炭」は世界の趨勢か? 日本の進む道なのか?
-
 2019/05/15
2019/05/15政府報告書「日本の気候変動とその影響」の問題点
-
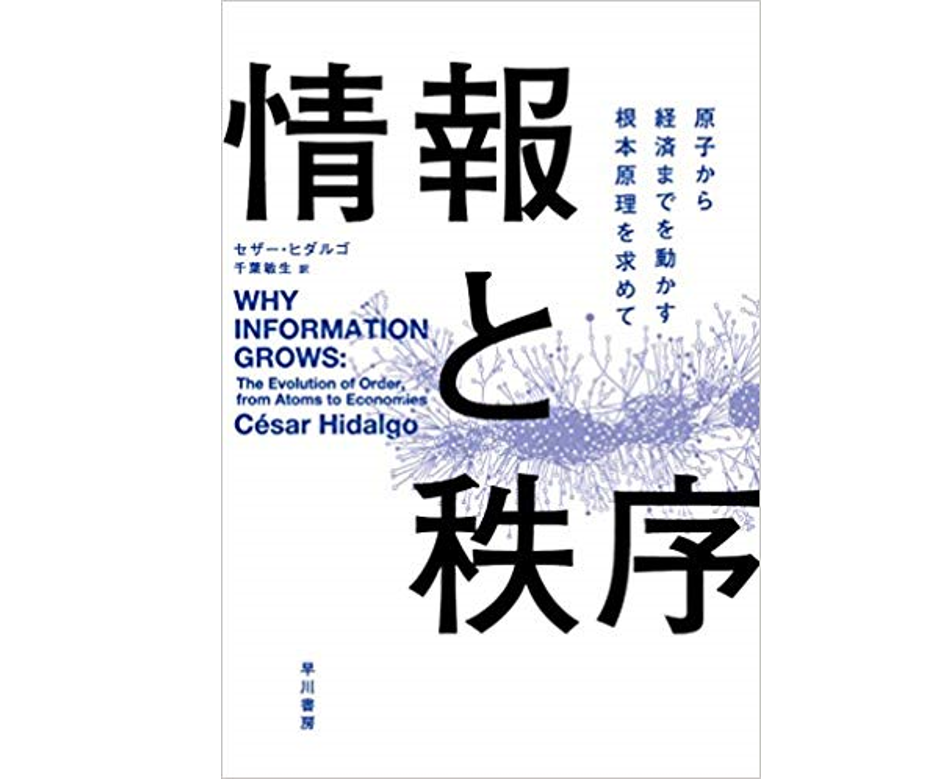 2019/02/14
2019/02/14複雑系理論で経済成長を解明
書評:セザー・ヒダルゴ 著、千葉 敏生 訳『情報と秩序:原子から経済までを動かす根本原理を求めて』 -
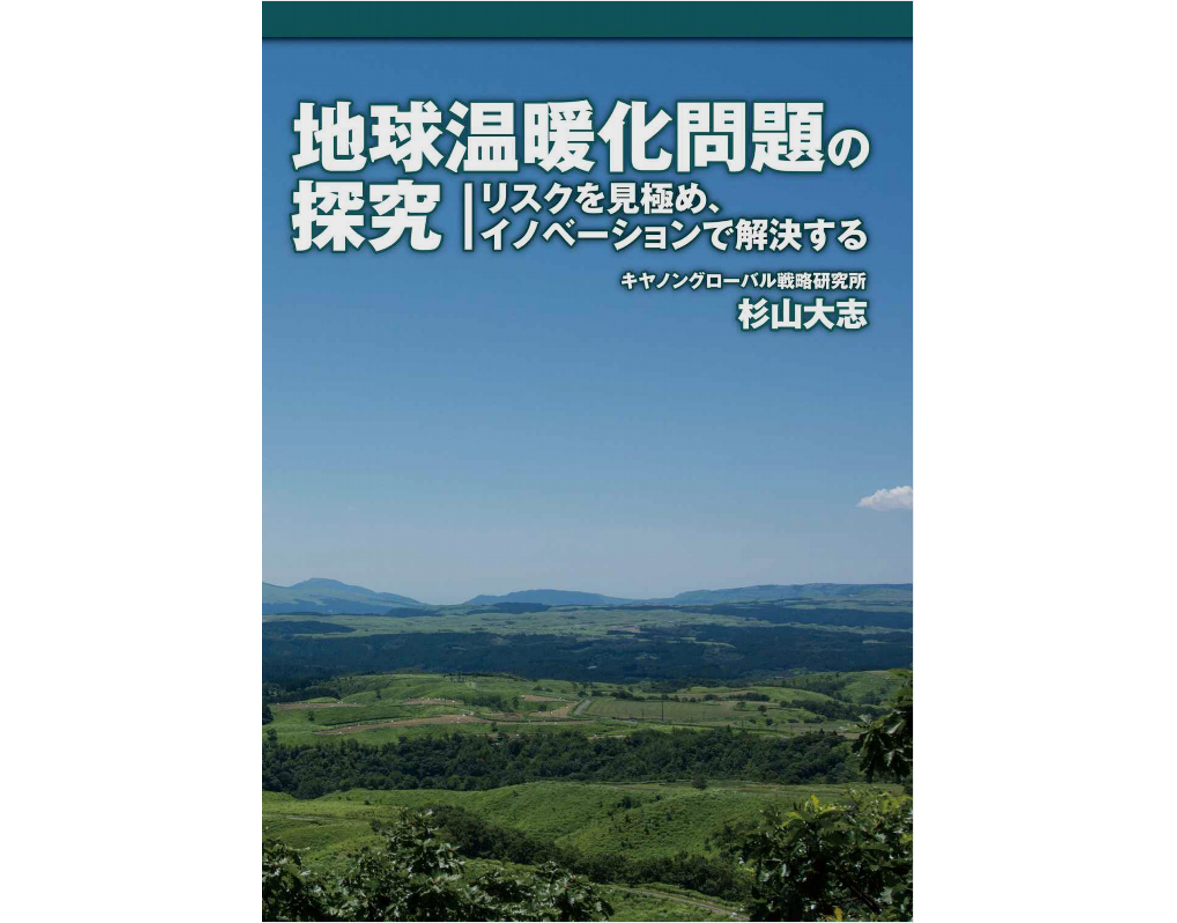 2019/01/31
2019/01/31地球温暖化問題の探究:リスクを見極め、イノベーションで解決する
-
 2019/01/25
2019/01/25ノーベル賞を獲得したノードハウスのDICEモデル
地球温暖化の被害はCO2削減の費用を正当化するか? -
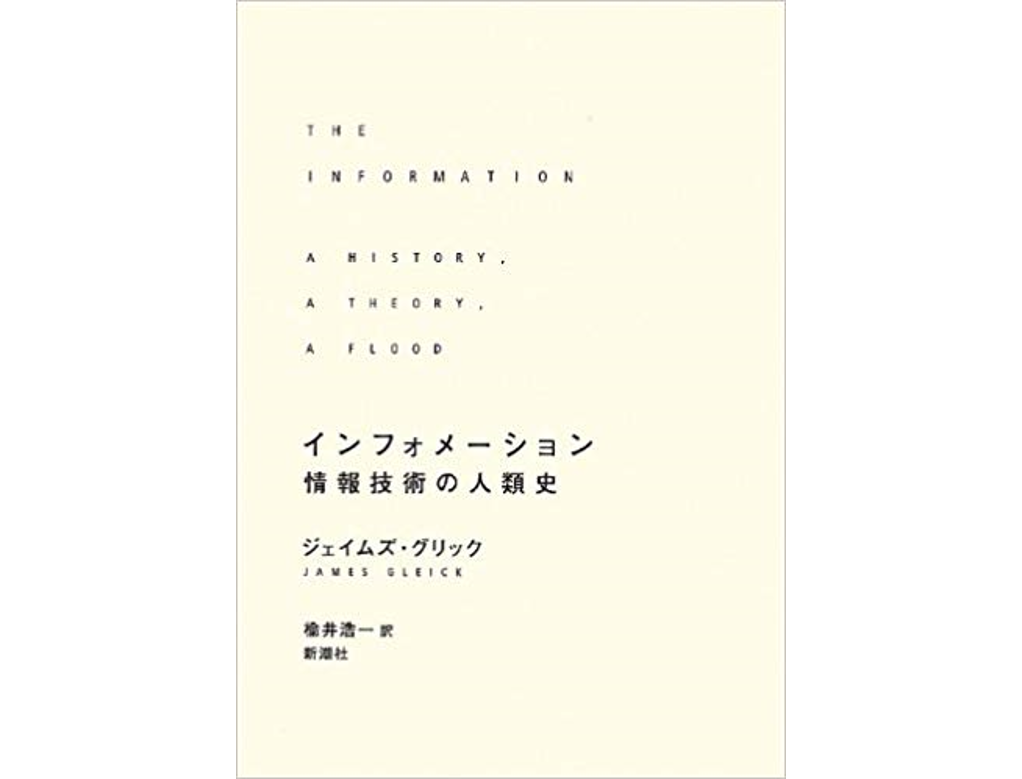 2019/01/08
2019/01/08情報技術とイノベーションの歴史に学ぶ
書評:ジェイムズ・グリック 著、楡井浩一 訳『インフォメーション-情報技術の人類史』 -
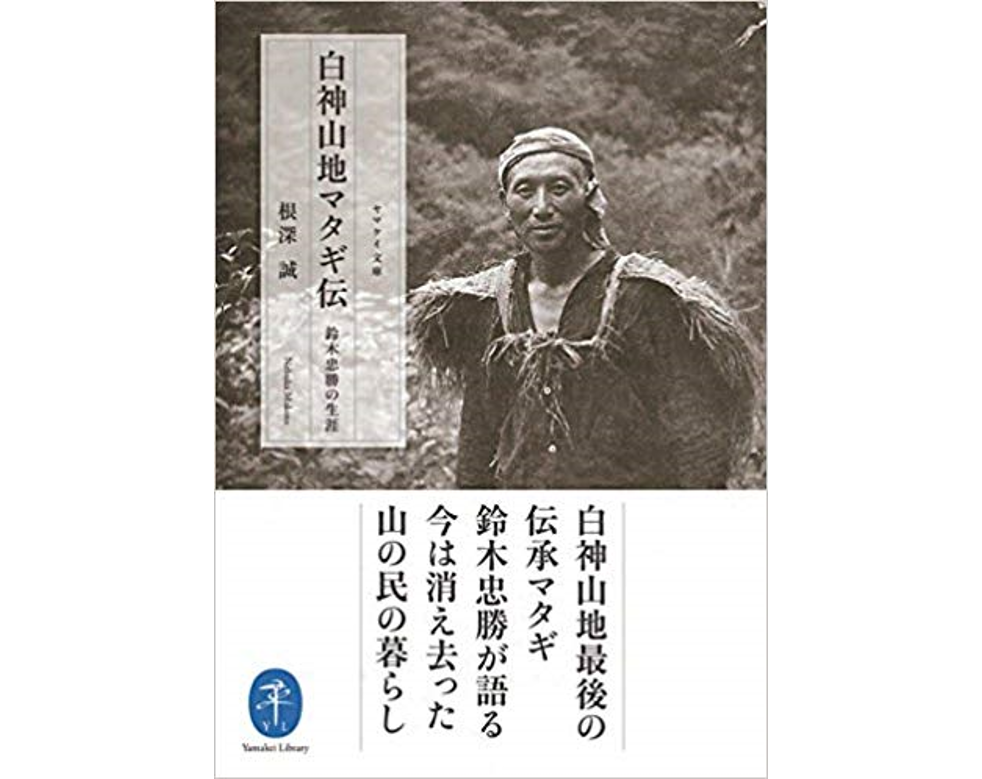 2018/11/02
2018/11/02失った山の民の暮らしと歴史
書評:根深 誠 著『白神山地マタギ伝: 鈴木忠勝の生涯』 -
 2018/10/24
2018/10/24発電所がモッタイナイ
-
 2018/10/09
2018/10/09IPCC1.5度特別報告書の解説(速報版)
-
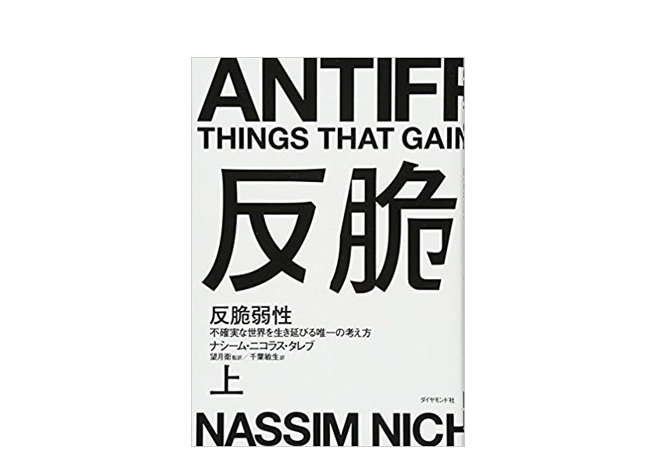 2018/09/21
2018/09/21生きもののしたたかさの秘密に迫る
書評:ナシーム・ニコラス・タレブ著『反脆弱性[上][下]――不確実な世界を生き延びる唯一の考え方』 -
 2018/09/06
2018/09/06猛暑・豪雨の地球温暖化との関係のホントとウソ
-
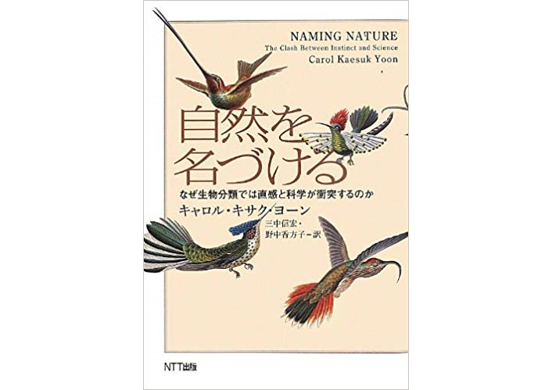 2018/08/29
2018/08/29外見か、遺伝子か 分類学を翻弄
書評:キャロル・キサク・ヨーン著『自然を名づける―なぜ生物分類では直感と科学が衝突するのか』 -
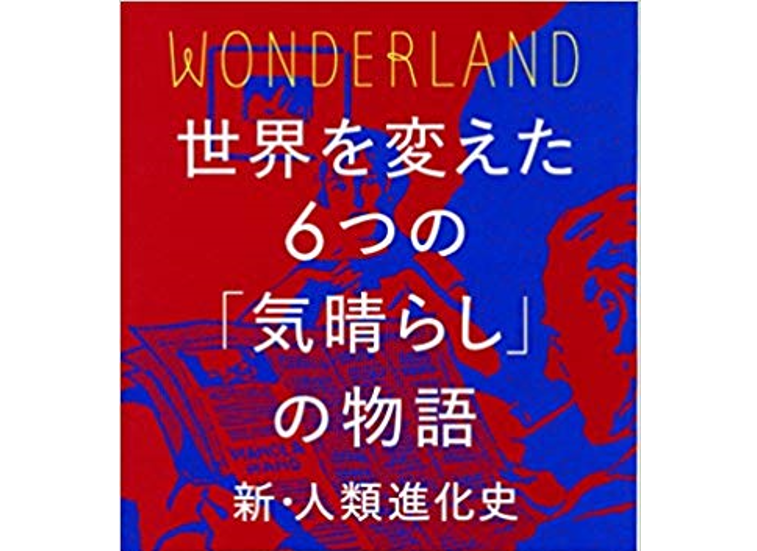 2018/07/27
2018/07/27遊びこそ未来を創る革新の親
書評:スティーブン・ジョンソン著『世界を変えた6つの「気晴らし」の物語【新・人類進化史】』 -
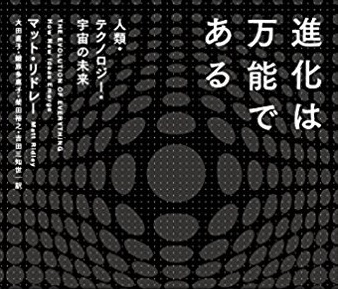 2018/05/01
2018/05/01万物に共通する発展の歴史
書評:マット・リドレー 著「進化は万能である:人類・テクノロジー・宇宙の未来 」 -
 2018/04/24
2018/04/24地球温暖化への適応をきっかけとした島嶼国との国際関係の強化について
-
 2018/04/19
2018/04/19化石燃料の環境便益
-
 2018/04/13
2018/04/13CO2による地球緑色化(グローバル・グリーニング)
-
 2018/04/09
2018/04/09中世は今ぐらい熱かった:IPCCの最新の知見












