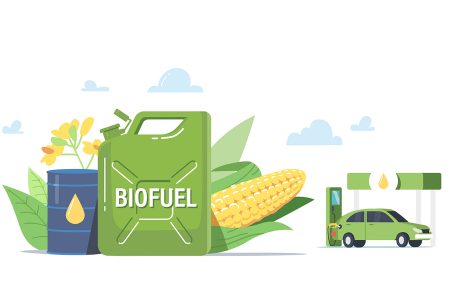食品に含まれるPFASのリスクはどれくらいか
小島 正美
科学ジャーナリスト/メディアチェック集団「食品安全情報ネットワーク」共同代表
◎食品から摂取するPFASのリスクはどれくらいか。メディアはもっと規制の裏側に隠された根拠を報じてほしい。
有機フッ素化合物のPFAS(ピーファス)の健康リスクはいったい、どれくらいなのだろうか。食品中に含まれるPFASの含有量を調べた農林水産省の最新調査で、ヒトへの健康影響のおおよその大きさが分かってきた。その一方、PFASをめぐっては、どの研究論文を重視するかで政策のあり方が異なるという問題もあったが、この問題を考えるうえでとても有益な新著「世界は基準値でできている」(講談社)も紹介したい。
すでに製造・輸入は禁止
PFASは、炭素とフッ素が結合した有機フッ素化合物の総称で1万種類以上ある。その代表的な物質が世界中で話題となっているPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)だ。水や油をはじき、熱や化学薬品に強い性質を持つことから、焦げ付きにくいフライパンや防水加工された衣類、食品の油をはじく包装紙、泡消火剤など、私たちの生活で幅広く使われている。分解しにくく、生物の体内に蓄積しやすいことから、国際的な規制が進み、PFOSは2010年、PFOAは2021年に国内での製造・輸入が原則禁止されている。
健康影響の指標は「耐容一日摂取量」(TDI)
これらの物質は食品にも含まれるが、いったいどの程度のリスクがあるのだろうか。人への健康影響は、それらの物質を人が生涯にわたって取り続けても健康影響のない指標とされる「耐容一日摂取量」(TDI)で判断する。TDI(Tolerable Daily Intake)は、意図的に使う食品添加物や農薬と異なり、意図的に使用されずに食品中に含まれる化学物質のリスクを考えるときに適用される考え方だ。このTDIの考え方はコメや魚などに含まれる水銀やカドミウムなどの重金属にも適用される。
つまり、食品中に含まれるPFAS(ここではPFOSとPFOA)のリスクがどれくらい大きいかは、私たちが食事から体内に取り入れているPFASの摂取量が「耐容一日摂取量」を下まわっているかどうかで判断する。PFOSとPFOAの「耐容一日摂取量」は、化学物質のリスク評価を行う内閣府食品安全委員会が動物実験などで影響のなかった量から設定し、それぞれ体重1kgあたり1日20ng(nはナノと読み、10億分の1の単位)となっている。この1日あたり20ngの耐容量を、体重が50kgの成人にあてはめると、PFASの摂取量は1日あたり1000ng(20ng×50)に相当する。つまり、成人ならば、1日あたり1000ng以下に収まっていれば、健康への影響はないと判断できる。
PFASは野菜や米、肉類では低く、魚で高い傾向
では、食品中に含まれるPFASはどれくらいだろうか。農林水産省は8月下旬、玄米、ジャガイモ、キャベツ、トマト、牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳、鶏卵、マイワシ、マダラ、カツオ、アユ、アサリの14品目を対象にPFOSとPFOAの含有濃度を調べた結果を公表した。
まずは、PFOSを見てみよう。同じ品目でも濃度に差があるものの、中央値を見ると玄米(1kgあたり5ng)や野菜、肉類では低かった。これに対し、マイワシ(同130ng)、カツオ(同350ng)、アユ(同760ng)など魚では高い数値が見られた。しかし、それら14品目を平均的に摂取した場合のPFOSの平均摂取量は体重1kgあたり0.1ngとなり、TDIの200分の1(0.1÷20=200分の1=0.5%)と分かった。
このTDIは、生涯にわたって取り続けても健康影響のない目安なので、その目安の200分の1ということは、健康へのリスクは無視できるということだ。
最大値の食品を摂取してもTDI以下
このTDIの0.5%は、平均的な含有濃度を想定したケースだ。では、14品目のすべてで最大の含有量(たとえば、アユは1kgあたり76000ng、マイワシは同1800ng)を摂取したと仮定した場合はどうなるのだろうか。その場合でも、PFOSの体内摂取量は体重1kgあたり1日1.5ngとなり、TDIの7.5%(TDIの約13分の1)である。マイワシやアユを毎日食べ続けることはありえないが、たとえ最大含有量を食べたとしても、健康への影響は極めて低いことが分かる。
では、PFOAはどうか。PFOSと同様の傾向が見られ、玄米や野菜、肉類では低いが、アユ(最大で同2900ng)やアサリ(同9000ng)で高い。しかし、14品目から摂取するPFOAの平均摂取量はTDIの0.4%と十分に低く、PFOSと同様に最大含有量を食べたと想定した場合でも、TDIの2.6%だ。PFOSとPFOAのいずれの場合も、TDIを大幅に下回ることが分かる。
これら14品目は食品全体の約3割に相当する。アユやアサリなど特異的に高い魚介類があるため、今後もさらなる監視は必要だが、少なくとも食品中のPFOSとPFOAの健康リスクが高いとはいえず、ニュースで大騒ぎするほどのリスクではないことが分かるだろう。
これら14品目の詳しい数字は農林水産省の「令和6年度農畜水産物のPFAS含有実態調査結果」(250828-2.pdf)や食品安全委員会の「有機フッ素化合物(PFAS)」評価書に関するQ&A | 食品安全委員会 – 食の安全、を科学する」を参照してほしい。
国によって規制値が異なるのが現状
とはいえ、PFASに関しては、どういう研究論文を根拠に健康影響があるかどうかを判断する段階で論争が存在するのも事実だ。日本の食品安全委員会は「耐容1日摂取量」(TDI)を体重1kgあたり1日20ngと設定したが、海外ではそれよりも厳しい(低い)数値を設定している国もある。
国によって、なぜ規制のあり方が異なるかを考えるうえでとても参考になる本が「世界は基準値でできている 未知のリスクにどう向き合うか」(講談社ブルーバックス)だ。永井孝志氏(農研機構上級研究員)ら4人の専門家が新型コロナの基準値(距離や時間、空気感染)、原子力発電所の基準値、新しい「食」(コウロギ)の基準値、がん検診の基準値など11の基準値について、その根拠となる考え方を分かりやすく解説している。
この本の9章では「PFSAの基準値」について、村上道夫氏(大阪大学感染症総合教育研究拠点教授)が詳しく解説している。
PFASについては動物実験や疫学調査で「血中コレステロール値の増加」「出生時の体重低下」「腎臓がんや精巣がんとの関連」「子供のワクチン抗体応答(ジフテリア)の低下」などを指摘する研究文献があるが、どの文献をリスク評価に用いるかは国の評価機関によって異なる。日本の食品安全委員会は「ラットの実験による子ども体重の減少やマウスによる骨化部位の減少(エンドポイント)は科学的に納得できる」として採用したが、他の文献はリスク評価に採用するには一貫性がなく、信頼性に欠けると判断した。
「ワクチン抗体価」は適切な指標なのか?
このあたりの判断は、今年の第173回芥川賞と直木賞に「該当作なし」と判断されたのと似ている部分がある。多数の選考委員が一致して「この小説は賞に値する」と推した作品がなかったということだ。研究文献も同じだ。どの国の評価機関も文句なく一致して推す研究文献ばかりならよいが、いうまでもなく研究の質にはバラツキがあり、リスク評価に堪える文献は少ないのが現状である。
たとえば、米国は、デンマークのフェロー諸島の子供たちを対象にした疫学調査による「ワクチン抗体価(ジフテリア)の減少」を重視したが、同本は「PFOSとPFOAの濃度とワクチン抗体価に因果関係があるかは十分に証明されていない。フェロー諸島の人々には鯨食の文化があり、食物連鎖の頂点に立つさまざまな化学物質が高濃度に蓄積されたクジラによって、他の化学物質の血中濃度も高かった可能性がある」と述べ、抗体価が低下した原因は別の化学物質かもしれないと指摘している。
また、さらに「そもそも基準値の設定でワクチン抗体価を根拠とすることは異例だ。コロナ禍の中ではワクチン抗体価は私たちが守りたい健康のひとつかもしれないが、現在は死亡事例がない抗ジフテリア抗体価を使うことの妥当性は不明だ。感染症の免疫反応という複雑なプロセスを、ワクチン抗体価という単純なひとつの指標だけでとらえられるのか」などと述べ、ワクチン抗体価をリスク評価に用いるにはそれ相当の根拠が必要だと指摘する。
PFASに関する食品安全委員会のプレスリリースにはこういう分かりやすく的確な解説を載せるべきだろう。
大手メディアはこうした規制値の裏側に隠された科学的な解釈をなかなか報じてくれない。メディアの記者ならせめて、この本を読んだうえでPFASなどの規制のあり方を論じてほしいものだ。