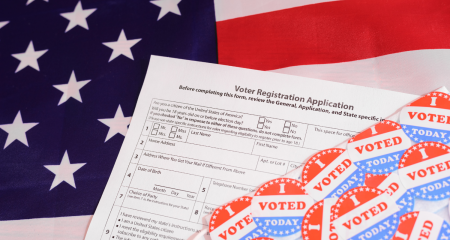米国トランプ政権の政策と事業者への影響
2009 Endangerment Finding(GHG規制の法的根拠)の撤回
西村 郁夫
一般社団法人 海外電力調査会 調査第一部長
はじめに
トランプ政権二期目が発足してから半年余り、各国および産業界が対応に苦慮している関税措置に加えて、内政においては、クリーンエネルギー、EVなどへのインセンティブの大幅縮小と特定分野の規制緩和・許認可プロセスの加速を含む財政調整法が成立した他、独立規制機関への政治的影響力の行使、政権の意向に沿わない規制の改変(環境アセスメント・プロセスなどを含む)、州の立法権への介入など、既存システムの改変が矢継ぎ早に進められている。この結果が創造的破壊(Creative Destruction)であったのかどうかは、後年の評価に委ねるとして、現状に対して、一部の州からは既に反発・提訴が生じている他、事業者の視点からは、これまで機能するかたちに組み上げられてきたシステムへの影響、プロジェクト実施に際して予見性の低下が少なからず懸念される。
このような中、2025年7月29日、米国環境保護庁(EPA)は、大気浄化法のもとでの温室効果ガス(GHG)規制の法的根拠とされてきた「Endangerment Finding(2009年当時のEPAによるGHGが公衆の健康および福祉を危険にさらしているという科学認定)」の撤回提案を行った。一部の産業分野において、これに基づく規制などに立脚して進められてきた気候変動対策の合理性に影響する他、民主党が優勢で気候変動対策において先進的とされる州との板挟み、投資家対応に対して懸念が生じはじめていると聞く。
大統領就任初日の「国家エネルギー緊急事態宣言に関する大統領令」での「大気浄化法第202条(a)に基づくGHGの危険性と原因、または寄与の調査結果に立脚した最終規則の合法性および継続的な適用可能性の再評価」の結果ではあるが、結論までの期間の短さもさることながら、改変の影響レベルの大きさに比べて連邦官報にて公示後45日間という極端に短いパブコメ期間は関係者の驚きを呼ぶとともに、訴訟になることを想定して、D.C.巡回区控訴裁、最高裁までの結審がトランプ大統領の任期内に収まることを念頭に置いたスケジュール感なのではないかとの憶測を呼んでいる。
2009年Endangerment Finding
2007年の「Massachusetts v. EPA判決」において、連邦最高裁は、「CO2を含むGHGは大気浄化法に規定する大気汚染物質の広義の定義に該当する」との判決を下した。これを受けて、2009年12月、オバマ政権下のEPAが「GHGの排出が国民の健康と福祉を脅かす」との危険性を認定したものが、今次論点となっているEndangerment Finding(以下、危険性認定)である。その後、EPAはGHGの大規模排出施設に対し、排出を最小限に抑制するため、大気浄化法の新規排出源審査(New Source Review)における重大な環境悪化防止(Prevention of Significant Deterioration)に基づく許認可を求める規則を制定、これが当初目的であった自動車に加えて、火力発電所をはじめとする固定排出源、石油・天然ガス産業からのメタン排出規制につながっている。
2009年危険性認定の再評価および自動車排出基準の見直し提案
今次公表された「2009年危険性認定の再評価およびGHG排出に関わる自動車基準の見直し」と題された文書の中で、EPAは危険性認定の撤回提案について以下の様な整理を行っている。
- 1.
- 大気浄化法第202条(a)の最適な解釈
大気浄化法第202条(a)および関連規定の文言、構造および2009年以前の同法の長きにわたる実施は、同規定が、地域的または局地的な曝露を通じて公衆の健康または福祉を脅かす大気汚染物質を特定し規制する権限をEPAに付与するものとして解釈することを示しており、地球規模の気候変動に関する懸念を引き起こす6つの混合されたGHGは、この基準を満たさない。
- 2.
- 議会による明確な受権の欠如
2024年の「Loper Bright Enterprises v. Raimondoケース」での連邦最高裁判決は、所轄の行政庁が法律に触れられていないこと、或いはその曖昧さに依拠して、法律で明示的に付与されていない権限や裁量権を推認することはできなくなったことを示している。大気浄化法第202条(a)で求められる判断を行う際、EPA長官は、同法の文言に可能な限り忠実に従い、過去の実施例、および2008年にGHGの影響および規制に関する分析と政策オプションについての意見募集を目的に公示された「大気浄化法の下でのGHG排出規制に関する事前通知」に示された初期のアプローチに準拠するべきである。
因みに上記通知において、(ジョージ・W・ブッシュ政権下)当時のEPA長官は、「大気浄化法に基づき自動車からのGHG排出を規制する場合、同法第202条(a)と関連規定との相互作用により、経済のほぼ全ての分野に深刻な影響を及ぼし、全国の全ての世帯に影響を与える前例のない規制権限の拡大を招く可能性がある」と指摘し、更に「大気浄化法という地域的な健康影響を引き起こす汚染物質の規制を目的として制定された古い法律が地球規模でのGHGの規制という任務に適しておらず、この方針を追求することは、必然的に非常に複雑で時間がかかり、恐らく混乱を招くような規制体系をもたらすものとなる。GHG濃度を低減する効果は、雇用や米国経済に与える潜在的な損害を考慮すると、相対的に低いものとなる」と警告している。
このように今次のEPAの提案は、科学的根拠に基づいて判断を撤回するという単純なロジックではなく、大気浄化法第202条(a)で用いられる大気汚染という用語が、文脈上、危険な大気汚染への地域的または局地的な曝露を指すものと解釈するのが適切であること、議会が同第202条(a)および関連規定に基づき規制するよう指示した汚染物質全てが地域レベルでの影響のため懸念されることを示しつつ、「大気浄化法の法解釈」と近年の連邦最高裁判決において改めて示された「議会による明確な受権」に重心を置いた説明となっていることに留意が必要である。恐らく多くの関係者にとって想定外であったと共に、今後おこり得る裁判においても覆しにくいある意味良く考えられた法的論拠に基づくものとなっている。更に現行の連邦最高裁が保守系6名対リベラル系3名と保守系色が強いことも、今後のプロセスを想定する上で考慮しておくべきことと映る。
産業界のリアクションと事業者への影響
運送業を代表し、EVトラックマンデートと称される大型車両のGHG排出基準 – フェーズ3に強く反対する米国トラック協会は、今次提案を歓迎することを表明しているが、主要な産業セクターは、必ずしも危険性認定の廃止や撤回を強く求めておらず、政権の勢いに比べて温度差が見られる。電気事業者の業界団体からは、今次提案については精査中としつつ、エネルギー・インフラ投資を促進し、米国の経済・エネルギー安全保障を強化する明確で一貫性のある規制政策をEPAが確立することを支持する旨、コメントされたことが報じられている他、自動車業界を代表する業界団体や、一部の自動車メーカーからは、持続可能で合理的な基準を望むとの発言があると聞く。規制緩和を求めてきた米国石油協会は、今次提案に賛意を表明する一方で、排出削減に貢献しつつ、消費者に信頼性高く、手ごろな価格の交通手段を確保する政策の策定に協力していきたいとの姿勢を示している。
これらの背景には、GHGの排出者に対して気候変動を起因とした経済的損失への補償を求める地域レベルでの訴訟、ニューヨーク、バーモントなど複数の州で立法の動きが見られる気候変動特別基金法(Climate Superfund Law)に対する抑止力の喪失懸念があると言われる。大気浄化法のもとで、EPAがGHGを規制する権限を有し、適正に規制を行うことで、これがその他の連邦法、州法に優先され、また、個々のGHG排出者が地球規模での気候変動に対して責任を訴求されないというのが、上記の様な訴訟、州レベルでの規制に対する反論の論拠とされてきた。
おわりに
今次の危険性認定の撤回提案は、「大気浄化法の法解釈」と「議会による明確な受権」を主な論拠としており、最終的に連邦最高裁まで判決がもつれ込んだとして覆しにくいものになると考えられる。一方で、これによって、米国で環境規制だけでなく、燃料輸送コストの負担も足かせとなって経済性を失った石炭火力が新増設に向かう様な方針転換やクリーンエネルギーへの投資の停止など、時計が逆回転をはじめるわけではない。上述のとおり、米国の主要産業セクターも困惑しているというのが正直なところと推察する。このような中、我が国の産業界としては、しっかりとエネルギー安全保障に加えて、エネルギー移行の中での国際競争力の維持を念頭に、未来に向けて現実的な対応を着実に進めていくことが求められている。