「エネルギー政策」前史:石油が国家を作るとき
向山 直佑
Associate Professor / 准教授
Institute for Future Initiatives
The University of Tokyo(東京大学 未来ビジョン研究センター)
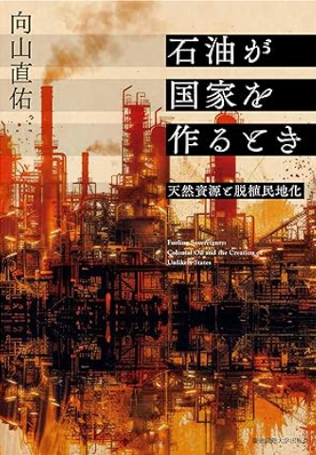
タイトル:石油が国家を作るとき -天然資源と脱植民地化
著者:向山 直祐
出版社:慶應義塾大学出版会
定価:4620円(税込み)
初版年月日:2025年1月30日
ISBN:978-4-7664-3004-2
例えば日本企業がマレーシアでガス田の開発に参入するとか、アラブ首長国連邦(UAE)の国営石油会社のトップが来日したといったニュースを目にした際、私たちはマレーシアやUAEといった国家が存在し、そうした主権国家を単位として政治が行われていることを当然のこととして受け入れている。ある国の政策を論じるためにはその国が存在していなければならないのだから、当たり前のことである。そのとき、私たちは「マレーシア/UAEという国が先にあって、そこに石油が出る」という前提を無意識に置いている。
しかし歴史をひもとけば、これが実は不正確な認識であることがわかる。なぜなら、実際には「石油が出る地域に、マレーシア/UAEが後から誕生した」というのが正しいからである。先に国家があってそこに石油が出たのではなく、石油が出るところに後から国家ができたのだ。もちろん、すべての場所でこうした順序だったというわけではなく、むしろ世界的に見れば石油が国家に先行する事例は例外的である。アメリカでも、ノルウェーでも、国家の誕生は石油生産に先行している。だが、特に植民地支配からの独立によって誕生した比較的若い国家の中には、主権国家の誕生に先駆けて石油生産が始まっていた事例がままある。石油生産が行われる地域に後から国家を作ろうとするとき、そこでは何が起きるのだろうか?今年1月に上梓した拙著『石油が国家を作るとき』(慶應義塾大学出版会)では、この疑問に回答している。
まず前提として、かつて世界のほとんどを植民地支配下に置いていたイギリスをはじめとする旧宗主国は、植民地の独立を考えるにあたって、各地に存在した小さな植民地を、友好的な指導者の下にできるだけ合併させてから独立させようとした。それは、極小国を作ってしまうことで、周辺国からの侵略を受けて国際情勢が不安定化したり、社会主義陣営の影響下に取り込まれたりしてしまうことを危惧したからだった。西側に友好的な指導者を支援し、周辺の小規模植民地も合わせて1つの(多くの場合は連邦)国家として独立させる、というのが第二次大戦後数十年間のイギリスの脱植民地化の「王道」のようになっていたのである。
しかし、当の小規模植民地の側からすれば、これは一方ではありがたく、他方では迷惑な提案であった。というのも、より大規模な国家の一部になることは、市場の拡大や公共サービスの提供という意味ではメリットが大きく、安全保障上もより安定するのだが、同時に意思決定において自律性が失われるというデメリットもあるわけである。つまり、自分たちに関わる政策を決めたくとも自由には決められない。なぜならば、必ずしも利害を共有しない他地域も含めた国全体の政策に縛られるからだ。
この自律性の意味で最も合併を受け入れがたく感じたのが、産油地域であった。石油が出ることで周辺地域よりもはるかに豊かになった産油地域だが、合併してしまえば、その収入が中央に吸い取られ、他地域に分配されてしまう。取り分が少なくなるわけである。例えば東南アジアのブルネイ、中東のカタールやバーレーンがこうした事例にあたる。ブルネイは1963年に設立されることになるマレーシア、カタールとバーレーンは1971年に設立されるUAEの一部となることが当然視されていた。しかしマレーシアやUAEを構成する他地域(アブダビを例外として)よりも圧倒的に豊かなこれらの地域にとって、これまでの豊かさを投げ出さなければならないというのは、到底容認できない問題だった。
こうした合併への不満の原因となった石油は、逆に単独での独立への道を拓く鍵ともなった。つまり、石油が出ることで、その収入によって産油地域は単独でも国家として生きていけることになり、また石油の供給を重視する宗主国やその他の西側諸国の庇護を受けることができ、安全保障上の課題も解決される。ただ、石油だけでは独立は保障されない。単に石油が出るだけの地域ならば、植民地時代に宗主国が都合よく搾取できる体制を整えられたはずだし、脱植民地化の局面においても合併を受け入れるように誘導しあるいは強いることもできるはずである。実際に例えばオランダ領ボルネオ、クルディスタンといった地域は、植民地時代に石油が出ていたにもかかわらず、合併されてしまった。
そこで小規模植民地が単独で独立するために必要なもう1つの条件が、私が「保護領制度」と呼ぶ、現地の支配者を維持し、宗主国がそれに保護を与える間接的な統治体制であった。ブルネイ・カタール・バーレーンはいずれも、宗主国であるイギリスが直接統治を敷く植民地ではなく、現地のスルタンや首長が(イギリスの庇護下で)伝統的な統治を続ける保護領であった。なぜこの要素が重要かというと、こうした保護領においては、イギリスとの取り決めによって、独立に関わる最終的な意思決定権が、イギリスではなく現地支配者の側にあったからである。合併してしまえば、石油収入が失われるだけでなく、支配者自身も「自領内の絶対君主」から「数ある支配者のうちの1人」に落ちぶれてしまうため、それを阻止するインセンティブが働いた。結果として現地支配者は合併に反対し、イギリスも彼らに無理強いすることはできなかったのだ。植民地からの独立を果たした今で言う「グローバル・サウス」の国々は、イギリスをはじめとする旧宗主国に対して厳しい視線を向けており、旧植民地への影響力を行使しようとするような行動は「新植民地主義」として厳しく糾弾された。そのため、例えばイギリスがブルネイを無理やりマレーシアに入れようとすれば、激しい非難が浴びせかけられることが予想され、イギリスも強くは出られなかったのである。こうしてブルネイ・カタール・バーレーンのような「本来なかったはずの」極小国が誕生した。
今日私たちは、今ある国の存在を自明視した上で、エネルギー政策を議論している。しかし実はそうした国々の存在自体が、石油という化石燃料の有無に強く依存しているのである。『石油が国家を作るとき』では、イギリス国立公文書館などの一次資料を用いつつ、世界各地における石油と国家形成の関係を論じ、さらに石炭や天然ガス、金銀といったその他の資源が与えた影響にも議論の対象を広げている。
















