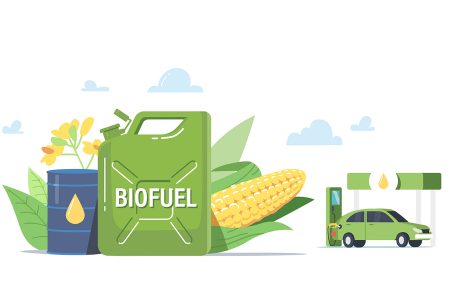PFAS報道に見る「煽り」の本質は科学と政治の関係にあり!
小島 正美
科学ジャーナリスト/メディアチェック集団「食品安全情報ネットワーク」共同代表
PFAS(有機フッ素化合物)に関する報道が目立っているが、総じて危険性を強調する傾向が強い。PFAS報道は1990年代の環境ホルモン大騒動とどことなく似ている。なぜ、メディアは危険性を煽るのか。その背景には、メディア特有の使命感、そして科学の世界にも「政治的な価値観」が入り込む問題があると言えそうだ。
文献をしぼってリスク評価
PFASに関しては、すでに唐木英明氏(東京大学名誉教授)、原田浩二氏(京都大学准教授)と藤井由希子氏(第一薬科大学)がこのサイトに記事を載せている。細かい専門的な議論はそちらに譲るとして、私はメディアの視点から、この問題の読み解き方(メディアリテラシー)を分かりやすく大局的に解説してみたい。
PFASの研究に関しては、これまでに世界で約3000本の論文がある。その中には、「血液中のPFASの濃度が高いと免疫の低下やがんを引き起こす」という論文もあれば、「がんや脂質異常とは関係ない」という相反する論文もある。日本の内閣府食品安全委員会(山本茂貴委員長・委員7人)と専門家ワーキンググループ(姫野誠一郎座長)は24年6月、約3000の論文のうち、科学的に信頼度の高いと思われる257本の文献を基にリスク評価をまとめた。
その結果、PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)については、これ以下なら健康影響はないとされる指標である「耐容1日摂取量」(TDI)を体重1キロあたり1日20ng(ナノグラムと言い、ナノは10億分の1の単位)、PFOA(パーフルオロヘキサンスルホン酸)についても、同様に20ngと決めた。
では、これら2つの物質に関して、日本人の平均的な摂取量は、この20ngを超えているのだろうか。農林水産省のデータから、日本人の1日あたりの平均推定摂取量は、PFOSが約0.60~1.1ng、PFOAは0.066~0.75ngだ。これらの数字を比べれば分かるように、日本人の平均摂取量は、耐容1日摂取量より相当に低く、特に健康リスクが高いという状況にはない。俗な言葉で言えば、あまり心配しなくてもよい。これが食品安全委員会の科学的なリスク評価である。
リスク評価とリスク管理の違い
ここで知っておきたいのは、「リスク評価」と「リスク管理」の違いだ。リスク評価はあくまで科学的な観点から文献を精査し、各種動物実験や疫学調査などから臨床的に見て確実に言えることを中心に評価する。たとえば、発がん性があるとする論文があっても、論文によって差があったり、摂取量と健康影響の関係(用量反応関係)に一貫性がなかったり、発がんのメカニズムが不明だったりする場合は、「証拠不十分」と判定されることもある。
これに対し、リスク管理はリスク評価とは異なる概念だ。管理という言葉から分かるとおり、たとえ証拠が不十分でも、ときの政府もしくは政党(与党)が政治的な判断を加味して、特定の研究論文を基に厳しい規制値(耐容1日摂取量や水道水の基準値、血液中の濃度指標など)を設定することは十分にありうる。実際に規制措置を決めるのは消費者庁や厚生労働省、農林水産省、環境省などだが、規制措置自体は科学的判断のほかに政治的な要素も加わるため、科学的な厳密性を必要としないケースもある。
つまり、リスク管理は国民の「安心」を重視して、予防的な観点から、規制を厳しくすることは往々にある。
放射性セシウムの基準値は「安心」重視
その例を示そう。日本政府は福島第一原発事故のあと、放射性セシウムの基準値を一般食品で1kgあたり100ベクレルと決めた。だが、これは西欧の基準値の1250ベクレルよりもはるかに厳しいものだった。当時、食品安全委員会や文部科学省の専門家グループは「欧米並みの基準でも問題はない」との見解を示していたが、日本政府(当時は民主党政権だった)は科学的な安全性よりも国民の「安心」を重視して、基準値を厳しくしたのである。放射性セシウムに関するリスク評価は日本と欧米で大きな差はなかったものの、リスク管理では大きな差が出たわけである。
これを見ても分かるように、リスク管理は科学だけで決まるわけではなく、政治的な要因やときの時代的な状況、国民の感情、政策決定にかかわる科学者の価値観によっても左右される。
アメリカのPFASの規制値は昨年、日本よりもはるかに厳しく設定された(たとえば、PFOSの水道水の基準値はアメリカが1ℓあたり4ngなのに対し、日本は同50ng)。それを決めたのは当時の民主党のバイデン政権である。アメリカ国内ではPFASをめぐる訴訟が続発し、なんとか政治的に対処せねばならぬ状況で厳しい規制値が決まった経過を見ると、日本の放射性セシウムの基準値が欧米より厳しくなったのと似ていると私は考える。
農薬にせよ、食品の放射線照射にせよ、その規制措置を決めるのは規制権限をもつ、ときの政府である。それがリスク管理である。
食品安全委員会がまとめたリスク評価はあくまで科学的な観点を重視しており、証拠の確かさや研究内容の一貫性を厳密に見ている。PFAS(PFOS、PFOAともすでに製造・使用が禁止されている)の健康影響に関して言えば、科学的な確かさから見て、それほど心配する必要はないという点をまずは押さえておくことが必要だろう。
NHKは危険性を強調するスタンス
では、こういう状況でメディアはどう報じているのだろうか。
一番気になるのがNHKの報道だ。明らかに危険性を強調する偏りが強い。「クローズアップ現代」(23年4月10日、24年6月12日)を見れば分かるが、数多くある論文のうち、がんや免疫低下、脂質異常などを指摘する学者(論文)を重視してニュースを作っている。番組では南デンマーク大学のフィリップ・グランジャン教授が登場して「私たちは、一部のPFASが様々な臓器に対して有毒であることを明らかにしてきた。毒性は親から子の世代へ影響し続ける」と述べるが、これはグランジャン教授の見解であり、科学的な定説ではない。
正しく恐れるとは何か
NHK(24年6月12日)は、健康調査で血液中のPFASの濃度が高かった岡山県吉備中央町の住民を取り上げ、「今も医者に行って、抗がん剤治療をやっていますが、これもう本当に水のせいだったら腹立ちますよね」という声を放映した。あたかも飲み水に含まれたPFASががんの原因かのような取り上げ方だ。
しかし、同町のホームページにある住民説明会(24年1月20日)の資料を見ると、以下のような解説があった。「PFASの健康影響はどのようなものか。どのようながんに注意すればよいか」などの声に対して、国立環境研究所の中山祥嗣氏(環境リスク・健康領域エコチル調査コアセンター次長、曝露動態研究室室長)は次のように答えている。
「出生体重の減少については、平均で50g程度の減少です。これは生まれて最初の便が200g程度なので、これと比較すると誤差の範囲とも考えられる。・・・PFOAによる発がん性の上昇はほんの少しです。たとえば腎臓がんになる人が1万人に1人との統計があるが、PFASの発がんの寄与率を仮に2%とするなら、100万人に2人くらいです。1000人の集団を1000年追いかけて2人増加するかどうかの影響率と考えています」。
中山氏の見解を聞けば、仮にPFASの健康リスクがあったとしても、おおよそのリスクの大きさを知ることができる。こういう見解を知ることも重要だと思うが、そういう見解はNHKの同番組には出てこない。
同NHK番組で「どういう恐れ方をしたらよいか」の質問に対して、ゲストの鯉淵典之・群馬大学教授は「過度に恐れないことだ」と答えるが、内容はどう見ても怖くなる話ばかりだ。
複数の専門家が登場して一見、客観性を重視しているかに見えるが、実は、食品安全委員会が評価するにあたってためらったような論文の考えを基に番組を構成している。こういう番組では、冒頭で「私たちNHK取材班は予防的な観点が重要だという判断のもとで欧米政府と同様の視点でストーリーを作りました」と正直に語るべきだろう。それを最初に言ってくれれば、安心して見ていられる。科学リテラシーも上がるだろう。
論文の選別はさまざまな分野で見られる
これまでの話で分かるように、政府にせよ、メディアにせよ、どの論文や学者を重視するかで国民に伝わる情報の中身は全く異なってくる。
この点について、東京新聞(3月31日)は、PFASとの関連で「心血管疾患のリスクが高くなる傾向がある」「脂質代謝を乱す可能性を示唆」「子どもの破傷風ワクチンに対する抗体が少なくなる傾向がある」「すい臓がんを促す可能性」などと指摘した11の論文があるのに、なぜ、食品安全委員会が不採用にしたかを問う記事を載せた。ポイントを突く良い記事だと思う。
ただ、この点については、すでに食品安全委員会はホームページで姫野誠一郎座長のインタビュー(聞き手は松永和紀委員)を載せている(24年6月26日掲載)。それを読むと、そうした疾患や影響を細かく評価した結果、「出生児への影響は証拠の確かさが強い」と評価したものの、他の項目については、証拠は限定的だったり、不十分だったりして、健康影響評価の指標値を導けるほど科学的な証拠はなかったと述べている。
不採用というと無視したかのように見えるが、無視したのではない。証拠としての信頼度が低かったということだ。こういうリスク評価に伴う論文の選別は何もPFASに限らない。農薬、食品添加物、遺伝子組み換え作物、ゲノム編集食品、食品の放射線照射、原子力、ワクチン接種、気候変動など様々な分野で論文の選別はつきまとう。
リスク報道の背景を知っておこう
実は、メディアの報道では論文の選別は常に起きている。私は1990年代にダイオキシンをはじめとする環境ホルモン問題で危険性を指摘する記事を数年間にわたって書いていた。そして、「環境ホルモンと日本の危機」や「人体汚染のすべてがわかる本」という2冊の本まで書いた。あのころはダイオキシンで男性がメス化して、子孫が滅ぶという懸念まで言われていた。
なぜ、危険性を強調していたかと言えば、それが市民側に立つ記者の使命だと思っていたからだ。そのときの手法は、とにかく環境ホルモンの危険性を指摘する論文を片っ端から紹介する手法だった。当時の私はまだ科学的なリスク論に目覚めておらず、いまになってみれば、汗顔の至りだが、今なお、この種の使命感に燃えるメディア・記者はいるだろう。東京新聞の記事はまさに過去の私とそっくりだ。
日本の国会での質問を見ていても、与党と野党ではどの論文を重視するかでかなりの差がある。野党の立憲民主党や共産党はたいていの場合、農薬や食品添加物などで危険性を強調する論文を選んで質問する。
価値観や政治姿勢が異なれば、記者も含めて、だれしも自分の主張に合った論文を好む。リスクに関する報道記事を読む場合は、そういう背景を念頭に置くことも重要だと知っておきたい。