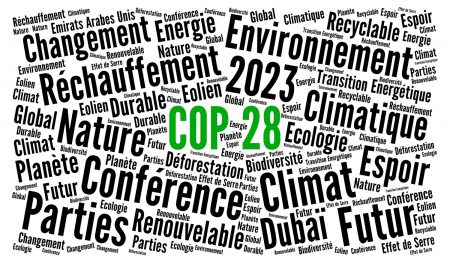第二期トランプ政権発足とエネルギー温暖化問題
有馬 純
国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授
(「産業環境管理協会「環境管理」 2025年3月号 vol.61 NO3」より転載:2025年3月10日)
国益最優先の第二期トランプ政権の発足は政治、外交、経済のあらゆる面で激震をもたらしている。エネルギー温暖化政策では国内エネルギー生産の最大化、エネルギーコスト引き下げ、エネルギードミナンスの確立を打ち出す一方、パリ協定の離脱、環境規制の緩和等、温暖化問題の軽視が顕著である。
筆者は温暖化防止をすべてに優先するような原理主義的な議論を強く批判してきたが、脱炭素を全面否定するのも無責任である。日本には右顧左眄(うこさべん)せず、国益をしたたかに見据えた、コモンセンスあるエネルギー温暖化政策を実施してほしい。
はじめに
第二期トランプ政権が発足した。様々な政策分野で激変が予想されるが、エネルギー温暖化分野はその最たる事例だろう。温暖化問題をめぐる共和党と民主党の党派的対立は非常に強い。2024年1月に世論調査機関のピューセンターが大統領選に向けた関心事を聞いたところ、20項目中のトップが経済(73%)であったのに対し、気候変動は18番目(36%)であった。しかし党派別にみると気候変動を重視するとしたのは民主党支持者の59%に対し、共和党支持者は12%に過ぎなかった。このため温暖化政策とその表裏の関係にあるエネルギー政策は政権交代のたびに前政権の路線の否定となる。
トランプ大統領は選挙期間中、「インフレを破壊し、物価を急速に引き下げ、歴史上最も偉大な経済を構築し、国防産業基盤を復活させ、新興産業に燃料を供給し、米国を世界の製造大国として確立するため、米国のエネルギーを解き放たなければならない。我々は、掘って、掘って、掘りまくり(drill,baby,drill)、輸入エネルギーに依存しない、エネルギードミナントな国になるだろう」と、エネルギー重視の姿勢を前面に押し出した。
Day1の大統領令でバイデン政権の施策を全否定
1月20日の就任演説では化石燃料掘削を制限し、再エネを推進したバイデン前政権の政策を「気候過激主義」と呼び、「エネルギー緊急事態」を宣言し、過剰な政府支出とエネルギー価格の高騰がインフレを招いたとして「黄金の液体」である石油の採掘を拡大するとの方針を表明した。
この方針を実施に移すため、同日、ホワイトハウスは「米国のエネルギーの解放」と題する大統領令を発出した*1。大統領令では「米国は豊富なエネルギーおよび天然資源に恵まれている。近年、負担の大きい、あるいはイデオロギーに動機付けられた規制が、これらの資源の開発を妨げ、信頼性が高く手頃な価格の電気の発電を制限し、雇用創出を減らし、そして国民に高いエネルギーコストを強いてきた。こうした高いエネルギーコストは、輸送費、暖房費、公共料金、農業、製造業のコストを押し上げ、米国の消費者を疲弊させると同時に、国家の安全保障を弱体化させている。米国の安価で信頼性の高いエネルギーと天然資源を解き放つことは、国家の利益につながる。これにより、近年、経済から取り残されてきた男女を含め、米国の繁栄が回復されるであろう。また、わが国の経済および軍事安全保障を再建し、強さを通じて平和をもたらすことにもなる」との認識の下、以下の政策を実施するとしている。
- ・
- 連邦政府が所有する土地および水域(大陸棚を含む)におけるエネルギーの探査および生産を奨励し、国民のニーズを満たし、米国が将来にわたって世界のエネルギーリーダーとしての地位を確固たるものにする。
- ・
- レアアースを含む燃料以外の鉱物の主要な生産者および加工業者としての地位を確立し、国内に雇用と繁栄をもたらし、米国およびその同盟国のサプライチェーンを強化し、悪意のある敵対的な国家による世界的な影響力を削減すること。
- ・
- 信頼性の高いエネルギーの十分な供給が、米国のすべての州および領土で容易に利用できるようにすることで、米国の経済および国家安全保障、軍事準備態勢を保護すること。
- ・
- エネルギーに関するすべての規制要件が明確な適用法に基づいていることを確保する。
- ・
- 自動車利用に関する規制障壁を撤廃し、自動車に関する消費者の選択肢に公平な規環境を確保し、また、ガソリン自動車の販売を制限する機能を持つ州の排ガス規制免除を適宜廃止すること、および、電気自動車を他の技術よりも優遇し、個人、民間企業、政府機関による購入を事実上義務付けるような、不公平な補助金やその他の不適切な政府による市場歪曲を排除することを検討すること。
- ・
- 電球、食器洗浄機、洗濯機、ガスレンジ、給湯器、トイレ、シャワーヘッドなど、多種多様な商品や家電製品から選択するアメリカ国民の自由を保護し、製造および家電業界における市場競争と技術革新を促進すること。
- ・
- 規則、規制、行動の世界的影響を、その都度評価する際に、国内における費用対効果とは別に報告することを確保し、健全な規制上の意思決定を促進し、アメリカ国民の利益を優先させること。
- ・
- すべての執行部門および機関(機関)が、公衆の意見を求める機会と、厳格なピアレビューによる科学的分析を提供することを保証すること。
- ・
- 法律で義務付けられている場合を除き、本条に概説された原則に反する方法で連邦資金が使用されないことを確保すること。
大統領令ではバイデン政権時代に発出され導入されたエネルギー、気候変動に関する以下の12本の大統領令を廃止するとした。更に気候変動に対処するための2万人以上の人材育成を目的にバイデン政権が発足させた「気候部隊」に関する活動、プログラムも直ちに廃止される。
- ・
- 公衆衛生および環境の保護、および気候危機への取り組みのための科学の復興に関する大統領令13990
- ・
- 連邦規制に関する特定の大統領令の失効に関する大統領令13992
- ・
- 国内外における気候危機への取り組みに関する大統領令14008
- ・
- 大統領科学技術諮問委員会に関する大統領令14007
- ・
- 難民の再定住プログラムの再構築および強化、ならびに気候変動が移民に及ぼす影響の計画に関する大統領令14013
- ・
- 気候変動支援室の設置に関する大統領令14027
- ・
- 気候関連の金融リスクに関する大統領令14030
- ・
- クリーンな自動車およびトラックにおける米国のリーダーシップの強化に関する大統領令14037
- ・
- 連邦政府の持続可能性を通じてクリーンエネルギー産業と雇用を促進する大統領令14057
- ・
- 国家の森林、地域社会、および地域経済の強化に関する大統領令14072
- ・
- 2022年インフレ抑制法のエネルギーおよびインフラ規定の実施に関する大統領令14082
- ・
- すべての人々に対する環境正義に対するわが国の公約の活性化に関する大統領令14096
文字通り、バイデン政権の政策の完全否定であり、政権交代のインパクトの凄まじさを如実に示している。トランプ大統領はバイデン政権のエネルギー温暖化施策の最大の実績ともいうべき2022年インフレ抑制法にも否定的で、大統領令の第7条「グリーンニューディール政策の廃止」では2022年インフレ抑制法またはインフラ投資・雇用創出法で計上された資金の支出を直ちに一時停止し、補助金等を交付するためのプロセス、政策、プログラムを法律および大統領令に示された政策の方向と整合性を保つために見直すとしている。ただインフレ抑制法によって裨益(ひえき)しているクリーンプロジェクトは共和党州に多く分布しており、トランプ大統領がインフレ抑制法を廃止、大幅見直ししようとしても共和党内からブレーキがかかる可能性もある。
第二期トランプ政権のエネルギー・気候政策の布陣
第二期トランプ政権に向けてトランプ大統領が指名した閣僚人事を見ても温暖化重視のバイデン政権とは打って変わってエネルギーシフト全開となっている。まずキーパーソンとなるのが内務長官に指名され、ホワイトハウスに設置される国家エネルギー会議議長にも就任予定のダグ・バーガム元ノースダコタ州知事である。バイデン政権ではホワイトハウスで気候変動問題の国内・国際対応を総括する閣僚級の「ツアー(皇帝)」が任命されていた。国際面を統括したのがジョン・ケリー元国務長官であり、化石燃料を敵視する環境原理主義的な温暖化外交で日本も大いに迷惑をこうむった。今回、こうしたポストが廃止され、代わって国家エネルギー会議が設置されたのは、米国の国内エネルギー生産の拡大に向け、各省庁に強い指導力を発揮することを意図するものだ。バーガム氏は上院公聴会において「エネルギードミナンスは米国の歴史的繁栄、家計の経済的余裕、比類ない安全保障の基盤だ」と述べ、石油など化石燃料を増産する考えを強調した。バーガム氏はノースダコタ州知事時代にCCS技術を活用した2030年カーボンニュートラル目標を発表しており、温暖化問題を否定しているわけではないが、国の重点シフトは明らかだ。エネルギー政策を統括するエネルギー長官にはリバティエナジーCEOのクリス・ライト氏が指名された。彼も上院の公聴会で石油、天然ガス開発の大幅拡大とエネルギー価格の低下、エネルギードミナンスの強化を打ち出し、バイデン政権が凍結したLNG新規開発、輸出計画審査を就任初日に再開すると宣言した。ライト氏は気候変動問題を否定しないが、気候変動が世界の最も緊急な課題ではなく、むしろ化石燃料を含むエネルギーアクセスの拡大により2050年までに世界の貧困をゼロにする方が2050年カーボンニュートラルよりも有益との考え方である。また再生可能エネルギーの役割を認めつつも、太陽光や風力だけでは増大するエネルギー需要を満たすことはできず、エネルギー密度の高い化石燃料と原子力が不可欠であるとも述べている。環境保護庁(EPA)長官に指名されたリー・ゼルディン氏は下院議員時代にEPAの予算・人員の大幅カット、気候変動枠組み条約からの離脱、国内エネルギー資源開発の拡大に賛成しており、上院公聴会においても「EPAはCO2を規制する義務はない」と発言している。
この布陣の下で、今後、石油ガス掘削規制のための連邦所有地の開放、化石燃料掘削に関する環境規制の緩和、自動車燃費規制の緩和、電気自動車補助金の廃止等、バイデン政権の施策の180℃転換が進められることになる。共和党は上下両院を抑えたとはいえ、下院は数議席差で拮抗しており、上院でもフィリバスターをオーバーライドできる議席数ではないため、政策変更は上述の大統領令のような行政命令が中心となろう。
パリ協定からの離脱とその影響
国際面では予想された通り、20日夕の演説で「不公平で一方的なパリ協定から即時離脱する。中国が平気で汚染を続けているのに、米国が自国の産業を妨害することはしない」とし、同日、大統領令「国際環境協定においてアメリカを最優先に」を発出した*2。この大統領令では「米国は、環境保護に向けた世界的な取り組みにおいて指導的役割を果たしながら、経済を発展させ、自国民の雇用を維持しなければならない。米国は、民間部門の活動を妨げない賢明な政策の支援を受け、数十年にわたって経済を発展させ、労働者の賃金を引き上げ、エネルギー生産を増大させ、大気および水質汚染を削減し、温室効果ガス排出量を削減してきた。経済と環境の両方の目標を達成してきた米国の成功例は、他国の模範となるべきである。近年、米国は、米国の価値観や経済および環境目標の追求に対する米国の貢献を反映していない国際協定やイニシアティブへの参加を表明している。さらに、これらの協定は、米国国民の利益のために、財政支援を必要としない、または価値のない国々に米国の納税者の資金を流している。米国経済に損害を与えたり、その成長を妨げたりする可能性のある国際協定の策定や交渉においては、米国および米国国民の利益を最優先すべきであり、米国に不当または不公平な負担を強いてはならない」との認識の下、以下を規定した。
- ・
- 米国連大使は、気候変動枠組条約に基づくパリ協定からの米国の離脱を正式に書面で直ちに通知する。米国は、本通知をもって、条約からの離脱およびそれに伴う義務を即時に有効とする。
- ・
- 米国連大使は、気候変動枠組条約の下で締結されたあらゆる合意、協定、協約、または同様の約束から離脱する旨の正式な書面による通知を、直ちに国連事務総長または関係者に提出する。
- ・
- 米国連大使は、国務長官および財務長官と協力し、気候変動枠組条約に基づき米国が行ったとされる財政的義務を直ちに停止または破棄する。
もとより米国がパリ協定、更には気候変動枠組条約から離脱したとしても温暖化に対する国際的取り組みが崩壊するわけではない。環境意識の強い欧州は米国の動向にかかわらず温暖化防止努力の継続・強化を標榜するだろうし、中国は米国との対比で「責任ある大国」を演出するだろう。また脱炭素に熱心な米国の自治体、企業等が「We Are Still in(我々はまだパリ協定にいる)」運動を推進し、トランプ政権の意向にかかわらず、米国の温暖化防止は進むとPRするだろう。
しかし、先進国中最大の排出国である米国が温暖化防止に背を向け、気候資金への拠出を一切行わないことになれば、温暖化防止に対する国際的なモメンタムが実質的に低下することは避けられない。昨年11月のCOP29では途上国に対する新資金援助目標として「2035年までに少なくとも3,000億ドル」が合意された。先進国最大の経済規模を有する米国が離脱すれば、新資金援助目標の達成が困難になることは明らかだ。最大のドナーとなるべき米国が抜ければ、新興国・途上国は「先進国からの支援が十分得られないならば、できることにも限界がある」というモードになるだろう。さりとて欧州や日本が米国の穴を肩代わりするわけにもいかない。
トランプ政権の政策変更と日本への影響
第二期トランプ政権のエネルギー環境政策が日本に与える影響も注視が必要だ。米国のエネルギー生産が拡大すれば、中東依存度の高い日本のエネルギー安全保障にとってはプラスになる可能性が高い。第一期トランプ政権時に比して中国の地政学的脅威は大きく高まっており、中国製のクリーンエネルギー産品や中国がサプライチェーンを支配する重要鉱物への依存度拡大は新たな経済安全保障上の問題を惹起する。第一期トランプ政権時代の日米戦略エネルギーパートナーシップ(JUSEP)のように、LNG供給、CCUS、原子力、バッテリー、重要鉱物分野での協力を推進すべきだ。
バイデン政権時代、G7プロセスで米欧が連携して石炭火力のフェーズアウト等で日本を苦境に追いやる構図がしばしば見られたが、化石燃料を重視するトランプ政権はそのような立場はとらないだろう。
他方、トランプ政権のパリ協定離脱を踏まえ、「脱炭素をめざす日本のエネルギー政策は誤りだ」とか「日本もパリ協定から離脱すべきだ」との議論があるが、これは大きな誤りだ。
我が国のエネルギー温暖化政策の前提となっている1.5℃目標の非現実性についてはこれまで繰り返し発信してきたところである*3。2028年COP28で合意されたグローバルストックテイクでは「1.5℃目標を射程内にとどめる」とされたが、COP29において合意された「2035年少なくとも3,000億ドル」という資金援助目標について途上国は強い不満を提起しており、1.5℃目標実現に不可欠な途上国の目標の大幅な引き上げは全く期待できない。もともと実現可能性のなかった1.5℃目標の死は誰の目にも明らかになりつつある。しかし、平和団体が絶対に実現しない「核なき世界」を標榜し続けるごとく、COPやG7をはじめとする国際社会は1.5℃目標を掲げ続けている。こうした中で政府が1.5℃目標を表立って否定しにくいことも元役人としては理解できる。米国では政権交代によって前政権の政策を全否定することが常態化している。
しかし自民党政権が続いている日本においてこれまでの政策を全否定することはできない。またパリ協定の締約国として温暖化防止に努力すること自体は決して間違っていない。第一期トランプ政権と蜜月であった安倍政権でも温暖化対策やパリ協定については一線を画した対応をした。日本が温暖化防止に関する唯一の国際的枠組みであるパリ協定から離脱することの外交的コストはあまりにも大きい。共和党政権が未来永劫続くことは考えられない。将来、民主党政権が復活し、パリ協定に復帰したら日本もそれに追随するというのだろうか。パリ協定で提出する目標も法的義務ではない。EUやバイデン政権の米国と並んで見栄えの良い目標を発表したとしても、それに向けた取り組みは国益を最優先とすればよい。国益を毀損してまで目標数値と心中する国など存在しない。
日本のエネルギー温暖化政策で留意すべきはコスト
おりしも昨年12月には第7次エネルギー基本計画の素案が提示され、温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が閣議決定された。
素案においては第4次エネルギー基本計画以来、日本のエネルギー政策を呪縛してきた「原発依存度の可能な限りの低減」が削除され、再エネと原子力をともに最大限活用するとの考え方を明記された。福島事故以降、日本のエネルギー政策をゆがめてきた原発と再エネを二者択一的にとらえる議論を克服したことは高く評価できる。またエネルギー需給見通しにおいては複数シナリオが提示された。2050年カーボンニュートラルに向かう直線上で目標が設定された(2035年▲60%、2040年▲73%いずれも2019年比)が、そこに向けて大幅な技術コストの低下を前提に4つのシナリオ(再エネ拡大、水素・新燃料活用、CCS活用、革新技術拡大)が提示され、加えて2040年度時点において脱炭素技術のコスト低減が十分に進まないリスクケースも想定された。削減目標先にありきの「都合の良いシナリオ」よりも蓋然性の高い「リスクケース」を想定した意義は大きい。リスクケースでもエネルギー安定供給に万全を期すということは、温暖化目標をすべてに最優先するのではなく、コスト如何によってエネルギー安定供給を優先することであり、ウクライナ戦争前の脱炭素最優先的な風潮から、より常識的な方向にバランスがシフトしていることを示す。
基本計画の実施において重要なのはコストに対する目配りである。脱炭素政策による国内電力コストの高騰がデータセンターや半導体工場誘致を阻害し、ドイツのように我が国の製造業が生産拠点の海外移転を考えるようなことも決してあってはならない。基本計画で示された方向に向かう際の「値札」を常にチェックし、何等かのベンチマークに基づき、国際的な負担の公平性を比較するプロセスが必要となる。エネルギー転換に伴うコスト負担増が日本の国益を阻害するようであれば、「リスクケース」で想定されたようにエネルギー安定供給を脱炭素化に優先させることを躊躇してはならない。
おわりに
国益最優先の第二期トランプ政権の発足は政治、外交、経済のあらゆる面で激震をもたらしている。筆者は温暖化防止をすべてに優先するような原理主義的な議論を強く批判してきた者であり、率直に言えば環境原理主義者の横っ面を張り飛ばすようなトランプ大統領のやり方にエールを送りたい気持ちもある。しかしパリ協定からの離脱や資金援助の凍結等、脱炭素を全面否定するのは環境原理主義とは反対の意味で無責任であると考える。ましてやトランプ政権に乗っかって「脱炭素は終わりだ」「パリ協定から日本も離脱すべきだ」との議論には全く賛同できない。トランプ大統領は就任演説で「コモンセンスの革命」を強調した。筆者は行き過ぎた環境原理主義も、温暖化をまやかしという姿勢もコモンセンスに反すると考える。日本には右顧左眄(うこさべん)せず、国益をしたたかに見据えた、コモンセンスあるエネルギー温暖化政策を実施してほしい。
- *1.
- https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/
- *2.
- https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/
- *3.
- https://foreignpolicy.com/2024/01/08/climate-target-degrees-warming-cop-emissions-resilience/