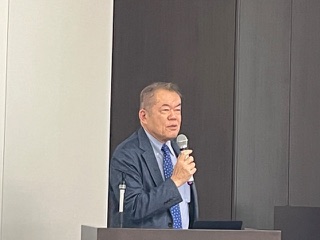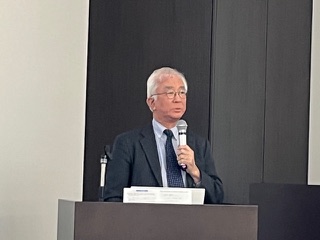水素・アンモニア利用の課題「コスト」をいかに解決するか?–IEEIシンポ
石井 孝明
経済記者/情報サイト「withENERGY」(ウィズエナジー)を運営
国際環境経済研究所(IEEI)は1月31日に公開シンポジウム「水素・アンモニア社会実現の課題」を東京で開催した。水素・アンモニアは脱炭素を達成するエネルギーとして注目されている。しかしコストの高さなど、乗り越えなければ課題も多い。
講演は2つ行われた。IEEI所長で常葉大学名誉教授の山本隆三氏による「トランプのエネルギー政策と欧米の水素戦略」(内容の概要)。
また国際環境経済研究所主席研究員の塩沢文朗氏による「水素・アンモニア利用の課題」だ。(内容の資料)。
トランプ新政権のエネ政策、共和党州の利益が鮮明
トランプ大統領は就任直後に風力と太陽光、EV補助金など、これまでバイデン政権の進めてきたクリーンエネルギーへの政府支援を縮小し、化石燃料の生産増をはかることを表明している。建前では進行するインフレ抑制のためとするが、山本氏はこの政策に「党派性がある」と指摘する。
洋上風力の計画が着工された州は、全て東部の民主党が地盤、つまり知事や議席の多い州だ。一方で共和党支持の州は中西部を中心に、1人当たりの車の利用距離、つまりガソリンの使用量が多い傾向がある。ガソリン価格の上昇は車に乗ることが多い米国民の生活を苦しめている。つまりトランプ政権は、洋上風力発電の新設を邪魔することで民主党への政治的ダメージを与える一方で、共和党支持者の人気を集めようと原油を増産しガソリン価格を引き下げようとしているわけだ。
講演時点で、トランプ政権は水素の支援政策について明確にしていないが、「それはコスト、米国の利益になるかどうか次第だろう」と山本氏は指摘した。
計画倒れに終わりそうな水素社会
バイデン前政権は意欲的な水素の利用構想を示した。2030年1000万トン、2050年に5000万トンの製造目標を立てた。またEUは2030年に域内生産で1000万トン、域外生産で1000万トン、そして2050年に全エネルギーの10%を水素にする計画だ。しかし、その生産能力を満たすことは難しい。
水素にはさまざまな製造法がある。再エネから作られる水素を「グリーン水素」、またそれと重なる脱炭素の電源を使う製造を「クリーン水素」などと呼ぶ。現在は化石燃料から作られる方法が主流だ。IEEIでは、2024年秋にEUを訪問し、専門家らと意見交換を行った。そのヒアリングや公開情報で、次の事実が出た。
2030年にEU域内で生産可能なクリーン水素は年250万トン、大きな政策支援が追加されても年440万トンの製造しか確保できるめどはない。そして域外からの1000万トンの輸入構想も調達の見通しはない。さらに水素輸送のインフラ整備も進まず、EU全域への流通手段が確保されていない。
EUで国や業界団体の計画があっても、事業の設備着工が始まらない理由は製造コストの高さにあるとされる。その結果、水素の需要の先行きが不透明で、ビジネスとしての投資がしづらい状況になっている。
高くつく日本の水素
現在の水素の製造コストは次の状況だ。現在の欧州でのSMR方式(天然ガスあるいは石炭と水蒸気による製造)でCCS(二酸化炭素回収・貯留技術)を併用した場合に、天然ガス価格が百万BTU(MMBTU)当たり約12ドルの前提で1キログラム(kg)当たり3.6ユーロとされている。
水電解によるコストは、各国の電力コストにより異なる。現在の電気料金(二酸化炭素も排出される)での欧州の国の水素の製造コストは、フィンランドでkg当たり約4ユーロ、ドイツでは10ユーロ近くになる。米国では天然ガス生産が世界一で、それを使った水素の製造コストは安くなる。米国石油協会は、天然ガス価格がMMBTU当たり約4ドルの場合、CCSを利用しても2030年時点の水素価格はkg当たり2ドルを下回ると試算している。
山本氏は欧州鉄鋼連盟の人に、「補助金で設備を作っても、その後はオペレーションコスト(操業費用)が経営に響く。そこまで各国政府は面倒を見ない。不透明で他の生産手段、あるいは米国よりコストがかかりそうで、水素向けの投資はしづらい」と言われたそうだ。
日本で水素を水電解で製造する場合の電気のコストは、電力料金を1kWh当たり10円と想定しても、水素製造の電気料金だけで水素1kg当たり400円を超えてしまう。設備の費用などを考えると、日本の水電解水素が競争力を持つことは難しい。
現在、出力制御されて売電できない再エネの電気が無駄になることが問題になっている。再エネ関係者などからそれを利用して水素を作れば良いとの提案が出ている。確かにそれを使えば電力費は抑制可能だが、自然現象で作られる電力であるためにいつ余剰電力が発生するか完全に予測できない。「そのために設備の利用率が低迷することになり、製造コストが抑制されることにはならない」と山本氏は指摘した。
また水素の製造では、水の電気分解による製造装置では中国製品が主流だ。EUとトランプ政権は中国依存を脱却する方針だが、水素の製造でも脱中国が問題になりそうだという。これらの課題を見ると、水素の利用は、近い将来ではかなり厳しいと山本氏は分析している。
アンモニアの可能性、海運、発電での期待
一方で、塩沢氏は講演で「山本さんの内容は悲観的だったが、私はそれほどでもない」と述べた。
塩沢氏は経産省、内閣府で化学物質管理、科学技術政策を担当した。民間に転じてからも、公的団体で、水素・アンモニアに関わり続けている。「電源の脱炭素化。特に再エネの調整力としての火力発電の脱炭素化の手段」「燃料の脱炭素化(産業部門、運輸部門)の手段」「原料の脱炭素化(鉄鋼、化学)の手段」「炭素のリサイクル・有効利用の手段」の4分野で、水素とアンモニアが使われる期待があるという。
石炭火力の二酸化炭素排出量の大幅な改善は、アンモニアの混焼が最も有力な技術だ。石炭と水素の混焼は難しい。そして世界は当面、石炭火力をゼロにはできない。2024年にJERAと国が行った石炭火力発電でのアンモニア混焼の実証試験をやった。その結果がよく、2027年から商業運転の予定だ。
世界のメーカーは水素製造に流れている。アンモニアの発電利用は日本独自で、メーカーの数も少ない。しかし水素をアンモニアに変え運搬する、それを発電に使う技術はすでに実用化されている。こうした合わせ技で、ランニング・コストを減らせる技術がある。
また国際海事機関(IMO)が2050年までのカーボンニュートラルを決めている。2023年に船舶燃料で、2050年までにアンモニアを4割強、水素を2割弱の燃料にする目標を掲げた。主に長距離を移動する外洋航行をする船の燃料にアンモニアの利用が増えるだろう。
アンモニアの管理は可能
ただし化学物質として、管理はいずれも難しい。水素やアンモニアにも発がん性とか、生殖毒性などはない。ただしアンモニアは、刺激などの毒性はあり、危険な物質である。化学物質は日常の管理、また事故後の対応で安全性が必要だが「これまで水素、アンモニアは工業利用されており、管理の方法も経験も蓄積されている。対応は可能」と塩沢氏は、専門家として指摘した。
質疑応答では、専門家が多かったためか、水素、アンモニアの商業利用に懐疑的意見も出た。
水素、アンモニアの社会実装には、少し時間がかかりそうだ。しかし世界が脱炭素に向かう中で、2つのエネルギーの先行きは注目するべきビジネス情報だ。