著書「新しい石油の地政学」を上梓して
橋爪 𠮷博
日本エネルギー経済研究所 石油情報センター
今般、新著「新しい石油の地政学」(秀和システム刊)を上梓した。
カーボンニュートラルを目指して脱炭素化が進む中、「新しい石油」もないが、近年、シェール革命やウクライナ戦争によって、世界の石油・エネルギー情勢が一変したことを踏まえ、あえて「新しい石油の地政学」とした。
石油に携わって42年、職業生活の終わりに秒読みが始まる中、その間ウォッチし続けてきた国際石油情勢、特に原油価格の変動と国際政治・経済情勢の相互関係について、自分なりの見立て・仮説を踏まえて、骨太に考察した。もちろん、昨今の脱炭素・カーボンニュートラルの動きが、石油情勢や国際情勢、さらには我々の生活にも与えるであろう影響についても言及した。特に、安定供給の前提となる、脱炭素に伴う産油国と消費国の長期相互依存関係の消滅を強調したい。それは、昨今の原油価格高止まりの根本原因でもある。脱炭素が進めば、エネルギー安全保障問題は自動的に解決するという考え方は、あまりに楽観的過ぎて危険である。
一般に、戦争やテロなど国際情勢の緊張・変動があった場合、原油価格にどのような影響を与えるかといった分析や説明は、専門家やマスコミから盛んに行われる。今回のイランによるイスラエル報復攻撃もそうである。しかし、その逆、原油価格の激変が国際情勢に与える影響が説明されることはほとんどない。その点を、原油の生産コストと販売価格の差、すなわち、石油の「レント」・「富」に着目して、大産油国の国力、その栄枯盛衰を中心に考えた。国際情勢から石油情勢への一方的な因果関係ではなく、その相互作用を考察したかった。
また、石油・エネルギーに関する「地政学」というとき、わが国では、通常、エネルギーセキュリティの観点から、産油地帯への進出、自主開発原油の確保、ホルムズ海峡・南シナ海の安全航行など、供給アクセスの問題が中心的論点となる。それは、確かに、無資源の消費国であるわが国とっては死活問題であり、太平洋戦争の反省・石油危機の教訓でもあるから、当然である。しかし、あえて本書で焦点を当てたのは、従来あまり言われてこなかった、二度の石油危機を経て、メジャー国際石油資本が原油価格の支配権・設定権を喪失したことを原因とする、この50年間の原油価格の高騰・暴落の繰り返しとそれに伴う3大産油国(米国・ロシア・サウジアラビア)の栄枯盛衰を描く「地政学」であった。
そもそも、「地政学」自体、学問体系には位置づけられていないし、論者が自分なりに使う、定義があいまいな用語であるが、一般的に使われる「地理的条件が特定の国・地域の政治・経済・軍事等に与える影響について研究する学問」であるとするならば、産油国の石油という天然資源の埋蔵・生産、あるいは逆に、消費国の石油への国民生活・産業活動の依存という意味で、「石油の地政学」という言い方は許されるであろう。
もうひとつ、言い訳をさせて頂くとするならば、著者は、マスコミや事業者・一般消費者に対する石油情報の「発信者」ではあるが、アカデミックな訓練を受けたエネルギーの「研究者」ではない。したがって、本書で述べた仮説・見立ての多くは、先行研究を踏まえたもの、定量的な検証・実証を経たものではないことをお詫びしなければならない。ただ、脱炭素化は確実に進むであろうが、将来に向けて、本書が何らかのヒントとなれば、これに勝る幸せはない。
最後に、故澤昭裕氏による設立以来、多くの学識者や実務者の末席に加えて頂き、議論や認識を深めて下さった、桝本晃章前理事長、小谷勝彦現理事長、山本隆三研究所長をはじめとする国際環境経済研究所の関係者の皆さんに深く感謝申し上げなければならない。皆さんとの交流なくしては、本書は出来なかったと思っている。
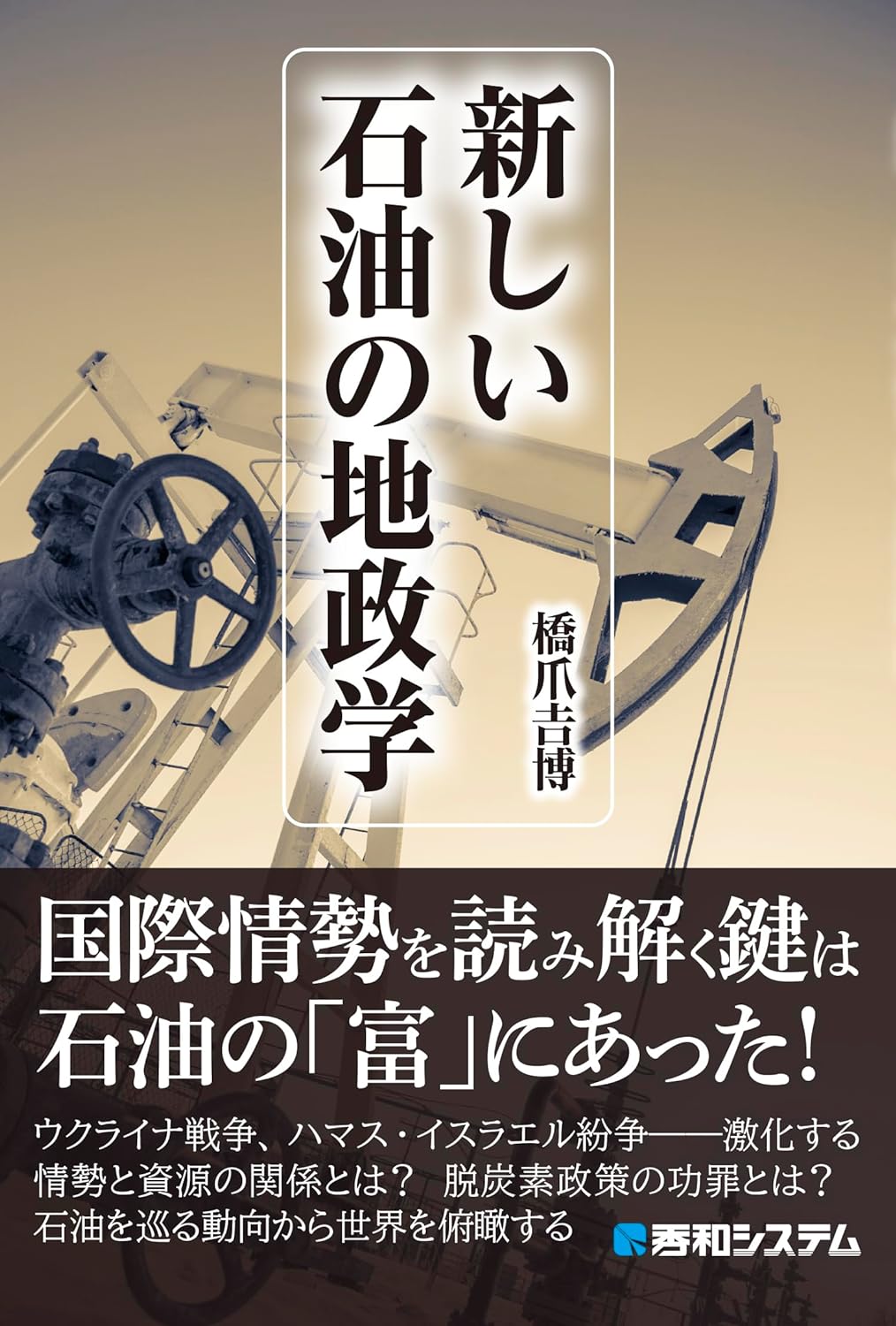 『新しい石油の地政学』
『新しい石油の地政学』
橋爪 吉博 著(出版社::秀和システム )
ISBN-13:978-4798070773




















