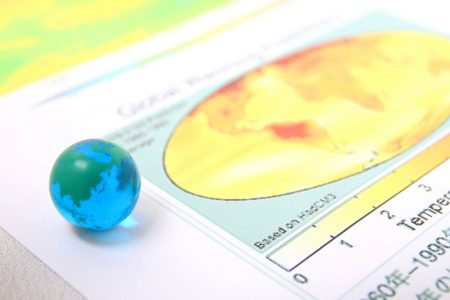二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その1)
金子 勇
北海道大学名誉教授(社会学)
第1節 「再エネ」問題の所在
各新聞報道を総合すると、2021年11月13日閉幕した国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)では、石炭火力発電の低減が会議の成果文書に盛り込まれた。表現が「廃止」から「削減」に弱まったものの、今後も石炭火力の活用を続ける日本には、脱炭素化へ向けた国内対策の弱さへ内外から批判が続く可能性が残る結果となった。一方、脱炭素化に貢献すると国際認識が高まる原子力発電については、日本は再稼働を掲げるものの具体的な将来像は描けていないままになっている。
文書では「排出削減対策のない石炭火力のフェーズダウン(段階的な低減)に向けた努力を加速する」との表現が入った。政府関係者は閉幕後「これまでのCOPで世界全体の枠組みとして石炭が入るのは初めて」とそのインパクトを指摘している。改めて2030年度の削減目標(2013年度比46%)達成に向け、非効率石炭火力の削減を着実に進めていく姿勢を強調した。
脱炭素の議論が盛り上がる中、世界ではむしろ原発の意義が高まっている。総発電量に占める原発の比率が70%を超える電力輸出国のフランスは、COP26期間中脱炭素化を進展させるため原発建設の再開を発表した。それに先立ち、10月にはEU加盟の9カ国とともに原子力に関する共同宣言をまとめ、無炭素電源としての原子力活用の重要性を訴えた。
一方、日本は10月決定の「エネルギー基本計画」で、排出削減に貢献するとして原発再稼働は盛り込んだが、建て替えや新設に向けた議論は棚上げした。
このように、COP26で各国が示した温室効果ガスの排出削減目標が達成されても、2030年の温室効果ガスの排出量は2010年より16%程度多くなるとみられている。そのため今回の参加国が宣言した対策を全て実施しても、今世紀末には2.4度気温が上昇する見込みで、温暖化対策は待ったなしという。そのシミュレーションを受けて、今後は「再エネ」の利用がますます高唱されるであろう。日本でも同じ状況にあるが、一方では低周波音による健康被害や環境への悪影響も懸念される。
たとえば、風車から発生する「低周波音」は人体に影響を及ぼすといわれて久しい。風車のタワー先端には発電機などを納めた「ナセル」があり、ブレード(回転羽根)とつながっていて、風を受けてブレードが回ると、その動きが発電機に伝わって電気を起こす。その際にナセルからは可聴音が、ブレードからは超低周波音や低周波音が発生する。これは風力発電機では構造的に避けられない。
人間によく聞こえる音は、周波数1000〜4000Hzで、周波数20Hz以下の超低周波音は聞こえにくいとされてきたが、周波数が低くても音が強ければ知覚できるし、時計の秒針の音が気になって眠れないなど、音の感じ方には個人差が大きい。さらに低周波音や超低周波音は波長が長いため、数キロメートル離れた場所でも確認でき、広範囲で健康被害を生じる可能性が各方面で指摘されてきた。
低周波音や超低周波音による人体への影響として、心血管系(血圧、心拍数など)の変化や、集中力の欠如、めまい、倦怠感、睡眠障害、鼓膜の圧迫感、振動感などが報告されている。
これまでにも風力発電所周辺に、睡眠障害や頭痛、疲労感などの体調不良を訴える住民が存在することが、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オランダなど世界各国で報告されてきたことはインターネットで数多く閲覧できる。
一般的に風力発電機の設置は、年間を通じて風が吹く地域に集中する傾向があった。エネルギーとして利用できる風の資源量が日本で最も多いのは北海道であり、全国の約50%を占め、次いで東北地方が約22%となり、これらの地域では風力発電所の建設が急増している。たとえば、私が定点観測してきた北海道石狩湾新港地区では、2005〜2007年にかけて、定格出力1.5メガワットと1.6メガワットの風車3基が設置されていたが、2018年以降、風力発電事業者が次々と参入し、3メガワット級の風車合計19基(約60MW)がすでに稼働する。
そのうえ後述するように、8メガワット級の洋上風車を港湾地区に14基設置する計画や、港の外の石狩湾洋上に大規模な風力発電所を建設する計画やすでにアセスメント実施の段階にある洋上風力発電も数多くある。
風車が大型化するほどそして設置数が増えるほど、音の影響は強くなる。石狩市は人口約6万人で、隣接する札幌市の人口は約195万人、小樽市は約11万人であり、このような人口密集地に隣接して、大規模な風車群が設置されるのは、世界的にも稀である。大規模風車群が稼働すれば石狩市だけでなく、小樽市や札幌市を含む広範囲で健康被害が出る可能性が指摘されている注1)。
設置反対の主な理由は、植物や動物など環境への影響、低周波音・超低周波音による健康影響、景観破壊や住宅の資産価値の下落などである。一方、政府や投資家は、主に経済面に関心があり、自然環境を犠牲にする傾向が見られる。現地をみれば一目瞭然だが、「自然に優しい」と手放しで喜べる状態ではけっしてない。
近隣住民の反対によってヨーロッパでは陸上に風車を設置するのが難しくなり、陸地から遠く離れた洋上に風力発電所を設置するようになった。しかし、大陸棚が広がり水深が浅いヨーロッパの海とは違い、日本近海の海底は急峻なので、そのため住宅地に近い沿岸部や港湾での洋上風力発電導入が進んできた。
ともすれば「再エネ」推進派は、周辺住民や環境にどのような影響が出るかについての疫学調査だけではなく、風車の羽根に鳥がぶつかって死亡するバードストライクをはじめ周辺の動植物への悪影響にも配慮しない傾向がある。「再エネ」というイノベーションの実践的な活用でも、功罪合わせて情報をすり合わせたうえでの合意形成が求められる。地球環境を持続的に守るという「目的の共有」はありながらも、電源だけでも同床異夢が目立つ現在、このような観点から社会学で彫琢されてきた機能分析法を使って、以下「再エネ」問題を考えてみたい。
第2節 機能分析の目的と方法
英語の諺に“Fling dirt enough and some will stick.”がある。10年前に出した『環境問題の知識社会学』(金子、2012)以来、二酸化炭素地球温暖化論についての国内外における言動に接するたびに、この諺を思い浮かべてきた。ついでに言えば、‘dirt’には‘uncleanness of thought, speech or action’という意味もある(Idiomatic and Syntactic English Dictionary)。
この観点から、「資本主義終焉論」の先にある「日本再生計画」でも必ず主要な分野となる環境・エネルギー問題を、知識社会学的な機能分析法で論じる一番の理由は、自然科学や工学系の環境や「再エネ」装置の構造などについて私は素人の域を超えないからである。しかし、「知識が社会的制約を受けている」(マンハイム、1931=1973:152)、ないしは「理論および思考様式の社会的被制約性」(同上:152)という認識からすれば、様々なメディアで流されている主張をある程度整理することは可能である。
それは科学的知識の活用としても必要な試みであり、パーソンズがいう①経験的妥当性、②論理的明晰性ないしは個々の命題の正確さ、③命題間の論理的一貫性、④いくつかの原理の一般性を判断基準としても取り込める(パーソンズ、1951=1974:334)。本節での「再エネ」論の知識社会学は、「日本再生計画」のために行う「系統立った知識体系の再編成」(同上:335)の一環をなすという位置づけにある。
さて、まずは機能分析の簡単なまとめをしておこう。本連載全体として、各方面で期待が高まる「再エネ」が従来の火発と原発に対して、「機能的等価性」(functional equivalents)をもつほど優れているかのという問題解明を行う。機能分析法としてマートンが体系化したのが社会学的機能主義(正・逆機能、顕在・潜在機能)であり、機能的等価性の有無についての判断はその一翼を占める。
その出発点は、「社会的機能とは、観察しうる客観的諸結果を指すものであって、主観的意向(ねらい、動機、目的)を指すものではない」(マートン、1957=1961:20)にある。ここでいう機能とは、「一定の体系の適応ないし調整を促す観察結果であり、逆機能とは、この体系の適応ないし調整を減ずる観察結果である」(同上:46)。
機能とは人々の意向やニーズではなく観察された結果、すなわち言動と行動が引き起こした具体的事実を意味する。選挙でいえば、「投票行動」による票数が示す結果であり、マスコミによる事前のアンケート調査や出口調査などの結果ではない。個人でも法人組織や一般的集団でも、ある行動が社会システムと適応する際には正機能、適応を減じて阻害する場合には逆機能と命名される。
マートンの貢献は、この正機能と逆機能をしっかり区別した点にある。「逆機能の概念は、構造的平面におけるひずみ、圧迫、緊張の概念を含む」(同上:48)。正・逆機能の区別はあらゆる行動に適用可能な社会学の分析用具である。たとえば受験勉強の正機能としては、英語に強くなり、国語の総合力が高まり、世界史的な視野が得られ、数学的なセンスと合理性を磨くことなどがあげられる。一方その逆機能には、青春時代の関心を受験教科の学習に限定し、音楽やスポーツにも縁遠くなり、受験ストレスが嵩じて、心身ともに体調を崩してしまう、家族関係がうまくいかないなどが指摘されてきた。
「再エネ」でいえば、今日の「推進派」によって完全に黙殺されてきた「ひずみ、圧迫、緊張」としての自然攪乱、景観破壊、聴覚異常や不眠ストレスなどの健康被害などもまた、議論の素材に組み入れることになる注2)。
そして、もう一つの貢献である機能の顕在性と潜在性の区別もマートンの功績である。すなわち、「顕在的機能とは、一定の体系の適応ないし調整に貢献する客観的結果であって、しかもこの体系の参与者によって意図され認知されたもの」(同上:46)であり、逆に「潜在的機能は意図されず、認知されないもの」(同上:46)とされた。しかし、企画建設に参与した業者には意図されず、認知されないが、実際には太陽光発電設備工事の不徹底により、集中豪雨の際には土砂崩れや土石流災害が発生してきた歴史がある。これは潜在的逆機能の典型である注3)。
たとえばクルマの購入動機の筆頭である顕在的正機能には、気象条件を問わず、目的地まで思い通りのコースで時間の制約もなく出かけられることが挙げられる。これに対して運転者が意図しない潜在的正機能は、運動不足による足腰の脆弱化になる。これが顕在的逆機能になると、休日などでは渋滞に巻き込まれ、目的地まで予定時間内に到着できなかったり、維持費がかさみすぎて、クルマのある生活が楽しめないなどが例示できる。さらに潜在的逆機能では運転中の事故による死傷、ないしは排ガスによる大気汚染などもあげられる。
この4通りの組合せで、多くは個人行動を事例とした機能的説明を行うが、法人組織や一般的集団の行動にもこれは等しく適用できる。具体的にいえば、食品企業による安くて美味しい商品の開発で喜ぶ国民にとっては、その商品は顕在的正機能を発揮するといえるが、アレルギー物質が含まれていて、たまたまそれを食べた人がアレルギー反応により苦しんだら、たちまちそれは顕在的逆機能を発揮したことになる。
このような内容の機能分析を用いて、国民生活でも産業活動でも等しく根源的な資源の代表として、「再エネ」を中心とした発電と発電形態を取り上げて、その機能について思考実験をしてみよう注4)。現代の根源的な資源には、電力のほかにもたとえば水、空気、森林、山林、河川、海洋などの自然資源や、ガス、上下水道、道路、港湾、公園、交通機関、病院診療所、交番、郵便局、銀行支店、小中学校などの貴重な社会資源がある。このうち電力を含む後者は「社会的共通資本」(social common capital)と命名されて、多方面からの研究がなされてきた(宇沢、2000)。
この電力という資源は、民営ではあるが極めて公共性が強い発電所を持つ会社が、国民全体にも産業界その他にもビジネスとして提供してきた歴史をもつ。時代的にいえば、明治期の水力発電から石炭火力、石油火力、LNG火力発電などを経て、昭和の後半1970年からは原子力発電所が登場した。その後は徐々に原発比率が高まり、最盛期にはそれが35%、火力が50%、水力が10%、その他が5%程度の比率で安定していた。
日本では2011年の「3.11」後の10年間で、原発事故による放射能汚染への危惧と「脱炭素」と「二酸化炭素地球温暖化」防止を目的として、最終的には「石炭火力発電」を全廃して、「再エネ」100%を目指すという主張が形成された。
世界的には1988年までの30年間は「地球寒冷化」の心配が大勢を占めていたのに、その年の6月にNASAのハンセンによるアメリカ上院公聴会での「二酸化炭素地球温暖化」論が出された後は、「地球寒冷化」時代と同じような二酸化炭素の排出量の増大にもかかわらず、「地球温暖化」論へと変貌した。二酸化炭素の濃度上昇は変わらないのに、1989年から文字通り雪崩を打って「地球寒冷化」論が捨てられて、「地球温暖化」論が形成された。そしてそれに乗じる形で「国連気候変動枠組み条約締約国会議」(COP)が継続されてきた。
主な活動目的である「脱炭素」と「二酸化炭素地球温暖化」防止という理念自体にも疑問があるが、本連載ではむしろその2つの理念を体現しているとされる「再エネ」が、従来の電源の主力であった火発と原発と機能的に等価であるかどうかを論証したい。それらを5つの下位領域、すなわち①目標年、②基準年、③発電所の敷地面積、④発電単価、⑤二酸化炭素の排出量にわけて比較分析する。そしていずれの領域でも、「再エネ」はウェーバーのいう資本主義のコアである「合理性」を満たしていないことを証明する。
資本主義を生み出してそれを促進する「合理性」は、ウェーバーにより次のように表現されていた。「合理的なる持続的企業・合理的簿記,合理的技術・合理的法律」と「合理的精神・生活態度の合理化・合理的なる経済倫理」である(ウェーバー、1924=1955 下:237)。この「合理性」は、近未来の新しい経済社会システムでは変質するのかしないのか。
要するに、「再エネ」と火発・原発との間における交換に、どのような相互利益があるのかを考えたい。「再エネ」論では現在のように「自然に優しい」、「放射能を出さない」、「二酸化炭素を排出しない」という顕在的正機能だけの議論しかなく、潜在的正機能、顕在的逆機能、潜在的逆機能などの議論を省略していいのかという問いかけを行う。次回以降では、いずれも具体的な資料を使いながら分析してみたい。
- 注1)
- 『北方ジャーナル』第50巻第11号(2021年11月1日)では、石狩湾岸の風力発電機でもこのような健康被害の危険性が指摘されている。
- 注2)
- 社会現象の総合的把握には、科学的な専門知とともに、人類の英知としての「ことわざ」に象徴される民衆知もまた活用したい。これについては金子(2020)を参照してほしい。
- 注3)
- これらの組み合わせは、要約版の表1を参照してほしい。
- 注4)
- 詳しい機能分析の概観、方法、事例研究は金子(2018)第3章で行なっている。