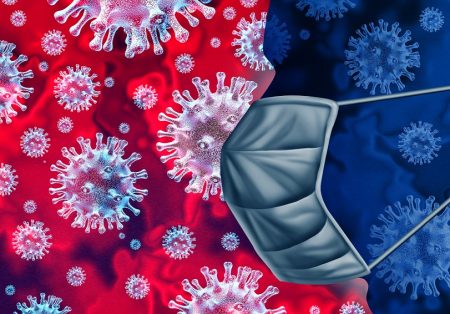双葉町レポート(2):避難と記憶
越智 小枝
相馬中央病院 非常勤医師/東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 講師
福島第一原発事故後の議論の中で、いまだに解の見えない問題に、「避難指示」があります。避難すべきか否か、避難区域の設定はどうすべきか、避難時の適切なコミュニケーションは。様々な切り口がありますが、そのすべてについて、未だ明確な答えはありません。
地震・津波という大災害の後に出された避難指示に対し、人々はどのように反応したのか。実際に避難された方の体験をお聞きすることは、私たちにとって貴重な学びの機会です。しかし人の記憶は必ずしも当時を正確に反映するとは限りません。たとえば、災害弱者と言われる高齢者や子どもは、その時のことを正確に語ることができないことも多いでしょう。また、一番辛い記憶は人に言うことができない、という方もいます。そのような時、時に人以上に雄弁に状況を語ることができるのが、現場に残された「物の記憶」です。
双葉町には当時の避難の日のままの爪痕が残されています。辛い風景ではありますが、それは同時に当時そこにいた方々の、言葉にされなかった貴重な「記憶」ではないかと思います。
地震・津波・そして原発事故というトリプル災害は全く同時に起きたわけではありません。本稿では、双葉町で見た3つの施設から、各々の災害の発災時に人がどのように避難していったのか、当時を振り返ることができます。
地震からの避難:双葉南小学校
双葉南小学校は、原子力発電所から3㎞ほどと近いため、3月11日には夕方に体育館の一部へ近隣の方が10名程度避難したもののすぐに別の避難所へ移動し、その後一度も避難所にならなかった場所です。そのため、ここには地震が起きた直後の状態が今も残されています。
その日はちょうど大掃除とワックスがけの予定だったようで、机は全て教室の外に出されていました。その教室の床に、生徒が整列したままの状態でランドセルが置き去りにされています。玄関の靴箱周辺にもランドセルが散らばり、運動靴もそのまま残っていることから、一部の生徒は下校直前に地震に遭い、そのまま戻ってこなかったことがうかがわれます。
大地震の後建物の中に戻ることは危険です。
「建物は無事だったし、ランドセルは地震が落ち着いたら取りに戻ろうね」
大切なランドセルを取りに戻りたがる子どもたちを説得して帰宅させた親御さんもいたかもしれません。
「ここにランドセルが置かれている、っていうことは、この子どもたちは、避難先の始業式を使い慣れた自分のランドセルなしで迎えたっていうことです」。
Hさんの娘さんも当時小学生1年生だったといいます。私自身も転校の経験がありますが、周りが持っている普通のものを持っていないというだけでちょっとしたいじめの対象になりました。ランドセルも教科書も体操服も持たないままに突然始めなくてはいけなかった転校生活を想像するだけで胸が詰まります。
「ランドセルや思い出の品を取り戻したい、っていう声はなかったんですか?」
思わず口をついた質問でしたが、回答を聞いて私は自分の無神経に気づきました。
「震災直後には保護者からの数件問い合わせがありました。思い出の品を取り戻したい気持ちはあったと思うんですが、あまり聞きません。当時は取り戻しても放射能に汚染されている可能性があると考えて、使えなかったと思います」
あまりにも「そのまま」の風景にすっかり忘れてしまっていましたが、ここにある「思い出の品」は、すべて「放射能に汚染された物」という言葉がつきまといます。素直に懐かしんで、触れて、抱きしめることができない。それはもしかしたら物だけに限らず、震災以前の「思い出」全てに言えることなのかもしれません。
子どもたちは、15歳になれば帰還困難区域に入ることができます。そんな子どもたちが、いつか思い出を取り戻したいと思えるのだろうか。そんなことが気にかかりました。
津波避難と避難指示:双葉北小学校
一方、双葉北小学校は震災の後700名ほどの住民の避難所となり、Hさんの家族もこの小学校で夜を明かしました。教室の黒板には、子どもの字と思われる筆跡でたくさんの書き込みがされていました。
「地しんがきてもおちついて」
「たすかる」
「つなみはね ぜったいこない だいじょうぶ」
子どもたちが一生懸命書いた文字に、当時の地震と津波への恐怖が伝わってきます。
不安な一夜を明かした双葉北小学校の人々に災害対策本部から指示が入ったのは3月12日の朝のことです。
その日、別の避難所となっていた双葉中学校で避難所運営にあたっていたHさんは、校内放送で皆に避難を呼びかけたといいます。
「朝7時30分ごろに、校内放送で『原発が危険な状態なので国道288号線を使って、西に避難してください』と放送しました。『念のため』と言ったかどうかは覚えていません。車を持たずに避難してきた人は、車で避難される方の隙間に乗せてもらいました。でも、西にどのくらい離れるのか、どこへ行くべきなのかどれくらい急ぐのか、などの情報はありませんでした。結果的にはこの放送が町の人を分断してしまったんです」。
これは私の勝手な推測ですが、Hさんは震災の後、ご自身の放送内容を何度も反芻されたのではないかと思います。たとえ指示通りの放送だったとしても、自分の放送が町の分断につながった。その思いから、自分の放送を顧みないわけにはいかないでしょう。それでも当時自分がどんな放送をしたかも含め、当時のことをすべては思い出せない、とHさんは言います。
「地震の時町内のお店の中にいました。地震が起きて、店を飛び出しました。向かいの家が壊れかけていて、その前で腰が抜けている人を助けたことは覚えています…でも、避難所に着くまでの記憶を含め、一部の記憶がどうしても思い出せません」。
原発事故の避難を考える時、私たちはその前に起きた地震と津波という出来事が人々に与えた影響を、十分想像できていないのかもしれません。どうやって家に帰ったかわからない、その日の夕飯を食べたのかどうかを思い出せない…そんな記憶の欠如は、他の被災者の方々からも時折聞くお話です。私はこのような反応を精神的ショックによる事故防護反応では、と考えていました。しかしHさん自身は、純粋に「パニックに陥っていた」というものとは少し異なるのでは、と自己分析されています。
「震災当時はあまりにも現実離れした出来事が多くて、決してパニックになっていたわけでもなく、夢の中にいるような不思議な感覚だったことを記憶しています。忌まわしい過去を記憶から消し去ろうという自己能力が働いているわけではなく、単純に『情報過多』の中で、記憶に無いのかな、と自分では感じています」。
小学校に残された地震・津波の跡を見ると、Hさんの言われる「情報過多」という言葉に非常に納得がいきます。災害時の情報というのは、暗闇の向こうから断片的な情報が次々に投げ込まれてくるような状態です。その断片がいずれも平時には想像もつかないような情報であったら。そう考えると、当時の情報が混乱したように見える原因は、いわゆるコミュニケーションの不備という単純な問題ではなかったように思えてきます。
では同じような状況であった避難所の人々に、Hさんの校内放送はどのように伝わったのでしょうか。
「放送の約30分後には、700人ほどいた避難者は全員いなくなっていました。『川俣町まで避難してください』という情報が町内放送で流れたのはその15分後くらいです。この放送を聞いていた人は川俣町でとどまりましたが、それを聞き逃して田村や郡山まで避難した人もいました」。
700名が30分でいなくなるというのは尋常ではないスピードです。それでもHさんは、その時点では多くの人はこの避難をさほど深刻に受け止めていなかった、と言います。
「最初に2-3㎞だったのが10㎞、20kmまで広がっちゃったな、爆発するとは思っていないから念のために逃げるんだ、という程度の気持ちでした…まさか7年半たっても帰れないなんて、皆思っていなかったですよ」。
おそらくその前日に受けたショックに比べれば、まだ爆発していない原発は深刻には感じられなかったのかもしれない。あるいは「これ以上悪いことが起こる」という想像を頭が受け付けなかったのかもしれません。いずれにしても、避難時に多くの方は比較的冷静な状態であったようです。