都市の代案、200年後を見据え
書評:「風の谷」という希望ー残すに値する未来をつくる 著者 安宅和人
竹内 純子
国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授
(「電気新聞 本棚から一冊『「風の谷」という希望』より転載:2025年7月11日)
「風の谷」を紹介するところから始めなければならないだろう。人類は急速に都市化を進めている。本書も「都市への人口集中は、人類の本質的なニーズと社会の発展方向性に合致した、論理的な帰結」と評するが、しかし、都市しか選択肢がないという未来は果たして正しいのか。
都市集中型社会に対するオルタナティブである疎空間を「風の谷」と呼び、その実現を目指す試みに参加するメンバーはいま、極めて多様なバックグラウンドを持つ100人弱までになっている。自然(森)、インフラ、エネルギー、ヘルスケア、教育、食と農など分野ごとに検討を進め、定期的に全体でも共有・議論する。実際に風の谷に適した土地を探し、その地域の方々と関係性を構築する機会もあり、私も含めてメンバーは皆、楽しみながらボランタリーに参加している。
とんでもないメンバーによる、酔狂な課外活動といえばそうかもしれない。しかし、社会の変革は幅広で深い検討と長い時間を必要とするのであり、コンパクトシティーやエコビレッジ、村おこしなど、風の谷と似て非なるものとの違いを一つ述べるならば、「簡単に答えを求めない」ことか。風の谷は200年後を目指している。
本書は、7年半にわたる活動で交わされた膨大な議論を土壌とした一つの果実である。未来を語る本はあまたあるが、現状の否定とそこから編み出されたビジョンの提示に力点が置かれ、実現に向けた道筋は、特定のある領域からの示唆にとどまることが多い。各省庁が描く将来構想も似ている。それらも重要な指針だが、示す未来の実現可能性は乏しいと言わざるを得ない。なぜなら、社会を構成する要素は複雑に絡み合っており、部分的な変革はどこかで齟齬をきたすし、うまくいかなかった場合の他責を可能とする。本書にはそうした逃げ場は一切ない。著者の人格だろう、希望とやる気を与えてくれる。社会・空間の変革を自分事とするには、こうした思考が必要だということだろう。
幅広い領域の極めて深い議論でありながら、専門家が読んでも素人が読んでも極めて明快でわかりやすい。私がこの試みのメンバーであることを差し引いてもそう感じるのは、問いを立てる力、数値的に分析する力、人々の理解を得る表現力のすべてにおいて、著者安宅和人氏が卓越した存在であるということを示している。
エネルギーインフラに関わる方々には必読の書であり、これから長くバイブルとなることは間違いがない。
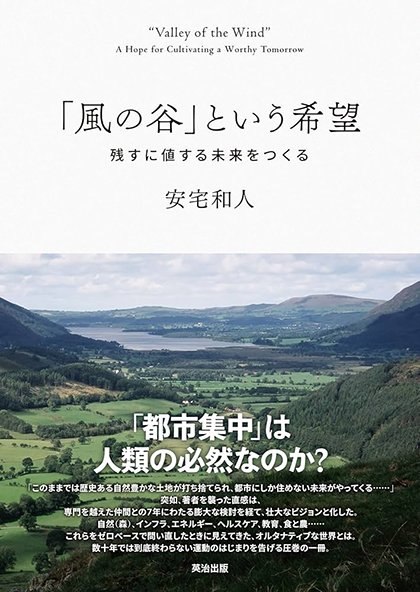
・タイトル:「風の谷」という希望
・著者:安宅 和人
・出版社:英治出版
・発売日:2025/7/30
・単行本:984頁
・ISBN-10:4862763502
・ISBN-13:978-4862763501
※一般社団法人日本電気協会に無断で転載することを禁ずる。




















