民間主導、戦略的な選択を検証
書評:著者 柳沢 崇史 現代日本の資源外交ー国家戦略としての「民間主導」の資源調達
竹内 純子
国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授
(「電気新聞 本棚から一冊『現代日本の資源外交/柳沢崇文 著』」より転載:2025年4月4日)
電力安定供給は、発電設備の十分な確保と、安定的な価格で燃料を十分に調達すること、そして健全な送配電網の維持の三拍子が揃わなければ成しえない。規制料金制度の下では発電設備や送配電網への投資が確保されていたため、わが国におけるエネルギー政策の中心は燃料確保にあり、資源外交は政府の主要政策の一つだった。
しかし、オイルショックから約50年が経過し、安定的な資源調達が「当たり前」になると、その重要性への認識が薄れてしまうのは人間の性か。欧州では、CO2削減をエネルギー政策の最重要課題と認識するあまり、長期契約から市場での燃料調達に軸足を移していたことが、ロシア・ウクライナ戦争によるエネルギー危機をより深刻なものとした。
しかしわが国もそれを対岸の火事と眺めていることはできない。電力自由化の進展と再生可能エネルギーの導入拡大により、稼働率が悪化した発電設備の休廃止が進み供給力が低下しただけでなく、LNGの長期契約が急速に減少したため、数年後に再びエネルギー危機が起きた場合、わが国はエネルギー価格高騰に苦しんだ今回の欧州諸国の、まさに二の舞いとなる。さらに石炭は、温暖化対策の機運の高まりもあって、上流投資が決定的に不足している。
電気事業を切り口に考えても、脱炭素社会への極めて長い移行期間における化石燃料の安定的確保に向け、資源外交が極めて重要な局面にあることは明白だ。
本書の問いは、「石油危機以降、政府としてエネルギー安全保障を軍事的安全保障と並ぶ国家課題としたのにもかかわらず、なぜ日本のエネルギー調達は民間主導の形が維持されたのか」。石油危機前後で、政府の関与・支援を強化させた欧州諸国を比較対象としつつ、さまざまなプロジェクトを巡る資源外交を振り返り、日本政府と企業が「戦略的に民間主導の形を選択した」という仮説を検証している。
事例を振り返る中で、資源外交を円滑に進めるには、いかに官民を挙げての戦略的対応が必要であったかを認識させられる。今年2月の日米首脳会談でも話題に上ったアラスカLNGプロジェクトも1980年代からの懸案事項だったことを本書は詳らかにしている。
わが国の政府・企業が、エネルギー調達を「戦略的に」民間主導にしてきたとして、では、近年行った電力・ガス事業の自由化は資源外交に関してどのような戦略を描いていたのだろうか。そのさらなる問いも投げかけたくなる、まさに今が「読みどき」の一冊だ。
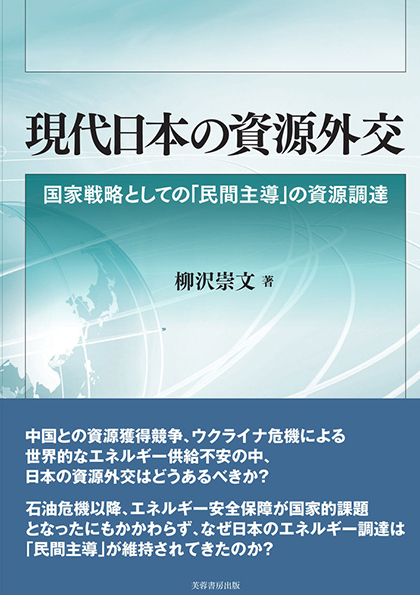
・著者:柳沢 崇文
・出版社:芙蓉書房出版
・発売日:2024/1/25
・ISBN-10:4829508728
・ISBN-13:978-4829508725
※一般社団法人日本電気協会に無断で転載することを禁ず




















