2014年11月のアーカイブ
-
 2014/11/28
2014/11/28CO2削減の「イノベーション・シナリオ」
-
 2014/11/27
2014/11/27レシプロエンジン発電で風力発電の出力変動に対応
-
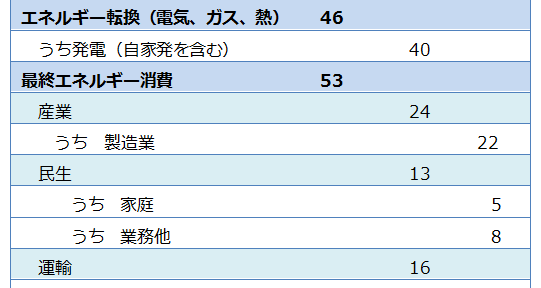 2014/11/25
2014/11/25水素社会を拓くエネルギー・キャリア(5)
「水素社会」の実現のために必要なこと -
 2014/11/21
2014/11/21原子力推進策?差額調整契約制度の実相
英国発の原子力CfD制度 -
 2014/11/19
2014/11/19電力会社が再エネの接続を保留
固定価格買い取り制度(FIT)の本質的欠陥 -
 2014/11/17
2014/11/17中小企業経営から見た電力問題
-負担限界を考えないエネルギー政策の迷惑- -
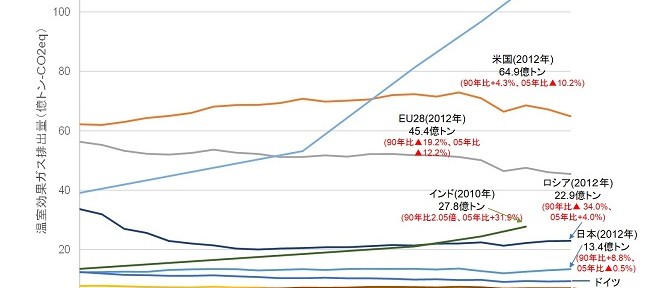 2014/11/14
2014/11/14【速報】米中が温暖化目標を発表 どうする日本
-
 2014/11/12
2014/11/12混迷するエネルギー政策のなかで
安全な原発「高温ガス炉」が用いられる時代がくる? -
 2014/11/11
2014/11/11経済学を知らない経営者と経営を知らない経済学者
-
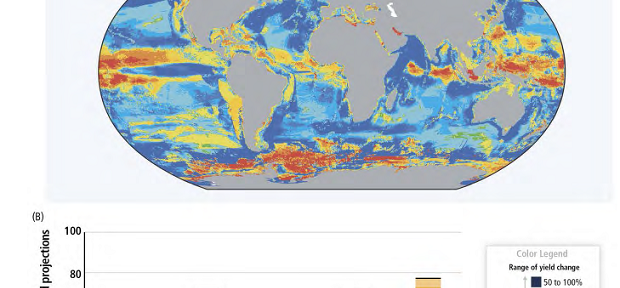 2014/11/10
2014/11/10IPCC統合報告書の問題点(速報)
-
 2014/11/07
2014/11/071%イコール1兆円
数値目標の本当のコスト -
 2014/11/06
2014/11/06再生可能エネルギーの普及策 抜本見直しを(前編)
-
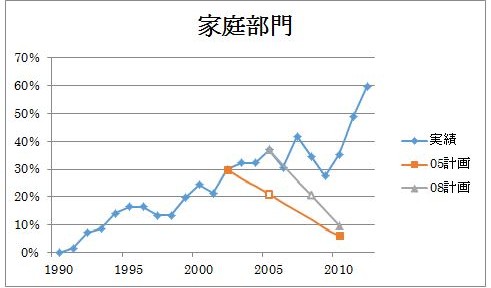 2014/11/04
2014/11/04CO2の排出量は計画できない
「数値目標」ではなく「参考数値」とすべし













