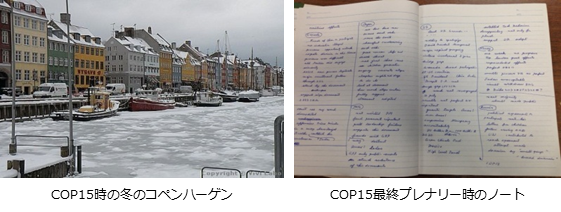私的京都議定書始末記(その32)
-COP15が残したもの-
有馬 純
国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授
COP15が終わって日本に戻ると、各方面に対してその結果を説明する業務に追われた。鳩山首相を含む100数十カ国の首脳が参加する大会議であっただけに、会議中も連日ニュースで報道され、日本国内における関心も非常に高いものがあった。欧米のメディアはCOP15は大失敗だったという報道が躍っていた。会議中の混沌とした状況から解放され、各方面に説明をしていく過程の中で、COP15の残したものとその意味合いについての考えが徐々にまとまっていった・・・・。
第一に「留意」に終わったとはいえ、コペンハーゲン合意の意義は非常に大きいということだ。会合終盤、議長国デンマークが指導力を喪失し、「このままでは多くの首脳を集めたCOP15は何の成果もなく終わることになる」という危機感から、通常では考えられない首脳レベルのドラフティングが急遽行われ、その結果、生まれたのがコペンハーゲン合意である。これは当初、想定されていないシナリオであったが、主要排出国、最貧国、島嶼国等を含む26ヶ国の首脳がドラフトし、合意したことは文書に大きな重みを与えることになった。交渉官レベルで積み上げられたAWG-LCAテキストのどうしようもない泥沼から、重要な論点を抽出し、合意文書ができた。職業交渉官、いや「交渉屋」に任せていたのでは永遠に合意は不可能であったろう。
第二にコペンハーゲン合意は米国、中国、インド等の主要排出国が参加する新たな国際枠組みの青写真を提示しており、先進国・途上国の二分法に呪縛された京都議定書のパラダイムから大きく踏み出したということだ。先進国だけが削減目標を設定し、その履行義務を負うという京都議定書のパラダイムは1997年当時はそれなりの意味があったかもしれない。しかしこれは「米国が参加していれば」の話であり、米国が京都議定書から離脱し、主要途上国を含め、途上国の排出量が世界の半分近くを占めるようになった2009年時点では、将来枠組みのモデルにはなり得ない。先進国と途上国がそれぞれ緩和目標、緩和行動を別表に登録し、途上国の緩和行動についても計測・報告・検証(MRV)の対象とするというプレッジ&レビューの考え方に基づくコペンハーゲン合意のエッセンスは、ポスト京都の土台といえよう。
もとよりコペンハーゲン合意は土台であり、これを枠組みに仕立て上げていくためには多くの作業を必要とする。また首脳レベル合意に中国が参加していたといっても、彼らがどの程度、本気で賛成していたか疑問もあった。コペンハーゲンの最後の夜、中国からはコペンハーゲン合意の採択を主張する発言がなかった(事実、その後の交渉の中で「コペンハーゲン合意は採択された文書ではない」等、コペンハーゲン合意の位置づけを下げる発言をしばしば聞くことになる)。
とはいえ、コペンハーゲン合意の歴史的意義は大きい。今、この原稿をワルシャワのCOP19に参加しながら書いているが、コペンハーゲンからカンクン(2010年)、ダーバン(2011年)、ドーハ(2012年)を経て現在に至る将来枠組みの議論はコペンハーゲン合意の考え方に淵源を有すると言える。したがってメディアや環境NGOの批判とは異なり、COP15は歴史的意義のある会合であったというのが私の見方である。
第三にEUは深い挫折感を味わうことになった。欧州の中でも環境保全を声高に叫んでいたデンマークがCOP15を半ば強引にコペンハーゲンに招致したのは、2009年の国際合意を欧州の地で成立させようというEUの強い意欲の体現でもあった。しかし蓋を開けてみればデンマークは議長国としての存在感を示すことができず、コペンハーゲン合意の最も重要な調整局面は米国と中国、インド、南ア、ブラジル首脳の膝詰め談判であり、そこにEUの姿はない。「温暖化防止で自分たちが世界のリーダーとして率先垂範する」というEUの自尊心が大きく傷ついたであろうことは想像に難くない。それまで日本や米国とともに一つの法的枠組みを主張してきた欧州がコペンハーゲン以後、ポジションを変え、京都議定書第二約束期間と新たな枠組みの二本立てを受容するようになったことの背景には欧州の存在感を取り戻したいという思いと無関係ではないようにも思える。
第四にコペンハーゲンにおける最後の混乱は、国連交渉プロセスの限界を露呈した。主要排出国を含む26ヶ国の首脳が合意した文書が、一握りの国の反対によって合意を阻まれた。194ヶ国が全員合意しなければ前に進めないシステムは、これまでもいたるところで交渉の進展をブロックしてきた。MEFに参加している20カ国未満の国で世界の排出量の8割近くを占める。G20で見れば、カバー率はもっと高くなる。温暖化問題の緊急性を考えれば、194ヶ国の交渉を延々と続けることが果たして良い事なのか?貿易の世界ではWTO交渉がデッドロックに陥り、二国間、複数国間、地域レベルのFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)が生まれている。気候変動の世界においても国連以外の場で物事を前に進めることはできないのか?コペンハーゲン後、こうした問題提起を色々な場で見るようになった。例えばフランスのサルコジ大統領は「気候変動枠組み条約の192ヶ国の締約国の間で全てのイシューを同時に交渉し、全員一致の承認が必要だというフォーマットはやめる(ditch)べき」と発言し、国連システムの改革と少数国会合の活用を提言した。
しかし、コペンハーゲン直後に盛り上がった国連以外のプロセスを追求すべきという動きは、結局、実を結ばなかった。最大の要因は中国、インド等の主要排出国がMEFやG20等の少人国会合の場で気候変動の実質的なディールをすることを頑として拒否していたことである。彼らにとって途上国が圧倒的な数をしめる国連プロセスの方が、自分たちにスポットライトが当たる少数国プロセスよりも居心地がよいことは明らかだった。FTAやEPAの場合、合意国の間で貿易・投資がより自由化されるというメリットを享受できるが、温室効果ガス削減というマイナスサムゲームの場合、中国やインドを抜きにして合意してもフリーライダーを許すだけであり、全く意味がない。何より、そのような枠組みには米国が参加しない。唯一、ありえる方策はアウトサイダーに炭素関税等の国境調整措置を講ずることで、フランスはこうした方策に強い関心を示していたが、WTOとの整合性等の面で大きな疑問があった。環境目的での貿易制限措置(例えば炭素関税の賦課)がWTO上可能なのかどうかは専門家の間でも意見が分かれていたことに加え、炭素関税の根拠となる輸入品の炭素含有量を客観的に計算できるのかという技術的困難もある。更に中国、インド等からの報復措置等の貿易戦争を招来し、先進国も返り血を浴びる可能性があったからだ。
また、国連システムには不思議な「自律回復力」がある。コペンハーゲン後に国連システムの有効性に重大な疑問符が付いたが、後述するように、COP16議長国メキシコは国連プロセスへの信頼回復を大きなミッションとし、優れた外交調整能力でCOP16を成功に導いた。COPが二度続けて失敗すれば、COPのレジティマシー(正統性)が地に落ちる、自分たちの寄りどころがなくなってしまう。交渉プロセスにぶら下がっている職業交渉屋にはそうした本能があるのではないかと穿った見方をしたくなる。
第五に、直前の論点と関連することだが、「納得のプロセス」の重要性である。土曜日の午前3時に全体会合を開催し、1時間でテキストを採択してほしいというのは乱暴すぎた。仮に土曜日の夕方までかけて少数国会合に参加していなかった国々への根回しをしていれば、最終局面での混乱があれほどひどいものにはならなかったろう。あるいは首脳プロセスがもっと早く始まっていたら結果は違ったかもしれない。議長国デンマークが議長テキストを出す機会を逸し、不毛な事務レベル交渉を続けてしまったことで失われた時間は大きい。これも後述するが、COP16議長国のメキシコは、この失敗の経験を最大限活かし、会合を成功に導くことになる。
最後に日本の存在感である。日本は25%目標と150億ドルの鳩山イニシアティブをかかげて交渉に臨んだ。会合後に外務省が発表した「概要と評価」には「議長国デンマーク政府との連携、米国等他の先進国との協調、中国をはじめとする途上国への働きかけ等を進めながら、交渉に参画、貢献した」とある。首脳レベル交渉に入っていないので、鳩山首相がその場でどのような発言、貢献をしたのかは承知していない。しかし公平に見ればコペンハーゲン合意の策定に日本が貢献したとは言い難い。「高い目標を掲げて交渉にポジティブな影響を与える」という狙いが奏功したとも思えない。仮に日本の目標が90年比40%減であったとしても、2005年比15%減のままであったとしても、COP15は同じような展開を辿ったであろう。ちなみにワルシャワのCOP19では日本の2005年比3.8%減という新目標が「国際交渉に悪影響を与える」と批判されている。ワルシャワでの交渉は例によって難航しているが、日本が90年比25%減を維持したとしても交渉が好転していたとは思えない。「日本の目標値で交渉を左右する」という自意識過剰の発想からは卒業した方が良いと思われる。
コペンハーゲンから戻って各方面への説明を終える頃には年の瀬になっていた。2010年の交渉の道行きはまだ全く見えなかったが、まずは交渉のことを忘れたかった。寒く、暗く、何でも高価なコペンハーゲンから戻ると、日本で過ごす年末年始はこの上もなく心地よく思われた。